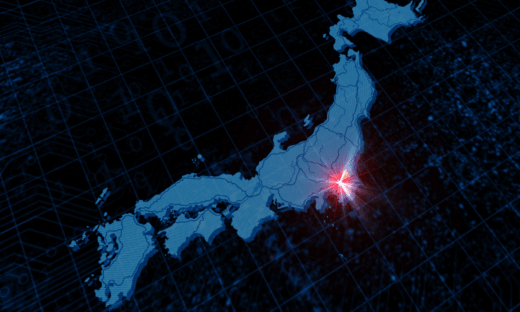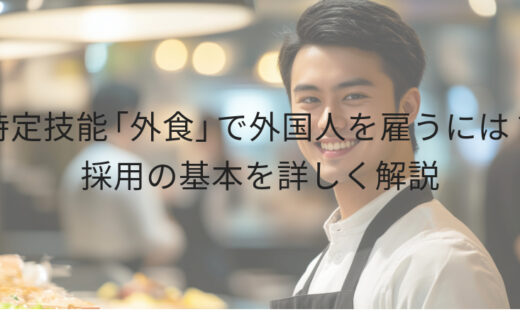特定技能【建設】を受け入れる際の手続きと留意点

建設業界では深刻な人手不足が続いており、その解決策の一つとして「特定技能」制度が注目されています。
本制度は、一定の技能や日本語能力を持つ外国人労働者を受け入れ、建設業の現場で即戦力として活躍してもらうことを目的としています。
しかし、特定技能の仕組みや採用の流れ、受け入れ企業が守るべきルールなど、制度を正しく理解しなければ円滑な活用は難しいのが現状です。
本記事では、特定技能「建設業」の概要から、外国人を雇用するメリット、対象職種と業務内容、採用条件や手続きの流れ、注意点までを詳しく解説します。
これから特定技能外国人の採用を検討している企業の人事担当者や経営者の方にとって、実務に役立つ情報を提供します。
特定技能「建設業」とは?制度の概要

建設業界では慢性的な人手不足が続いており、その解決策として特定技能制度が導入されました。
特に「特定技能1号」は、即戦力となる外国人労働者を受け入れるための仕組みであり、一定の技能試験と日本語能力を満たせば就労が可能です。
本章では、特定技能制度の背景や、建設分野における1号・2号の違いについて詳しく解説します。
特定技能制度の背景と目的
外国人労働者の受け入れが求められる背景
日本では少子高齢化が進み、多くの産業で労働力不足が深刻化しています。
特に建設業は高齢化が顕著であり、若年層の就業者が減少しているため、技能を持つ労働者の確保が急務となっています。こうした状況を受け、政府は2019年に「特定技能」制度を創設し、即戦力となる外国人労働者の受け入れを拡大しました。
建設業界における人手不足の深刻化と今後の見通し
建設業界では、高度経済成長期に活躍したベテラン作業員の大量引退が進み、特に現場作業員の減少が深刻です。
国土交通省のデータによると、建設業就業者の約3割が55歳以上であり、若手の担い手不足が大きな課題となっています。今後、国内人材だけでは労働力の確保が難しいことから、特定技能外国人の活用がますます重要になると考えられています。
特定技能1号・2号の違いと建設業での位置づけ
特定技能1号の要件と業務範囲
特定技能1号は、一定の技能と日本語能力を持ち、即戦力として業務に従事できる外国人を対象とした在留資格です。建設業においては、型枠施工や鉄筋施工、左官、建設機械施工など 18の作業分野 での就労が可能です。
特定技能1号の要件
- 建設分野の「特定技能評価試験」に合格していること
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上、またはJFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)A2レベル以上
- 健康であり、受け入れ企業の基準を満たすこと
業務範囲
特定技能1号は 現場作業を中心とした業務 に従事することが認められており、 指導的な役割は担えません。また、雇用主は「建設特定技能受入計画」を国土交通省に提出し、承認を受ける必要があります。
特定技能2号の取得条件とキャリアパス
特定技能2号は、特定技能1号より 高度な技術と経験 を持つ外国人が対象で、 現場監督や指導的立場 での業務が可能になります。2024年4月より建設業も特定技能2号の対象分野となり、長期的な就労が可能になりました。
特定技能2号の取得条件:
- 特定技能1号での実務経験(一定年数以上)
- 建設分野の特定技能2号評価試験 に合格すること
キャリアパス:
特定技能2号を取得すると、在留期間の上限がなくなり、家族の帯同 も認められます。また、建設分野でのスキルをさらに磨き、技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ への移行や、日本の建設業界で管理職としてのキャリアを築くことも可能です。
建設業界において特定技能1号・2号を活用することで、外国人労働者の長期的な定着が期待されており、人材不足の解消にもつながると考えられています。
特定技能「建設業」で外国人を雇用するメリット
近年、建設業界では慢性的な人手不足が深刻化しており、国内の若年層の労働力確保が難しくなっています。こうした状況の中で、特定技能制度を活用した外国人労働者の雇用は、企業にとって 即戦力の確保 や 労働力の安定化 につながる重要な手段となります。
慢性的な人手不足の解消と即戦力確保
日本人労働者の減少と外国人材の活用意義
建設業界では、高齢化の進行や若年層の就業者減少により、人手不足が慢性化しています。特に、技能を要する職種では、新規労働者の確保が難しく、業務の継続に支障をきたす企業も増えています。
こうした背景から、外国人材の活用が重要視されており、特定技能制度の導入によって 一定の技能を持つ労働者を確保できる仕組み が整えられました。国内で不足する労働力を補うだけでなく、意欲的な外国人労働者を迎え入れることで、企業の生産性向上にもつながります。
実務経験のある外国人を採用することで即戦力を確保
特定技能1号の対象者は、試験や実務経験を通じて 一定の技能レベルを証明 した労働者であり、企業は基礎的な教育の手間を省いて即戦力として採用することが可能です。
また、特定技能2号を取得すれば、さらに高度な業務に従事でき、長期的なキャリア形成が可能になります。技能と経験を持つ外国人労働者を活用することで、企業の競争力強化にも貢献できるのが大きなメリットです。
企業の成長と国際化への貢献
外国人労働者の受け入れによる企業のグローバル化
特定技能外国人を採用することで、企業のグローバル化が加速します。
建設業は、国内市場にとどまらず、海外展開や外国企業との協業が求められる場面も増えています。こうした環境の中で、外国人労働者の受け入れは 異文化理解を深め、企業の国際的な競争力を高める要素 となります。
また、外国人労働者が増えることで、社内のマニュアルや教育体制を整備する必要が生じ、 標準化・体系化された業務フローの構築 につながります。これにより、業務の属人化を防ぎ、効率的な運営が可能になります。
多様な人材がもたらす職場の活性化とイノベーション
多様な価値観や文化的背景を持つ外国人労働者が加わることで、職場の活性化が期待できます。新たな視点や発想がもたらされ、業務改善や新しい技術の導入に対する 柔軟な発想 が生まれることも少なくありません。
さらに、異文化交流が進むことで、日本人社員の グローバルな対応力やコミュニケーション能力の向上 にもつながります。
外国人労働者との協働を通じて、企業全体の組織力が向上し、 変化に強い企業文化 を育むことができるのもメリットの一つです。
特定技能「建設業」の対象職種と業務内容
特定技能「建設業」では、人手不足が深刻な建設分野 において、一定の技能や知識を持つ外国人労働者が活躍できる制度が整備されています。
本制度では、対象となる職種や業務が明確に定められており、それに沿った形で外国人の雇用が可能となります。
対象職種と業務範囲の概要
特定技能「建設業」では、14の職種 が対象として認められています。これらの職種は、特に人手不足が深刻であり、一定の技能を持つ外国人労働者の受け入れが求められている分野です。
建設業で受け入れ可能な14職種の詳細
現在、特定技能「建設業」で受け入れ可能な職種は以下の14職種に分類されます。
- 型枠施工
- 左官
- コンクリート圧送
- トンネル推進工
- 建設機械施工
- 鉄筋施工
- 土工
- 屋根ふき
- 電気通信
- 内装仕上げ
- 保温保冷
- 配管
- 建築大工
- 海洋土木工
これらの職種は、技能試験と日本語能力試験 をクリアした外国人労働者が就業可能な分野となっており、それぞれの業務内容が細かく定められています。
各職種の具体的な業務内容と適性
各職種の具体的な業務内容と適性
特定技能「建設業」では、以下の14職種が受け入れ対象となります。それぞれの業務内容と適性を簡潔にまとめます。
- 型枠施工:コンクリート構造物の型枠を組み立て・解体する作業。精密な測定と施工技術が求められる。
- 左官:壁や床を塗り仕上げる作業。手先の器用さと仕上げのセンスが重要。
- コンクリート圧送:ポンプを使いコンクリートを打設する作業。正確な操作技術が必要。
- トンネル推進工:トンネル工事の掘削や補強を行う。体力と専門的な知識が必要。
- 建設機械施工:ショベルカーやブルドーザーなどの重機を操作。操作技術と安全意識が求められる。
- 鉄筋施工:鉄筋を組み立て、コンクリート建築の骨組みを作る。正確性と体力が必要。
- 土工:掘削や埋戻し作業を行う。体力と現場作業の経験が活かせる。
- 屋根ふき:屋根材の取り付け・修理を行う。高所作業に慣れていることが望ましい。
- 電気通信:通信設備の設置・保守を行う。電気通信の知識と細かい作業が求められる。
- 内装仕上げ:壁紙や床材の施工を行う。細かい作業が得意な人に適している。
- 保温保冷:建築物の配管や設備の断熱・保温作業を担当。専門的な知識が必要。
- 配管:水道・ガスなどの配管工事。測定や接続の正確性が求められる。
- 建築大工:木材を使用した建築工事全般。日本の伝統技術を活かす機会もある。
- 海洋土木工:港湾・海上工事を担当。特殊な環境下での作業が求められる。
各職種には、それぞれ異なるスキルや適性が必要ですが、共通して安全管理の意識や現場での協調性が重要になります。
実際の業務と特定技能外国人の役割
特定技能「建設業」の外国人労働者は、建設現場の様々な業務を担い、日本人スタッフと連携しながら作業を進める ことが求められます。
特に、即戦力としての活躍が期待されるため、それぞれの職種に応じた専門的な業務に従事します。
建設現場での主な業務内容と期待される役割
特定技能外国人は、以下のような業務を担当することが多く、各職種において重要な役割を果たします。
- 型枠施工:型枠の組み立てや解体を行い、コンクリート工事の基礎を支える。
- 鉄筋施工:鉄筋の配置・固定を行い、建物の強度を確保する。
- コンクリート圧送:生コンクリートを現場に送り込み、正確に流し込む作業。
- 建設機械施工:ショベルカーやブルドーザーを操作し、土木作業を進める。
- 配管:水道やガスの配管設置、メンテナンスを担当。
- 内装仕上げ:壁や天井の仕上げ作業を行い、建物の最終的な外観を整える。
これらの業務において、特定技能外国人は日本人スタッフと協力しながら現場作業を進める ことが前提となります。特に、正確な施工と安全管理が求められる建設業では、日本の職人の技術を学びながら高い施工品質を維持すること が重要です。
日本人スタッフとの連携と業務サポートの重要性
建設現場では、日本人の技術者や現場監督と連携しながら作業を行う ため、以下の点が求められます。
- 現場での指示を正しく理解し、迅速に対応する
- 日本人スタッフと円滑なコミュニケーションを取る
- 安全管理を徹底し、事故を防ぐためのルールを守る
- 経験を積みながら、より高度な作業にも対応できるようになる
特定技能外国人は、単に労働力として雇用されるのではなく、日本の建設業の一員として現場を支える役割を担う ことが期待されます。特に、ベテランの技術者から技能を学び、将来的にはより責任のある業務を担当することも可能です。
また、日本人スタッフとの良好な関係を築くことで、職場環境の改善や多文化共生の促進 にも貢献できるでしょう。適切な指導体制のもと、外国人労働者が活躍しやすい環境を整えることが、企業にとっても重要なポイントとなります。
特定技能「建設業」での採用条件と要件

特定技能「建設業」で外国人を採用するためには、一定の条件と要件を満たす必要があります。
単に外国人労働者を雇用するだけでなく、適切なスキルや経験を持つ人材を採用し、法律に基づいた手続きを行うことが求められます。
ここでは、特定技能1号・2号の取得条件や、企業が満たすべき要件について詳しく解説します。
外国人が満たすべき要件(試験・資格など)
特定技能「建設業」で働くためには、外国人労働者が一定のスキルや日本語能力を証明する必要があります。主に技能試験と日本語能力試験の合格が求められ、さらに就労前後の研修も重要なポイントとなります。
技能試験と日本語能力試験の基準
外国人が特定技能1号として建設業で就労するには、以下の試験に合格する必要があります。
- 技能試験
・建設分野の特定技能評価試験に合格することが必須。
・過去に技能実習2号を修了している場合は試験免除となる。 - 日本語能力試験(いずれかに合格)
・日本語能力試験(JLPT)N4以上
・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
これらの試験をクリアすることで、業務遂行に必要な基礎知識と、日本での職場環境に適応するための最低限の言語能力が証明される。
特定技能外国人が受ける必要のある研修
特定技能外国人は、就労前後に義務付けられた研修を受ける必要があります。
- 就労前研修・日本の建設業のルールや安全管理に関する教育
・労働災害防止のための基本的な知識
・日本での生活に関するガイダンス - 入国後・就労後の研修・雇用企業または業界団体によるフォローアップ研修
・技能向上のためのOJT(実務研修)
これらの研修を通じて、外国人労働者が安全かつ適切に業務を遂行できるようサポートされる。
受け入れ企業の条件と義務
特定技能「建設業」で外国人を受け入れる企業には、一定の条件を満たし、必要な義務を果たすことが求められます。適切な受け入れ体制を整えることで、外国人労働者が安心して働ける環境を提供することが重要です。
建設特定技能受入計画の申請要件
特定技能外国人を雇用するには、建設特定技能受入計画を作成し、国土交通省に申請・認定を受ける必要があります。主な要件は以下の通りです。
- 建設業許可を取得していること
特定技能外国人を受け入れる企業は、該当業務の建設業許可を持っている必要がある。 - 建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録していること
労働者の技能やキャリアを適正に管理するため、受け入れ企業はCCUSへの登録が義務付けられている。 - 労働条件が適正であること
特定技能外国人の給与は、同等の業務を行う日本人と同等以上であることが求められる。 - 適切な労務管理体制を整備していること
外国人が安心して働けるよう、雇用契約や労働時間の管理を適切に行う必要がある。
企業が果たすべき支援義務と責任
受け入れ企業には、特定技能外国人がスムーズに働き、生活できるようさまざまな支援義務があります。
- 生活支援の義務・住居の確保や生活に関する情報提供(銀行口座開設、交通機関の利用方法など)
・日本での生活に適応するためのサポート(ゴミの分別、公共サービスの利用方法) - 労働環境の整備
・労働安全対策の実施(現場での安全講習や保護具の支給)
・日本人従業員とのコミュニケーションサポート(通訳の手配など) - 適正な雇用管理と報告義務
・特定技能外国人の勤務状況を定期的に報告
・建設特定技能受入計画の内容を適切に履行し、必要な場合は更新・変更手続きを行う
受け入れ企業は、単に労働力を確保するだけでなく、外国人労働者が安心して働ける環境を提供し、長期的な雇用関係を築くことが求められます。
特定技能「建設業」の採用プロセスと必要な手続き
特定技能外国人を採用するには、計画的なプロセスと各種手続きが必要です。適切な流れを理解し、スムーズな採用を進めましょう。
人材の募集と選考の進め方
特定技能外国人の採用では、適切な募集方法を選び、スムーズな選考を行うことが重要です。以下のポイントを押さえて、効果的に進めましょう。
効率的な募集方法(求人サイト、紹介機関の活用)
特定技能の人材は、以下のような方法で募集できます。
・求人サイトの活用:特定技能外国人向けの専門サイトを利用し、広く募集をかける。
・登録支援機関の紹介:特定技能の支援を行う機関を活用し、適切な人材を紹介してもらう。
・海外の送り出し機関:海外の人材送り出し機関と連携し、事前にスキルを確認した候補者を紹介してもらう。
面接のポイントと選考基準
選考では、業務適性だけでなく、日本での就労意欲やコミュニケーション能力も重要です。
・技能試験の合格状況を確認:特定技能1号の要件を満たしているかチェック。
・日本語能力:業務に必要な日本語スキル(最低でもN4相当)があるかを確認。
・実務経験:過去の職歴や技術レベルを評価し、即戦力となるかを見極める。
・就労意欲と適応力:日本の労働環境や企業文化に適応できるかを重視。
選考基準を明確にし、企業と外国人双方にとって納得感のある採用プロセスを進めましょう。
在留資格申請と必要書類の準備
特定技能外国人を採用するには、在留資格の取得が必要です。申請の流れや必要書類を把握し、スムーズに手続きを進めましょう。
在留資格取得までのステップ
在留資格の申請から取得までは、以下の流れで進みます。
- 雇用契約の締結
- 企業と外国人の間で労働条件を明記した契約を結ぶ。
- 特定技能1号の対象業務であることを確認。
- 建設特定技能受入計画の作成・認定申請
- 建設業では、事前に「建設特定技能受入計画」を作成し、国土交通大臣の認定を受ける必要がある。
- 在留資格認定証明書(COE)の申請
- 企業が外国人の代理として、出入国在留管理庁に申請。
- 認定証明書が発行されると、外国人が自国の日本大使館・領事館でビザを取得できる。
- 入国・就労開始
- 外国人は在留資格を取得して入国し、就労開始。
- 企業は支援義務を履行し、適切な労働環境を整備。
申請時に必要な書類と手続きの流れ
在留資格の申請には、企業側と外国人側それぞれが用意すべき書類があります。
✅ 企業が準備する書類
- 建設特定技能受入計画書
- 雇用契約書(労働条件を明記)
- 企業概要(会社の登記簿謄本、事業計画など)
- 受入れ企業の納税証明書
- 特定技能所属機関(受入企業)の誓約書
✅ 外国人が準備する書類
- 特定技能1号評価試験の合格証明書
- 日本語能力試験(N4以上)の合格証明書
- パスポートおよび証明写真
- 健康診断書
申請手続きは企業が主体となって進める必要があるため、必要書類を事前に確認し、計画的に準備を進めましょう。
特定技能「建設業」の受け入れにおける注意点
特定技能外国人を採用する際には、法的な要件や労務管理のポイントを理解し、適切に対応することが重要です。受け入れ企業は、制度の趣旨を踏まえ、適切な環境整備を行いましょう。
法令遵守と適切な労務管理の重要性
外国人労働者を受け入れる際には、労働関係法令の遵守が不可欠です。適切な労務管理を行い、企業と外国人労働者の双方にとって良好な労働環境を整えることが求められます。
特定技能外国人の雇用における法的義務
- 建設特定技能受入計画の認定取得
・建設業で特定技能外国人を受け入れるには、「建設特定技能受入計画」を作成し、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。 - 労働条件の適正な設定
・日本人と同等以上の賃金を支払う義務があります。
・残業・休日出勤の管理を適正に行い、法定労働時間を遵守することが求められます。 - 社会保険・労災保険の加入
・特定技能外国人も、日本人と同様に健康保険・年金・雇用保険・労災保険への加入が義務となります。 - 適切な就業管理と安全対策・建設業では特に安全管理が重要です。外国人労働者にも日本の安全基準を理解させ、適切な研修を行う必要があります。
労務管理のポイント
・言語の壁を考慮し、ルールを分かりやすく伝える
→ 就業規則や安全マニュアルを母国語やシンプルな日本語で用意する。
・メンター制度を導入し、相談しやすい環境を整える
→ 先輩社員が外国人労働者のフォローを行い、定期的な面談を実施する。
・生活支援にも配慮する
→ 住居や生活面でのサポートを行い、安心して働ける環境を提供する。
適切な労務管理を行うことで、外国人労働者が長く働ける環境を整え、企業の安定した人材確保につなげることができます。
受け入れ後のフォローと定着支援
外国人労働者が職場に適応し、長期的に活躍できるよう、受け入れ後のフォローと定着支援が不可欠です。単に採用するだけでなく、適切なサポート体制を整え、安心して働ける環境を提供しましょう。
外国人労働者の定着に向けた支援策
- 日本語学習の支援
・業務上のコミュニケーションを円滑にするため、日本語教育の機会を提供する。
・企業内研修や外部講座、eラーニングなどを活用する。 - 生活サポートの提供
・住居探しの支援や生活ルールの説明を行う。
・生活相談窓口を設け、日常的な悩みを解決できる体制を整える。 - キャリア形成のサポート
・業務スキル向上のための研修を定期的に実施する。
・特定技能2号への移行を支援し、長期的なキャリア形成を促進する。
職場環境の改善と社内コミュニケーション
・文化の違いを理解し、柔軟な対応を心掛ける
→ 多国籍な職場では、価値観や習慣の違いを尊重することが重要。
・日本人スタッフと外国人労働者の相互理解を深める
→ 交流イベントや研修を通じて、チームワークの向上を図る。
・定期的な面談を実施し、問題を早期に解決する
→ 仕事や生活に関する不安を解消し、離職率を低減させる。
適切な定着支援を行うことで、特定技能外国人が安心して働き、企業の成長にも貢献できる環境を築くことができます。
まとめ
特定技能「建設業」は、慢性的な人手不足に悩む建設業界にとって、即戦力となる外国人労働者を受け入れる貴重な制度です。本記事では、制度の概要や採用のメリット、対象職種、採用プロセス、注意点などを詳しく解説しました。
外国人労働者を適切に受け入れ、定着を図るためには、法令遵守・労務管理の徹底・職場環境の整備が重要です。また、長期的なキャリア形成を支援することで、企業の成長にもつながります。
特定技能制度を正しく理解し、外国人材の力を最大限に活用することで、持続可能な建設業の発展を目指しましょう。
「特定技能、まだよく分からない…」そんな段階でもご相談OKです
「制度の仕組みが複雑で、なかなか前に進めない」
そんな時こそ、経験豊富なパートナーの存在が心強いものです。
TSBケア・アカデミーでは、初めて特定技能に取り組む企業様にも寄り添いながら、分かりやすく一からサポートしています。
どんな些細なことでもかまいません。お問い合わせフォームから、どうぞ気軽にご相談ください。