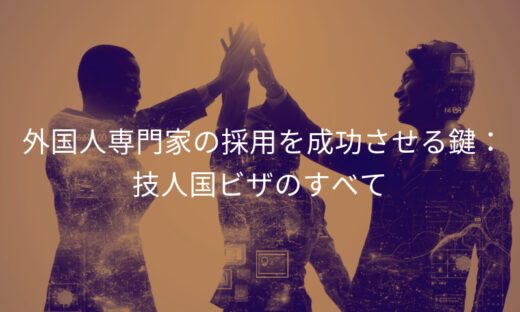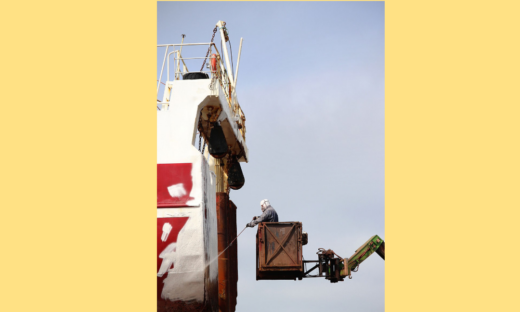入管法改正とは?外国人雇用企業が押さえるべきポイントを徹底解説!

なぜ今、入管法が改正されるのか?
現在の外国人雇用制度の課題と、改正の背景を理解しよう
日本では長年にわたり、外国人材の受け入れにおいて「技能実習制度」と「特定技能制度」が運用されてきました。しかし、これらの制度は現場のニーズや国際的な人権基準と乖離し、抜本的な見直しが求められてきた経緯があります。
2025年の入管法改正では、こうした課題を解決し、より持続可能で公平な外国人雇用制度を構築することが狙いとされています。中小企業が安定的に人材を確保し、共生社会を実現するためにも、改正の背景と目的を理解することが重要です。
人手不足と制度のミスマッチが改正の引き金に

技能実習制度・特定技能制度が抱える課題と企業現場の実情
多くの中小企業が直面している深刻な人手不足。これに対応する形で導入されたのが技能実習制度や特定技能制度でしたが、実際には制度の構造と現場のニーズとの間に大きなギャップがありました。
技能実習制度は「技能の移転による国際貢献」が建前で、労働力確保が本来の目的ではないため、企業にとって柔軟な人材活用が難しく、転職の制限などからミスマッチや人材流出が起きていました。
一方、特定技能制度は制度開始からまだ日が浅く、分野ごとの運用ルールが煩雑で、現場での混乱や理解不足も見られます。こうした課題が改正の出発点となりました。
国際的批判や国内議論が後押しした制度見直し
人権保護や持続的な人材確保を軸にした政策転換の流れ
技能実習制度に対しては、国際社会から「人権侵害の温床」として強い批判が寄せられてきました。過度な労働、低賃金、転職制限、さらには失踪者の増加といった問題が指摘され、日本国内でも国会や有識者による制度の在り方を巡る議論が活発化。
こうした状況を受け、政府は人材育成と就労を両立させる新たな制度設計に踏み切ることとなりました。
2025年の入管法改正は、単なる制度名称の変更ではなく、外国人材の尊厳を守りつつ、長期的な就労やキャリア形成を可能にする「育成就労制度」の導入という、大きな政策転換を意味します。
これは、受け入れ企業にも新たな責任と可能性をもたらすものとなるでしょう。
廃止される技能実習制度と新制度「育成就労」の創設
長年続いた技能実習制度が2025年をもって廃止され、代わりに「育成就労制度」が導入される予定です。
この制度改正は、外国人材を“実習生”ではなく“労働者”として適切に受け入れるための大きな転換点です。これから外国人を雇用する企業にとっても、制度の目的や仕組みを正しく理解しておくことが欠かせません。
技能実習制度はなぜ廃止されるのか
“実習”と“労働”の矛盾や失踪問題が限界に
技能実習制度は、開発途上国への技能移転を目的に1993年にスタートしました。しかし、実際には多くの企業が「安価な労働力」として技能実習生を受け入れ、制度本来の趣旨と実態の間に大きな乖離が生まれていました。
特に問題視されたのが、転職の原則禁止です。実習先で不適切な労働条件や人権侵害があっても、実習生は自由に職場を変えることができず、結果として「失踪」という手段を選ぶケースが後を絶ちませんでした。
この制度は国際的にも批判の的となり、ILO(国際労働機関)や国連などからは“労働搾取の温床”とまで指摘されました。また、日本国内においても、労働力確保の制度としながら建前として“実習”を装う矛盾に限界が来ており、制度設計自体の抜本的見直しが避けられない状況に至りました。
こうした背景から、政府は技能実習制度の廃止を決定し、より実態に即した「育成就労制度」への転換を進めることになったのです。
育成就労制度の特徴と目的
労働力確保+人材育成を両立させる新たな在留資格制度
育成就労制度は、従来の技能実習制度に代わる新たな枠組みとして、2025年に導入が予定されています。この制度は、単に外国人労働者を受け入れるための仕組みではなく、「段階的なキャリア形成」と「労働者としての権利保護」を両立させる点に大きな特徴があります。
具体的には、3年間の就労期間を「初期」「中期」「後期」と段階的に分け、それぞれのフェーズで必要な教育や評価を受けながら、最終的により高いレベルでの就労や「特定技能」への移行を目指す設計です。
転籍(職場変更)も段階的に可能とされており、不当な労働条件や環境からの離脱がしやすくなることで、失踪リスクの低下も期待されています。
また、これまで“監理団体”が担っていた中間的な管理機能を見直し、受け入れ企業自身に対して、より強い責任と支援体制の構築が求められるようになります。
つまり、育成就労制度は「単なる人手確保のための制度」から「人を育てて戦力化する制度」へと生まれ変わるものなのです。企業側も制度の本質を理解し、長期的な視野での受け入れ体制づくりが求められることになります。
育成就労制度の具体的な仕組みと運用ルール
企業が新制度を活用するうえで押さえるべきポイント
育成就労制度は、技能実習制度とは異なり、「人材育成」と「安定的な雇用」の両立を前提としています。そのため、単なる労働力として外国人材を受け入れるのではなく、段階的に成長を促し、キャリアを築ける仕組みが用意されています。
また、これまで中間的な役割を担っていた監理団体の廃止により、企業側にはより高度な管理責任と支援義務が課されます。ここでは、制度の構造と運用上の重要ポイントを整理していきます。
3段階のキャリア構造と転籍ルール
フェーズ別の就労内容・期間・移行可能性を解説
育成就労制度では、外国人材のキャリアを3段階に分けて育成していく仕組みが導入されます。これにより、受け入れ企業も単発的な労働力としてではなく、長期的な人材戦力として外国人を育てる視点が求められます。
第1段階(初期フェーズ):
原則として就労開始から1年未満の期間を指し、職業能力の基礎を身につけるフェーズ。原則転籍(職場変更)は不可。ただし、受け入れ先の不正行為や労働環境の悪化が認められた場合に限り、特例として転籍可能となります。
第2段階(中期フェーズ):
就労開始から概ね1年以降の段階で、職務内容の習熟が進んでくるフェーズ。一定の条件を満たせば、本人の希望と双方の合意に基づいて転籍が可能になります。
第3段階(後期フェーズ):
就労期間が3年目に入るフェーズで、特定技能1号への移行や継続的な就労が見込まれる段階です。この段階では、より高度な業務への従事やキャリアアップ支援が求められます。
このようなフェーズ構造により、外国人本人の成長を促進しつつ、企業にとっても中長期的な人材育成計画が立てやすくなるのが特徴です。また、段階的に転籍を認めることで、労働環境の健全化と定着率の向上にもつながると期待されています。
受け入れ機関に求められる管理体制と支援義務
監理団体の廃止と、新たに求められる受け入れ体制の整備
育成就労制度では、これまで技能実習制度で中間支援を担っていた「監理団体」が廃止されることになりました。そのため、受け入れ企業が直接的に外国人材の生活支援やキャリア形成支援、適正な労務管理を担う必要があります。
具体的には以下のような管理・支援体制が求められます:
就労環境の適正管理:労働条件や就業時間、休暇取得などについて、日本人と同等以上の扱いを担保する。
生活支援の実施:日本語学習の機会提供、住居や生活インフラの整備、相談窓口の設置など。
キャリア支援と評価:段階ごとのスキル評価や研修実施を通じて、特定技能等への移行を後押しする体制の整備。
この制度変更により、「人材を育てる覚悟」が受け入れ企業に求められることになります。一方で、支援機能を専門に担う登録支援機関との連携も視野に入れることで、企業単体ではカバーしきれない部分の補完も可能です。
いずれにしても、従来の“お任せ型”の受け入れ体制からの脱却が不可欠であり、制度の趣旨を正しく理解したうえでの体制整備が急務です。
特定技能制度との関係と移行ルート

複数制度を正しく理解し、自社に合った人材活用戦略を考えよう
育成就労制度の導入により、特定技能制度との連携や移行ルートが明確に設計されるようになりました。
企業としては、目の前の人材を「一時的な労働力」として扱うのではなく、長期的な雇用・戦力化を前提に、どの制度をどう活用するかを考える必要があります。この章では、育成就労から特定技能へのステップアップの仕組みと、制度間の違いを整理していきます。
育成就労から特定技能1号・2号へのステップアップ
制度間でのキャリア形成がしやすくなる新ルート
育成就労制度は、外国人が特定技能1号・2号へとステップアップしやすくなるように設計されています。これにより、これまで制度間の壁がネックとなっていたキャリア形成が、よりスムーズに行えるようになります。
育成就労から特定技能1号への移行
育成就労で一定のスキルと日本語能力を身につけた人材は、試験を経ずに特定技能1号へと移行できる道が開かれます(対象分野により異なる)。
この措置は、既に実務経験がある外国人にとって大きな負担軽減となり、企業側にとっても即戦力を確保しやすくなるメリットがあります。
特定技能2号への拡大と移行支援
特定技能2号は、より熟練した技能と経験を持つ人材に付与される在留資格で、在留期間の更新上限がなく、家族帯同も認められています。
将来的には育成就労→特定技能1号→特定技能2号という一貫したキャリアルートが制度上確立され、外国人材が長期にわたり日本社会に根付いて働ける環境が整っていく予定です。
このように、育成就労は単体の制度ではなく、特定技能制度と連携することで外国人の成長と企業の人材戦略の両方に貢献する存在として位置づけられています。
制度間の違いと企業が選択すべきルート
目的に応じた制度活用が、雇用の安定化と成長につながる
育成就労制度と特定技能制度は、どちらも外国人材の受け入れを可能にする仕組みですが、その目的や運用ルールには明確な違いがあります。企業側が制度を選ぶ際には、自社の業種・事業戦略・人材の定着方針などを踏まえて、適切な制度を活用する視点が求められます。
| 主な目的 | 転職可否 | 家族帯同 | 在留期間の上限 | 支援義務 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 育成就労 | 人材育成+就労 | フェーズにより可 | 不可 | 最大5年 | 有(企業主体) |
| 特定技能1号 | 即戦力の就労 | 可(条件あり) | 不可 | 最大5年 | 有(登録支援機関) |
| 特定技能2号 | 熟練技能人材の就労 | 可 | 可 | 無制限 | 無(自己管理) |
たとえば、「初めて外国人を受け入れる」「教育環境が整っている」企業は育成就労からの受け入れが適しています。一方、「すでに外国人雇用の実績があり、戦力としてすぐに働ける人材がほしい」場合は、特定技能1号からの採用を選ぶ方が効率的です。
制度を単体で考えるのではなく、育成→特定技能というキャリアルート全体で捉えることが、今後の外国人雇用においては重要になってきます。
企業が注意すべき法的義務とコンプライアンス対応

制度改正後は、受け入れ企業に求められる責任も大きく変化する
育成就労制度の創設により、外国人材の受け入れに関する企業側の責任や義務も強化されます。
とくに「労働者」として正式に受け入れる以上、就労環境や契約内容、支援体制などにおいて不備があると、法令違反として指導や処分の対象になる可能性もあります。
制度を正しく理解し、法的リスクを未然に防ぐための対応が、今後の安定した外国人雇用のカギとなります。
雇用契約・労働条件の明示と遵守
外国人労働者にも「日本人と同等以上の待遇」が求められる
新制度では、外国人を労働者として受け入れる前提のため、雇用契約や労働条件について明確かつ適正な取り決めが必要です。以下のような点を特に注意する必要があります。
雇用契約の書面交付(日本語+母国語)
労働条件通知書の交付は必須であり、外国人が理解できる言語でも説明することが推奨されます。
賃金水準は「日本人と同等以上」
最低賃金を上回っていればよい、という考え方では不十分で、同等の業務を行う日本人との比較が基準となります。
労働時間・休日・残業代なども明示的に
契約時の労働条件と実際の就労状況に差があると、トラブルの原因になります。入社後の労務管理も丁寧に行うことが重要です。
また、「研修」の名目で賃金を大幅に下げたり、契約内容にない業務を命じるといった行為は、制度の趣旨を損なう行為として厳しく指導される恐れがあります。
不当な解雇や人権侵害へのリスク管理
雇用する以上は、労働者の権利を守る義務が生じる
制度改正の大きな背景のひとつに、これまでの技能実習制度で多発した「不当な扱い」「人権侵害」の問題があります。育成就労制度では、こうした過去の問題を繰り返さないよう、企業の管理責任が明確にされています。
やむを得ない場合を除く解雇の禁止
一方的な雇止めや、自己都合退職を強要する行為は、労働法上の問題に加えて、在留資格維持に重大な影響を及ぼします。
ハラスメント防止措置の義務化
パワハラやセクハラ、宗教・文化に対する無理解による差別行為などが発生した場合、企業の責任が問われます。
生活支援体制と相談窓口の整備
労働だけでなく、生活上の困りごと(住居・病院・銀行・教育など)についても相談できる体制を整えておく必要があります。
企業にとってはややハードルが高く感じるかもしれませんが、これらは持続的に外国人材を活用していくうえで不可欠な“投資”ともいえる対応です。外国人労働者との信頼関係を築くことで、結果的に離職率の低下や現場の安定にもつながっていくでしょう。
転籍ルールや資格変更の流れ、申請書類の変化に備えよう
育成就労制度では、外国人労働者が一定の条件を満たすことで転籍や在留資格の変更が可能になる点が、これまでの制度と大きく異なります。そのため企業は、在留資格変更に関する手続きを正しく理解し、必要な書類やスケジュールを事前に整えておくことが求められます。
申請実務では、改正入管法に基づく新様式の書類提出や、受け入れ計画書・支援内容の詳細な記載が必要になる可能性があります。また、外国人本人への十分な説明や、変更申請に関するサポート体制の整備も重要です。
これらの実務対応を怠ると、在留資格変更が認められなかったり、受け入れ体制そのものが不適格と判断されるおそれもあります。制度変更にあわせた正確かつ迅速な対応が、企業の信頼性と継続的な外国人雇用の鍵を握るでしょう。
制度改正による企業のメリットと対応のチャンス

新制度を正しく活用すれば、外国人雇用は大きな戦力となる
2025年の入管法改正によって、従来の“育成の名を借りた安価な労働力”という外国人雇用の構造は終焉を迎えようとしています。育成就労制度では「人材を育て、長く働いてもらう」ことを前提とした枠組みが整備され、企業が誠実に取り組むことで多くのメリットを享受できる時代が始まります。
この章では、制度改正が企業にとってどのようなチャンスになるかを具体的に見ていきましょう。
柔軟な人材確保と長期雇用への展望
制度設計の見直しで“雇って終わり”から“育てて活かす”時代へ
これまでの技能実習制度は、「実習」という建前により、実際には転職不可・在留期間に制限がある中で、働き手として活用する難しさがありました。制度改正後は以下の点で企業の人材確保に柔軟性が生まれます。
転籍が可能に(段階的に)
フェーズによっては他社への転職が可能となることで、外国人本人のキャリア形成が現実的になり、企業側も定着のための努力を強化せざるを得なくなります。
特定技能との接続が明確に
ステップアップの仕組みが整備されたことで、長期的な雇用計画を立てやすくなり、「この人材を5年・10年と育てて活躍してもらう」発想が持てるようになります。
採用の裾野が広がる
特定技能ではカバーできなかったような未経験層を含む人材の採用が可能になり、自社で一から教育できる体制があれば、競争優位につながります。
これらは単なる“労働力確保”ではなく、組織の中核人材として外国人を育てていく体制を構築する企業にとって、大きな機会です。
制度を追い風にした採用・定着戦略の再構築
「採って終わり」ではなく「共に働き続ける」視点が求められる
育成就労制度への移行は、企業にとっては一種の“働き方改革”でもあります。外国人雇用を短期的な人員補充と捉えるのではなく、持続可能な経営戦略として再構築する絶好のタイミングです。
外国人採用基準の見直し
採用時に「定着できそうか」「育成に応じて成長するか」といった視点を持ち、将来の活躍像まで想定した人材選びが重要になります。
教育制度・評価制度の整備
日本語学習支援や、段階的なスキル習得を評価する仕組みなど、制度的な裏づけがあると、外国人側も安心して働くことができます。
日本人社員の意識改革
「外国人=補助的な存在」という認識から脱却し、対等なチームメンバーとして迎え入れる企業文化づくりも重要です。これにより職場全体の多様性や柔軟性が高まります。
制度変更にあわせて企業側のマインドセットや仕組みを整えることができれば、外国人雇用は“負担”ではなく“未来への投資”として、大きなリターンをもたらすはずです。
特定技能制度との関係と今後の役割
制度の併存と棲み分けをどう捉えるべきか
育成就労から特定技能への移行パス

「就労と育成のステップ設計」としての特定技能の位置づけ
育成就労制度の導入により、「外国人材の段階的受け入れ」という新たな枠組みが明確化されました。
フェーズ3まで進んだ外国人が、さらに高度な業務に従事するためには、特定技能1号や2号への移行が想定されています。特に特定技能1号は、一定の技能水準と日本語能力を有する者に対して認められる制度であり、育成就労で得た経験やスキルがそのまま評価対象となります。
このように、育成就労制度と特定技能制度は独立した制度でありながらも、実際の運用においては連携・補完関係にあります。入管法改正は、これらの制度を段階的に活用することによって、外国人材の適切な育成と定着を促進する狙いがあります。
特定技能制度の見直しと拡充ポイント
2025年改正に伴う対象分野の拡大や制度改善の動向
改正入管法により、特定技能制度にも大きな見直しが加えられる予定です。これには、対象業種のさらなる拡大や、在留期間の柔軟化、家族帯同要件の見直しなどが含まれます。また、外国人材が働きやすい環境を整備するため、企業に対する支援体制や情報提供の強化も行われる見通しです。
特定技能制度は、単なる労働力確保の手段にとどまらず、長期的な定着と戦力化を見据えた制度へと進化していきます。入管法改正の趣旨を踏まえた制度運用が、企業にも求められています。
今後の制度運用と外国人雇用の未来

持続的な人材活用に向けた企業の長期視点
制度変更に柔軟に対応する意識を持とう
育成型就労と共生社会に向けた企業マインドの転換
2025年の入管法改正を契機に、外国人雇用の在り方は大きく転換期を迎えています。企業は単なる労働力確保の視点だけでなく、「育成」「共生」「定着」という観点を持ち、柔軟に制度変更へ対応する姿勢が求められます。
特に育成就労制度は、単発的な雇用から持続可能な育成型雇用への転換を促すものであり、企業側の理解と取り組みが制度の成否を左右します。入管法改正の背景にある「人材の循環から定着へ」という国の方針を理解し、時代に即したマインドセットへの転換が求められています。
外国人材との共創を目指すために必要なこと
異文化理解と職場定着を重視した雇用戦略の再構築
制度が変わっても、雇用の本質は「人と人との関係」です。文化や習慣の違いを受け入れ、互いに歩み寄る姿勢こそが、企業と外国人労働者の信頼関係を築く鍵となります。
そのためには、異文化理解の研修をはじめ、社内コミュニケーションの強化、日本語教育や生活支援の継続的な充実が不可欠です。また、キャリアアップ支援や意見を聞く仕組みを整えることで、外国人材が自分の未来を描ける職場環境をつくることができます。
改正入管法のもとでの外国人雇用は、制度対応にとどまらず、人材戦略全体の見直しにつながる機会でもあります。企業の真の強みとなる「共創人材」を育てる視点で、今後の雇用戦略を見直していきましょう。
まとめ:入管法改正をチャンスに変えるために
2025年の入管法改正は、単なる制度変更ではなく、外国人雇用の質を問い直す大きな転換点です。育成就労制度の導入や特定技能制度の見直しを通じて、日本の労働市場はより実践的かつ柔軟な方向へ進化しています。
企業にとっては、これまでのやり方を見直し、新たなルールに適応することが求められる一方で、外国人材との信頼関係を深め、持続的に活用していくためのチャンスでもあります。
改正入管法の本質を正しく理解し、自社の雇用戦略と人材育成方針を再構築することで、グローバル時代にふさわしい組織力を築くことができるでしょう。
法令遵守と共生社会の実現を両立させる姿勢こそが、今後の外国人雇用における競争力の源泉です。