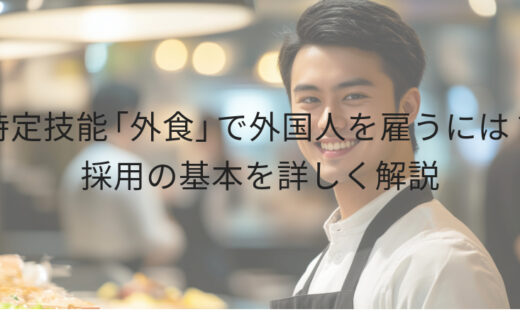特定技能の定期報告を徹底解説!提出先・期限・必要書類と安心運用のポイント

特定技能制度を活用して外国人材を受け入れている企業にとって、避けて通れないのが「定期報告」です。
「どんな書類を用意すればいいの?」「期限はいつまで?」「もし忘れたらどうなるの?」――こうした疑問や不安を抱えている担当者は少なくありません。
定期報告は、単なる事務作業ではなく、外国人材の雇用環境を適正に保ち、制度の信頼性を維持するための大切な仕組みです。しかし、そのルールや手順を正しく理解していないと、提出遅延や不備によって行政指導や罰則を受けるリスクもあります。
本記事では、特定技能における定期報告の基本から、提出先・期限、報告内容、提出方法、そして違反時のリスクまでをわかりやすく整理しました。最後までお読みいただければ、「これを読めば大丈夫」と安心して制度を運用できるはずです。
特定技能における定期報告とは

特定技能制度を利用して外国人材を受け入れる企業や登録支援機関には、四半期ごとに「定期報告」を行う義務があります。
これは単なる事務手続きではなく、外国人が適正な労働環境のもとで安心して働けているか、また策定された支援計画が実際に実施されているかを確認するために定められた仕組みです。
定期報告は制度運用の根幹に位置づけられており、怠れば企業や支援機関にとって重大なリスクにつながるため、正しく理解し、確実に遂行することが不可欠です。
特定技能制度は、技能実習制度の限界を補い、即戦力として外国人材が活躍できる枠組みとして導入されました。そのため、国としても「外国人材の雇用環境が健全に保たれているか」を継続的に把握し、必要に応じて改善を促すことが求められます。
定期報告は、この制度全体の信頼性を確保するための重要な監視・評価システムといえるのです。
定期報告の義務と目的
定期報告の最大の目的は、外国人材の就労状況を国が把握し、不適切な雇用や人権侵害を未然に防ぐことにあります。例えば、約束どおりの賃金が支払われているか、労働時間が労働基準法を守っているか、生活支援が計画通りに行われているかなどを確認します。
これにより、外国人材が安心して働ける環境を整えると同時に、制度全体の透明性と信頼性を高める狙いがあります。
また、定期報告を通じて外国人材の就労状況がデータとして蓄積されることで、国は制度の運用実態を把握し、必要な制度改正や分野ごとの政策判断にも活用できます。
企業にとっても、適切な報告を行うことは法令遵守を示すものであり、社会的信用や取引先からの信頼を守ることにもつながります。
報告対象となる企業と登録支援機関
定期報告の対象となるのは、特定技能外国人を雇用しているすべての企業と、その支援を担う登録支援機関です。企業は、雇用契約の内容や労働条件の遵守状況、給与や社会保険加入の状況などを報告する責任があります。
一方、登録支援機関は、生活オリエンテーションや行政手続きの補助、日本語教育支援など、日常生活に密接に関わる支援が計画通りに行われているかを報告します。
両者がそれぞれの立場から定期報告を行うことで、制度は二重のチェック機能を備えることになります。企業と支援機関が連携して責任を果たすことは、外国人材にとっても安心感をもたらし、制度を健全に運用するための基本姿勢といえるでしょう。
提出先と提出期限

特定技能の定期報告は、外国人材を適正に受け入れているかどうかを国が把握するために、必ず提出しなければならない重要な手続きです。
報告の提出先や期限は明確に定められており、これを守らなければ企業や登録支援機関は行政処分の対象となる可能性があります。制度を健全に運用するためには、この「提出先」と「期限」を正しく理解し、計画的に対応することが欠かせません。
提出先は出入国在留管理庁
定期報告の提出先は、出入国在留管理庁(入管庁)です。すべての報告はこの行政機関に集約され、外国人材の就労状況や支援実施状況が一元的に管理されます。
入管庁はこれらの報告を基に、企業や支援機関が適切に制度を運用しているかを審査し、問題があれば是正指導を行います。提出方法としては、入管庁が提供する「在留支援システム」を利用したオンライン提出が推奨されています。
オンラインであれば即時に受付が行われ、確認や補正もスムーズに行えるため、効率性と確実性の両面で優れています。一方で、やむを得ない場合には郵送や窓口での提出も認められており、企業の状況に応じた方法を選択することが可能です。
ただし、提出後に不備が見つかった場合は速やかに補正を行わなければならないため、正確な記載と十分なチェックが欠かせません。
四半期ごとの提出期限
定期報告は、四半期(3か月)ごとに行うことが義務付けられています。具体的には、4月〜6月、7月〜9月、10月〜12月、1月〜3月という区切りで、それぞれの期間が終了した翌月末日までに提出しなければなりません。
たとえば、4月〜6月分の報告は7月末までに提出する必要があります。期限を過ぎてしまうと「報告義務違反」とみなされ、指導や改善命令、さらには受け入れ停止といった行政処分につながる可能性があります。
そのため、各期末が近づいたら早めに資料を整え、余裕を持って提出することが重要です。特に複数の外国人材を雇用している企業や、支援内容が多岐にわたる登録支援機関では、情報のとりまとめに時間がかかるケースも少なくありません。
社内でスケジュール管理を徹底し、担当者を明確にすることで、期限内に確実に提出できる体制を整えておく必要があります。
定期報告の内容
特定技能の定期報告では、単に「提出したかどうか」だけでなく、外国人材が適切に就労し、支援を受けているかを確認するための詳細な情報が求められます。
報告内容は大きく分けて「雇用状況」「支援計画の実施状況」「生活支援や日本語教育の実施状況」の3つに分類されます。これらを正しく整理して報告することで、制度の健全な運用を証明することができます。
雇用状況に関する報告項目
雇用状況に関する報告では、特定技能外国人が就労している現場での労働条件や契約内容が正しく守られているかを明らかにします。具体的には、賃金額、給与支払い方法、労働時間、休日数、残業時間の実績などが求められます。
さらに、社会保険や労働保険の加入状況も報告の対象となります。これにより、外国人材が日本人と同等の条件で雇用されているかが確認されます。不適切な条件や未加入があれば、改善指導の対象となる可能性があるため、日常的に労務管理を徹底することが必要です。
支援計画の実施状況に関する報告項目
特定技能外国人を受け入れる企業または登録支援機関は、雇用にあたり「支援計画」を策定し、その実施状況を定期報告で明示する義務があります。
支援計画には、生活オリエンテーションの実施、行政手続きの補助、医療機関利用のサポート、相談窓口の設置などが含まれます。定期報告では、これらの支援が計画どおりに実施されているかを具体的に記載する必要があります。
例えば「入国後の生活オリエンテーションを◯月◯日に実施」「行政手続きの同行支援を実施」など、実際の対応を証拠として示すことが求められます。
生活支援・日本語教育の実施状況
生活支援や日本語教育の提供状況も重要な報告項目です。外国人材が安心して生活できるよう、住居探しや銀行口座開設のサポート、日常生活に関する相談対応が適切に行われたかを報告します。
また、日本語教育については、学習機会の提供や教材の手配、必要に応じた外部講座の紹介などを記載します。外国人材が日本社会に適応しやすくなるような取り組みは、定着率を高めるうえでも非常に大切であり、入管庁はその実施状況を注視しています。
単なる形式的な記載ではなく、実際の取り組み内容を具体的に示すことが求められる点が特徴です。
提出方法と必要書類

特定技能の定期報告は、形式や内容が細かく決められており、正しい方法で提出することが求められます。入管庁はオンライン申請システムを推奨していますが、郵送や窓口での提出も可能です。
また、提出書類には統一されたフォーマットがあり、それに従わないと受理されない場合もあります。ここでは、代表的な提出方法と必要書類の特徴を整理します。
オンライン申請システムの利用
現在、最も推奨されているのが「在留支援システム」を利用したオンライン提出です。
このシステムは出入国在留管理庁が提供しており、企業や登録支援機関がインターネットを通じて定期報告を行える仕組みになっています。オンライン提出のメリットは、即時に受付が完了する点や、提出状況をシステム上で確認できる点にあります。
また、誤りがあった場合も比較的早く補正依頼が届くため、修正対応がスムーズです。複数の外国人材を受け入れている企業では、紙での提出よりも大幅に効率が向上するため、オンラインの利用が実務上は必須といえるでしょう。
郵送・窓口提出の方法
一方で、オンライン環境が整っていない場合や、どうしても紙での提出が必要な事情がある場合は、郵送や窓口での提出も認められています。郵送の場合は、提出期限に間に合うよう余裕をもって発送することが重要です。
窓口提出を行う場合は、所轄の出入国在留管理局に直接持参します。ただし、窓口は混雑することも多く、待ち時間が長引くケースがあります。そのため、郵送・窓口提出はあくまで例外的な対応と考え、基本はオンラインでの提出を前提とした運用を行うのが望ましいでしょう。
提出書類のフォーマット
定期報告で使用する書類には、入管庁が指定した様式があります。代表的なものは「雇用状況報告書」と「支援実施状況報告書」で、それぞれの内容を正確に記載することが求められます。
フォーマットは入管庁の公式サイトからダウンロードできるようになっており、最新版を使用することが重要です。古い様式や独自のフォーマットを用いると、受理されない場合や再提出を求められることがあります。
また、添付資料として、雇用契約書の写しや給与明細、勤怠記録、支援活動の証跡(例:日本語教育の案内資料や相談記録)などを求められることもあります。提出前に必要書類をチェックリスト形式で確認し、漏れなく整えることが、スムーズな手続きにつながります。
違反時のリスクと行政処分

特定技能の定期報告は「義務」であり、提出を怠ったり不正確な内容を記載したりすると、企業や登録支援機関に重大なリスクが発生します。行政からの指導や罰則はもちろん、場合によっては特定技能外国人の受け入れ自体ができなくなることもあります。
ここでは主なリスクと行政処分の内容を整理します。
報告遅延や不備による指導
定期報告を期限内に提出しなかった場合、まずは出入国在留管理庁から「指導」や「改善命令」が出されることがあります。また、提出はしたものの内容に不備があった場合も同様で、補正を求められます。
これらの段階で誠実に対応すれば大きな問題には至らないこともありますが、繰り返し遅延や不備を起こすと「制度を正しく運用できない企業」と判断され、行政処分の対象となるリスクが高まります。小さな不備でも軽視せず、常に正確で期限内の提出を徹底することが大切です。
虚偽報告や未提出の場合の罰則
もっとも重大な違反にあたるのが「虚偽報告」と「未提出」です。例えば、実際には残業時間が多いのに「適正に管理している」と虚偽記載したり、支援を実施していないのに「実施済み」と報告したりするケースは、明確な違反行為とみなされます。
また、定期報告をそもそも提出しなかった場合も同様です。これらの行為が発覚すると、外国人材の受け入れ停止や事業者名の公表といった厳しい処分につながります。
さらに、悪質と判断された場合は、将来的に特定技能の外国人材を一切雇用できなくなる可能性もあります。
登録支援機関の登録取消の可能性
登録支援機関にとって、定期報告は自らの存在意義を示す最も重要な業務の一つです。そのため、報告の怠慢や虚偽記載が繰り返されると、「登録支援機関」としての登録自体が取り消されることがあります。
登録が取り消されると、他の企業からの依頼を受けて支援業務を行うことができなくなり、事業の存続に直結する深刻な問題となります。さらに、その機関が支援していた外国人材については、新たな支援先を探さなければならず、受け入れ企業や本人に大きな負担を与える結果になります。
登録支援機関は特に高い信頼性が求められる立場であることを意識し、報告義務を徹底する必要があります。
まとめ
特定技能の定期報告は、外国人材を受け入れるすべての企業や登録支援機関に課せられた重要な義務です。
四半期ごとに雇用状況や支援実施状況を正しく報告することで、外国人が安心して働ける環境を維持し、制度全体の信頼性を支えることにつながります。逆に、報告を怠ったり不備を繰り返したりすると、行政処分や受け入れ停止といった大きなリスクを負うことになります。
安心して制度を運用するためには、日頃から労務管理や支援の実施状況を整理し、余裕を持って報告準備を進めることが大切です。また、報告の方法や必要書類について不安がある場合は、専門家や登録支援機関のサポートを活用することで、正確かつスムーズに対応できます。
私たち TSBケアアカデミー では、特定技能に関する申請や定期報告のサポートを行い、企業と外国人材が安心して制度を活用できるようお手伝いしています。制度の詳細を知りたい方や実務でお困りの方は、ぜひ お問い合わせ からご相談ください。