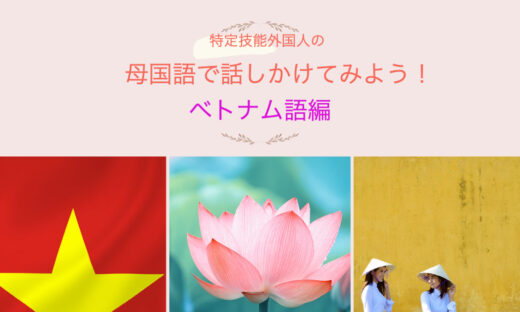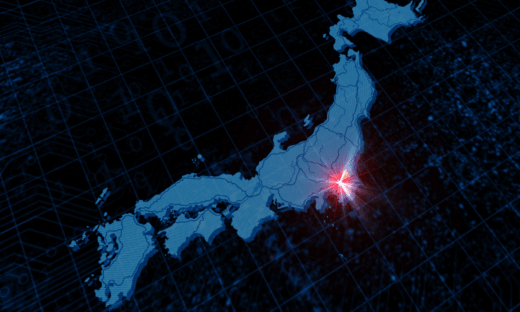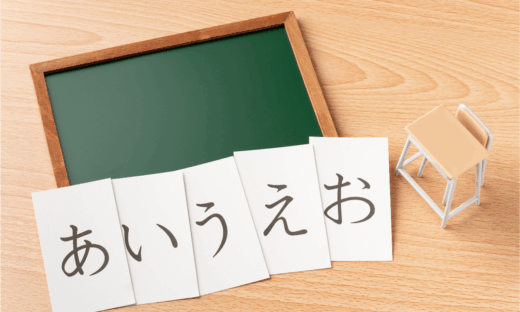特定技能で採用できる12分野・14業種を網羅的に解説

外国人材の雇用を検討するうえで、「特定技能」という在留資格は注目を集めています。しかし、実際に採用を進めようとすると「どの職種が対象なのか?」「自社の業務に合った分野はどれか?」といった疑問に直面する方も多いのではないでしょうか。
特定技能は、業種ごとに制度の運用ルールや必要な準備が異なり、理解が不十分なまま進めるとトラブルや採用ミスマッチにつながるリスクもあります。
この記事では、特定技能で採用できる職種をわかりやすく整理し、分野別の特徴や採用時の注意点まで丁寧に解説します。初めての外国人材受け入れでも安心して取り組めるよう、制度理解と準備のポイントを一緒に確認していきましょう。
特定技能で採用できる職種一覧

特定技能制度は、日本国内の深刻な人手不足を補うために設けられた在留資格制度です。まずはこの制度で採用可能な職種の全体像を把握しましょう。
認められている12分野・14業種
現在、特定技能制度で受け入れが認められているのは「12の分野」に分類された「14の業種」です。一見ややこしく感じるかもしれませんが、これは制度上の整理と実際の職種数の違いによるものです。
たとえば、製造業の中には「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」といった3つの分野があり、それぞれ別の技能評価が設定されています。
このように、一つの業界であっても複数の分野に分かれていたり、逆に一つの分野内に複数の業種が含まれていたりするケースがあるため、採用前には分野と職種の区分を正確に確認することが重要です。
特定技能で採用できる職種は、現在以下の12分野・14業種に限定されています。
| 分野・業種 |
|---|
| 介護 |
| ビルクリーニング |
| 素形材産業 |
| 産業機械製造業 |
| 電気・電子情報関連産業 |
| 建設業 |
| 造船・舶用工業 |
| 自動車整備業 |
| 航空業 |
| 宿泊業 |
| 農業 |
| 漁業 |
| 飲食料品製造業 |
| 外食業 |
これらの業種は、いずれも慢性的な人手不足が問題となっている分野です。特に製造業や介護、建設業などは地方でも需要が高く、今後ますます外国人材の活用が求められる分野といえるでしょう。
各職種の具体的な業務内容
特定技能で認められている業務内容は、業種ごとに明確に定められています。たとえば「介護」分野では、身体介護に加えて記録業務やレクリエーションの補助などが含まれます。「農業」では、露地栽培・施設栽培・畜産など、季節に応じた多様な作業が対象となります。
製造業の中では、「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」に分かれており、それぞれ異なる技能水準が求められます。外食業では、ホール業務・厨房での調理などが対象となりますが、「接待を伴う飲食」は対象外です。このように、業種ごとの詳細を事前に確認することが、制度活用の第一歩となります。
〜特定技能で採用できる14業種の完全解説〜
- 介護分野|高齢化社会を支える人材
介護分野は、日本国内で最も人手不足が深刻とされている分野の一つです。特定技能1号では、訪問介護を除く施設系の業務(身体介護・生活援助・レクリエーション支援など)が対象となっており、即戦力としての人材が求められています。介護技能評価試験と日本語能力試験(N4相当)に合格することが条件であり、採用後も継続的な教育支援が重要です。
2.ビルクリーニング分野|都市機能を維持するインフラ職種
オフィスビルや商業施設などの清掃業務を担うビルクリーニング分野は、都市生活に欠かせないインフラ業務です。清掃道具や設備の使用方法、安全衛生管理、作業の正確さが求められ、特に駅直結施設や医療施設内での作業では高い信頼性が必要です。日本語能力の水準が比較的高く、日本語での指示理解力が重要視されます。
3.素形材産業分野|金属加工や鋳造を担うものづくりの基礎
鋳造、鍛造、板金、めっき、溶接など、日本の製造業を支える基盤的な工程を含むのが素形材産業分野です。工場でのチーム作業、正確な加工スキル、危険物の取扱いに対する注意力が求められます。日本の熟練技術を次世代につなぐ役割も期待されており、技能実習からの移行も多い分野です。
4.産業機械製造業分野|設備組立や機械加工の中核
この分野では、エンジンや産業ロボット、建設機械などの製造を支える業務が対象です。部品の加工・組立、機械操作、検査などが主な業務であり、図面の読解力や精密作業への理解が必要です。職場では安全管理が重視されるため、日本語でのコミュニケーション能力は欠かせません。
5.電気・電子情報関連産業分野|組立から検査まで精密作業を担う
スマートフォンや家電、車載部品などの製造に関わる分野です。静電気対策や清潔な作業環境での作業が多く、部品の取り扱いや検査では集中力と手先の器用さが重視されます。マニュアルに沿った工程管理が必要なため、日本語の読解能力も一定水準が求められます。
6.建設分野|インフラ整備の最前線で活躍する多様な職種
建設分野は、型枠施工、鉄筋施工、配管、内装仕上げなど19職種に細分化され、多岐にわたる現場業務を含みます。即戦力としての作業員が求められており、厳しい作業環境の中でも安全に作業できる体力と技術が必要です。技能実習からの移行も多く、キャリアパスの継続性が評価されています。
7.造船・舶用工業分野|日本の海事産業を支える専門職
大型船舶の建造に携わる造船・舶用工業分野では、鉄工、溶接、塗装、機械加工、艤装などの業務があります。重量物の取り扱いや屋外作業が多く、現場での安全対策が徹底されています。特定技能2号への移行が可能なため、長期的な人材確保にもつながります。
8.自動車整備分野|車社会を支える重要な技術職
自動車の定期点検、整備、部品交換などが主な業務です。日本国内の高い技術基準に基づいた作業が求められ、基本的な整備知識と実務経験が必要です。整備士資格を要さない範囲での業務が中心ですが、経験を積んで資格取得や2号への移行も視野に入れる企業も増えています。
9.航空分野|空港の運営・安全を支える地上のプロフェッショナル
空港でのグランドハンドリング業務(手荷物・貨物の積み降ろし、航空機の誘導等)や整備補助作業が対象です。迅速さと正確性が求められるため、事前研修と現場での丁寧な指導が欠かせません。国際的な安全基準に準じた業務遂行が必要です。
10.宿泊分野|観光とホスピタリティの最前線で働く
ホテルや旅館などでのフロント業務、レストランサービス、客室清掃などが含まれます。接客スキル、日本語対応力、文化理解が問われる分野であり、教育体制が整っている企業ほど採用後の定着率が高い傾向にあります。
11.農業分野|季節労働と共に働く地域の担い手
施設園芸や畑作、稲作などの農作業が対象です。季節や地域によって作業内容が異なるため、柔軟な対応力と屋外作業への適応力が必要です。外国人材が地域コミュニティに溶け込めるような支援体制も重要な要素となります。
12.漁業分野|水産業の現場で求められる実務スキル
漁労業や養殖業に従事する職種で、体力と忍耐力が求められる海上作業が中心です。漁獲や水産加工などの作業を通じて、日本の食文化を支える重要な役割を担います。地域に根差した就労支援も成功のカギとなります。
13.外食業分野|接客力とスピードが求められる現場力重視の職種
外食業分野は、飲食店でのホール業務やキッチン補助など、日常的に顧客と接する機会が多い分野です。調理補助・配膳・後片付けといった基本的な作業に加え、日本語での注文対応やクレーム対応が発生するため、日本語コミュニケーション力が重視されます。
また、ピーク時間帯の混雑への対応や、シフト勤務への柔軟な対応力も必要です。特定技能試験に加え、実務の中での丁寧なOJTや定期的なフィードバック体制が、職場定着のカギを握ります。
14.飲食料品製造業分野|衛生管理と正確性が重視される製造現場
飲食料品製造業分野では、食品の加工、包装、検査、出荷などの工程に従事します。衛生管理の厳格さが求められ、マスク・手袋の着用や手洗い手順などの遵守が必要です。
ライン作業でのスピード感や反復作業の正確性も重要なポイントであり、体力と集中力の両立が求められます。外国人材の受け入れには、明確な作業マニュアルの整備やピクトグラムによる視覚的指示などの工夫が効果的です。技能評価試験に合格することが必要条件です。
分野別の特徴と採用時のポイント

特定技能制度は一つの枠組みによって運用されているものの、分野ごとに導入要件や制度の細かいルール、実務上の注意点が大きく異なります。そのため、自社の事業内容や受け入れ体制に合った分野を見極めることが、制度を有効活用する上での第一歩となります。
製造・インフラ系職種の特徴と導入しやすさ
〜技能実習制度からの移行実績と受け入れ体制の整備〜
製造業(素形材・産業機械・電気電子)、建設、自動車整備、造船・舶用工業などの分野では、「一定以上の技能水準」と「現場対応力」が特に重視されます。どの分野も技能評価試験への合格が必須となっており、実務経験や作業精度、安全意識が問われる場面も多くあります。
たとえば、製造業では工程のマニュアル遵守や品質管理が求められ、建設業では高所作業や重機操作など、日本人スタッフと同等の安全教育が必須です。造船業では溶接・配管などの専門技能が必要とされるため、教育コストを見込んだ中長期的な育成も想定されます。
特に建設分野と造船分野では、一定の条件を満たせば「特定技能2号」への移行が可能です。これは在留期間の上限が撤廃され、将来的な永住の道も開ける制度であり、企業にとっては長期雇用できる貴重な人材の確保手段となります。
反面、業務内容の細かい制限や就労場所の報告義務など、遵守すべきルールも多く、導入前に制度理解と体制整備が欠かせません。
サービス・生活支援系職種の注意点と支援体制
〜言語力と文化理解を重視した伴走型サポートが鍵〜
外食業、宿泊業、ビルクリーニング分野など、いわゆる「人と接する仕事」では、日本語での円滑なコミュニケーション能力が重要視されます。技能試験に加えて、日本語能力試験(JLPT)でN4以上の合格が求められる分野もあり、語学力は採用後の業務適応にも大きく影響します。
たとえば外食業では、接客時のマナーやクレーム対応など、日本独自の「おもてなし文化」への理解が必要となります。宿泊業ではフロント、客室清掃、レストランサービスなど多職種の連携が必要で、柔軟な対応力と気配りが重視されます。外国人観光客対応では英語や中国語が活きる場面もあり、語学力に応じた業務配置の工夫も大切です。
また、これらの分野では早朝・深夜の勤務が発生するケースも多く、就労時間の調整や休息時間の確保、シフト管理などの労務面の工夫も必要です。
文化の違いによる価値観のズレからトラブルになることもあるため、受け入れ時には「マナー研修」「接客ロールプレイング」などの社内研修を実施し、円滑な職場づくりを支援する体制が求められます。
地域産業系(農業・漁業)の活用のカギとは
〜季節変動への対応・地域支援との連携が成功の要因〜
農業・漁業といった地域産業分野では、季節ごとの繁忙期に応じた短期・中期的な人材確保が主な目的となるケースが多く見られます。農業では種まきや収穫のタイミング、漁業では漁期に合わせた人手が必要になるため、計画的な人員配置が重要です。
こうした背景から、特定技能外国人を採用する場合にも、柔軟な労働スケジュールへの対応力や、繁忙・閑散の差を理解した体制づくりが求められます。
また、就労の場が地方や山間部、離島などに位置することも多く、生活環境への適応支援が定着の大きな鍵となります。近隣にコンビニや病院が少ない、公共交通が限られているといった地域特有の課題もあるため、移動手段や生活インフラの整備、地域住民との交流の機会づくりが不可欠です。
地元自治体や農協、漁協などの支援団体、受入協議会との連携を強化し、職場だけでなく地域ぐるみでの受け入れ体制を整えることが、安定した雇用と定着に直結します。
採用に必要な準備と制度理解

特定技能制度を適切に活用するには、単に人材を採用するだけでなく、制度の構造や手続き、そして受け入れ体制に対する理解が不可欠です。
特定技能は「受け入れ企業の責任」が重視される制度のため、採用前から準備すべき事項が多岐にわたります。人材募集の前に、必要な要件や行政手続きを把握し、制度に沿った体制づくりを行うことが、スムーズな採用・定着につながります。
手続きの流れと必要書類
特定技能制度を活用するにあたり、すべての分野に共通して必要なステップがあります。まず、技能評価試験・日本語能力試験(または技能実習2号修了)など、在留資格取得の条件を満たしているかを確認します。
次に、外国人と雇用契約を結び、労働条件通知書を提示します。受け入れ企業は、分野ごとに指定された協議会(例:介護は「介護技能評価試験実施機関協議会」)への加入が義務付けられている場合があります。
申請先・報告義務と留意点
入国管理局(出入国在留管理庁)への在留資格認定証明書交付申請、在留カードの交付、定期的な報告義務など、行政手続きも発生します。受入責任者や支援計画の届出が必要な場合もあり、制度の詳細を理解したうえで準備を進めることが重要です。
試験・在留資格の基本要件
特定技能1号で外国人材を採用するには、まず対象職種に対応する「技能評価試験」と、日本語能力を測る「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験N4以上」の合格が必要です。
技能評価試験は分野別に内容が異なり、たとえば外食業なら調理や接客の基本技術、介護分野では身体介護の知識や対応力が問われます。ただし、技能実習2号を良好に修了した外国人については、原則としてこれらの試験が免除される特例があります。
これは技能実習制度と特定技能制度が制度的につながっているためであり、実務経験者のスムーズな移行を想定しています。
在留期間は1回あたり6カ月または1年で、最長5年までの更新が可能です。また、「建設」「造船・舶用工業」などの限られた分野においては、上位資格である「特定技能2号」への移行が可能です。
2号になると在留期限が撤廃され、家族の帯同も可能になるなど、生活基盤の安定につながるメリットがあります。
長期的な戦力として迎えたい場合には、将来的な2号移行も見越した戦略設計が求められます。
協議会加入と支援体制の整備
特定技能制度では、外国人材の受け入れ企業に対し、分野ごとに定められた「協議会」への加入が義務づけられています。これは単なる形式的な登録ではなく、業界全体として外国人労働者の処遇改善や育成環境の整備を進める目的があります。
たとえば、「外食業分野特定技能協議会」や「建設分野特定技能協議会」など、各分野に応じた専門組織が設置されており、採用に関する情報提供や支援も行っています。
また、受け入れ企業は外国人が安心して働き、暮らせるようにするため、「支援計画」の策定と実施が義務化されています。この計画には、日本での生活支援(住居の確保・行政手続き・日本語学習の支援など)、職場環境への適応支援、相談体制の構築などが含まれます。
支援内容は多岐にわたり、専門的な知識が求められるため、企業が自ら実施するほかに、「登録支援機関」に委託することも認められています。
登録支援機関は、出入国在留管理庁に登録された民間事業者であり、支援実務の代行に加え、必要な報告書類の整備や提出、トラブル対応も行うため、制度に不慣れな企業にとっては心強いパートナーとなります。初めての採用であれば、登録支援機関との連携も視野に入れて体制を構築するのが現実的です。
まとめ:自社に合った職種選びで制度を活用しよう

特定技能制度は、労働力不足の解消だけでなく、将来的な定着と成長も見据えた制度です。業種の選定や受け入れ準備をしっかりと行えば、外国人材と長く信頼関係を築いていくことができます。
制度をうまく活用するためには、自社に合った職種・分野の見極めが第一歩です。業種ごとの要件や支援内容を理解し、必要な準備を整えながら、安定的かつ継続的な人材活用を目指しましょう。
💡外国人材の採用でお悩みの企業様へ
特定技能制度の導入や職種ごとの選定に不安はありませんか?
TSBケアアカデミーでは、制度の基本から実務まで丁寧にサポートいたします。サービス内容の詳細は公式サイトをご覧いただき、
まずはお気軽にお問い合わせください。