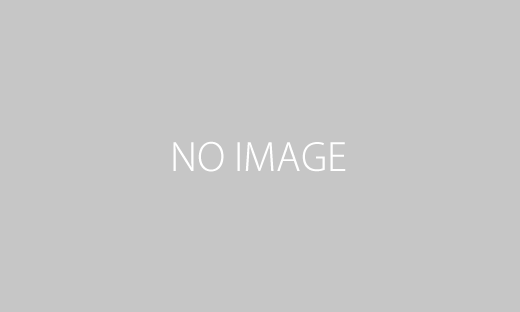特定技能「製造業」完全ガイド!対象職種・採用メリット・注意点をわかりやすく解説

日本の製造業は、かつて「ものづくり大国」と呼ばれた日本経済を支えてきた基幹産業です。
しかし少子高齢化や若年層の減少により、深刻な人手不足が続いています。特に地方の工場や中小企業では、採用活動を続けても必要な人材を確保できず、生産計画の遅延や事業継続への不安が広がっています。
こうした課題を背景に、2019年に導入されたのが「特定技能制度」です。特定技能は、外国人材が即戦力として現場で働くことを可能にする新しい在留資格であり、その中でも「製造業」は大きな注目を集めています。
本記事では、特定技能「製造業」の仕組みや対象職種、在留資格要件、企業が守るべき条件、採用メリットと注意点、そして今後の展望について詳しく解説します。
特定技能「製造業」とは

日本の製造業における深刻な人材不足に対応するため導入されたのが「特定技能制度」です。その中でも製造業は、幅広い職種で外国人材の受け入れが認められており、技能実習制度に代わる実務的な就労の枠組みとして注目されています。
特定技能制度の概要
特定技能制度は、日本における深刻な人手不足に対応するために2019年に創設された新しい在留資格制度です。
これまで外国人労働者の受け入れは技能実習制度や高度人材向けの在留資格が中心でしたが、特定技能は「一定の専門性や技能を持ち、即戦力として現場で働ける外国人材」を受け入れるための仕組みです。
特定技能には「1号」と「2号」があり、1号は比較的短期(最長5年)の就労を想定している一方、2号は熟練した技能を持つ人材が永住に近い形で就労・家族帯同できる枠組みとなっています。
製造業分野はこの特定技能制度の中でも大きな位置を占めており、素形材産業や産業機械製造業、電気・電子情報関連産業など、多様な業種で人材受け入れが認められています。
製造業における人材不足の現状
日本の製造業は長らく高度経済成長を支えてきましたが、近年は少子高齢化の影響により深刻な人手不足に直面しています。
中小企業を中心に、新卒採用や転職市場での労働力確保が困難になっており、特に現場作業を担う若手人材の不足が顕著です。厚生労働省や経済産業省の調査によれば、多くの製造業分野で「慢性的な人員不足」が続いており、国内労働力だけでは安定した生産体制を維持することが難しくなっています。
こうした背景から、外国人材の受け入れが不可欠な選択肢となり、特定技能制度が注目を集めています。実際に、既存の技能実習制度では「人材育成」が目的とされていましたが、製造業の現場では「即戦力」として働ける人材を強く求めているのです。
技能実習制度からの転換点
製造業における外国人材受け入れは、長年「技能実習制度」が中心でした。しかし技能実習制度は、本来「途上国への技能移転」を目的としており、人手不足を補うための制度ではありません。
そのため、実際の現場では「建前と実態の乖離」が指摘され、労働環境や待遇面での問題も多く報道されてきました。
こうした批判を受け、より現実に即した制度として導入されたのが「特定技能」です。特定技能は制度設計の段階から「労働力不足への対応」が目的とされており、受け入れ企業は正規の労働契約を結び、労働基準法や最低賃金法を遵守することが求められます。
技能実習から特定技能への移行ルートも用意されており、これによってすでに日本で一定期間働いた実習生が、即戦力人材として長期的に活躍できる道が開かれています。まさに、製造業における外国人材活用の「転換点」といえるでしょう。
対象職種と業務内容

特定技能「製造業」では、複数の産業分野や職種が対象とされており、それぞれで求められる技能や作業内容が定められています。素形材、産業機械、電気・電子のほか、追加された区分もあり、制度の適用範囲は広がっています。
素形材産業の対象業務
素形材産業は、製造業の基盤を支える重要な分野です。ここでいう「素形材」とは、金属やセラミックスなどを素材として加工し、最終製品の部品や構造を形づくるための材料を指します。
特定技能制度における素形材産業の対象業務は、鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、溶接、工業塗装などが含まれます。これらの作業は専門的な技術を必要とする一方で、国内では若年層の担い手が減少しているため、深刻な人材不足に直面しています。
特定技能外国人が加わることで、こうした重要工程において安定的な生産体制を維持することが可能になります。特に素形材分野は、日本の製造業全体の品質と競争力を左右するため、外国人材の参画は産業基盤を支える大きな役割を果たすと期待されています。
産業機械製造業の対象業務
産業機械製造業は、工場や生産ラインにおける機械の設計・組立・保守を担う分野です。対象となる業務は、産業機械組立、電気機械組立、金属工作機械の組立や部品製造など多岐にわたります。
これらの作業は正確さと効率性が求められ、日本の高度な製造技術を支える重要な領域です。しかし一方で、機械組立に携わる技術者は年々減少しており、特に地方の工場では人員確保が困難となっています。
特定技能人材の導入により、即戦力として現場で活躍できる労働力を確保できることは、企業にとって大きなメリットです。さらに、機械製造分野で経験を積んだ外国人材が将来的に特定技能2号へ移行することで、中長期的な技術継承や安定雇用にもつながります。
電気・電子情報関連産業の対象業務
電気・電子情報関連産業は、半導体製造や電子部品組立など、日本の輸出産業を支える先端的な分野です。特定技能の対象業務には、電気機器組立、電子機器組立、プリント配線板製造などが含まれます。
これらの業務は非常に精密であり、正確な作業が求められるため、従来は経験豊富な技術者が中心でした。しかし、需要の拡大に比べて人材供給が追いつかず、現場では人手不足が深刻化しています。
外国人材の活用により、生産量の確保や納期遵守が可能になるだけでなく、品質管理の体制強化にもつながります。また、この分野は国際競争が激しいため、多様な人材の受け入れがイノベーション促進の一因にもなると考えられます。
追加された業務区分(紙器・段ボール、コンクリート製品など)
製造業における特定技能の対象分野は、制度発足当初から拡張されてきました。特に追加された業務区分としては、紙器・段ボール製造、コンクリート製品製造、RPF製造、陶磁器製品製造、印刷・製本、紡織、縫製といった多様な分野があります。
これらはいずれも日常生活や産業活動に不可欠でありながら、労働集約的で人材不足が顕著な分野です。特に段ボール製造や印刷業は繁忙期の人手確保が難しく、コンクリート製品や陶磁器は地域産業にとって重要な役割を担っています。
こうした分野に外国人材を受け入れることで、地域経済の維持と活性化にも寄与することが期待されています。
関連業務として認められる範囲
特定技能制度では、対象業務だけでなく「関連業務」として認められる作業範囲が定められています。
例えば、金属加工に従事する人材がその製品検査や品質確認に関わること、機械組立に携わる人材が付随的な部品搬送や簡易的な補助作業を行うことなどがこれに当たります。
ただし、関連業務が認められるのはあくまで本来の対象業務と密接に関連している場合に限られ、単純労働や他分野の業務を行うことは認められていません。この仕組みにより、外国人材が現場で柔軟に対応できる一方で、制度の趣旨から逸脱しないよう厳格に管理されています。
企業としては、この「関連業務」の線引きを理解し、適正な受け入れを行うことが求められます。
在留資格の要件

外国人が特定技能で製造業に従事するためには、在留資格の取得要件を満たす必要があります。
特定技能1号・2号の違いや、技能評価試験、日本語要件、さらには技能実習からの移行ルートなど、制度を理解するための基本条件が定められています。
特定技能1号の在留資格要件
特定技能1号は、特定技能制度の入り口となる在留資格で、一定の知識や技能を有し、現場で即戦力として働ける外国人に付与されます。
1号の在留期間は最長で5年間であり、家族帯同は認められていません。要件としては、対象分野ごとに実施される「技能評価試験」と「日本語能力試験」に合格する必要があります。
日本語能力は、日常生活や職場での基本的な会話が可能なレベルであるN4相当以上が求められます。さらに、雇用する企業は外国人と直接雇用契約を結び、労働基準法や最低賃金法を遵守しなければならない点が大きな特徴です。
技能実習修了者の場合は、この試験の一部が免除される仕組みも整備されており、実習で培った経験を活かしてスムーズに1号へ移行できるようになっています。
特定技能2号の在留資格要件
特定技能2号は、より高度な技能を持つ外国人材に付与される在留資格です。2号では在留期間の更新に制限がなく、事実上の長期就労が可能であり、配偶者や子どもなど家族の帯同も認められています。
これにより、外国人材が日本で生活基盤を築きながら安定して働ける環境が整います。ただし、2号の対象は1号に比べて限定されており、製造業分野においては「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の一部に限られています。
要件としては、高度な技能を証明するための試験合格や、一定年数以上の実務経験が必要です。
そのため、1号で経験を積み、スキルを磨いた人材が2号へステップアップするケースが多いといえます。企業にとっては長期的な人材確保につながり、戦力としての期待値も非常に高い在留資格です。
技能評価試験の内容と水準
特定技能での就労を希望する外国人は、分野ごとに定められた技能評価試験を受験する必要があります。製造業の場合、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業など、それぞれの職種に応じた試験が用意されています。
試験内容は、基礎的な作業手順や安全管理に関する知識、実技試験による作業技能の確認など、多角的に評価されるのが特徴です。試験の水準は、日本の現場で即戦力として働けるかどうかを判断するレベルに設定されており、決して高度すぎる内容ではありません。
そのため、現地で訓練を受けた人材や技能実習を経験した人材であれば、合格が十分に可能な水準です。また、試験は日本国内だけでなく海外でも実施されており、幅広い国の候補者がチャレンジできる環境が整えられています。
技能実習から特定技能への移行条件
技能実習制度で一定期間働いた外国人が、特定技能へ移行するルートも用意されています。
具体的には、技能実習2号を良好に修了した場合、技能評価試験や日本語試験の一部が免除され、直接特定技能1号への移行が可能です。これは、実習期間中に培った作業経験や日本語能力を評価し、即戦力人材として継続的に就労できるよう配慮された仕組みです。
この移行ルートにより、既に日本での生活や職場環境に慣れている人材を、企業が引き続き雇用できるメリットがあります。一方で、技能実習で不適切な扱いを受けたケースや、実習修了が認められなかった場合は移行が難しくなるため、企業側の適切な管理も重要です。
技能実習から特定技能へのスムーズな移行は、企業と外国人双方にとって大きな利点であり、製造業における人材活用の大きな柱となっています。
受け入れ企業の条件
特定技能「製造業」で外国人材を雇用する場合、受け入れ企業側にも一定の条件や責任が課されています。制度の趣旨を正しく運用するために、事業所の要件、協議会への加入、分野ごとの特別条件、そして適正な労働環境の確保が求められます。
対象となる事業所の要件

特定技能外国人を雇用できるのは、対象産業に該当し、適切な生産活動を行っている事業所に限られます。
例えば、素形材産業や産業機械製造業など、制度で定められた分野での業務を主たる事業としている必要があります。また、企業自体が法令を遵守し、過去に不正な雇用や労働基準法違反がないことも条件とされています。
加えて、雇用契約は直接雇用であることが必須で、派遣労働の形態で受け入れることは認められていません。これらの要件は、外国人材を適切に活用するための最低限の基準といえるでしょう。
協議会加入の義務と役割
特定技能「製造業」分野の受け入れ企業は、所定の協議会に加入することが義務付けられています。
製造業の場合は、工業製品製造技能人材機構(JAIM)などがその役割を担っています。協議会は、外国人材の適正な受け入れや労働環境の改善を監督する役割を持ち、受け入れ企業はその指導や情報共有を受けながら制度を運用していきます。
協議会への加入は単なる形式ではなく、現場での支援やトラブル防止にも直結するため、企業にとって大きな意味を持ちます。万が一加入できない場合、外国人の受け入れが不可能になるため、早い段階での確認が欠かせません。
紡織・縫製分野における追加条件
特定技能の中でも「紡織・縫製」分野は、不適切な労働環境が過去に指摘された経緯から、特別な条件が課されています。
具体的には、人権保護基準の順守、勤怠管理の適正化、時間外労働の制限、そして月給制での給与支払いが義務付けられています。これにより、外国人材が低賃金や過酷な労働条件に置かれることを防ぐ狙いがあります。
企業側は、通常以上に厳しい管理体制を構築する必要があるため、導入には十分な準備と理解が求められます。紡織・縫製は地域産業に根ざす分野でもあり、制度を正しく運用することが産業全体の信頼回復にもつながります。
労働条件遵守と適正な雇用管理
特定技能外国人を受け入れる企業は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法などの法令を遵守する義務があります。
雇用契約は日本人労働者と同等の条件で締結しなければならず、賃金や労働時間、福利厚生の面で不公平があってはなりません。また、受け入れにあたっては「支援計画」を策定し、生活指導や日本語学習支援などを提供することも必要です。
さらに、出入国在留管理庁に対して定期的な報告を行う義務もあり、適正な管理が行われていない場合には受け入れ停止措置が取られることもあります。外国人材が安心して働ける環境を整えることは、企業にとっても持続的な人材確保につながる大切な取り組みといえるでしょう。
申請と手続きの流れ

特定技能「製造業」で外国人材を受け入れるには、所定の申請手続きが必要です。企業は適切な書類を揃え、入管への申請を経て許可を得なければなりません。さらに、登録支援機関との連携や、定期的な報告・更新も含めた継続的な管理が求められます。
申請に必要な書類一覧
特定技能外国人を雇用する際には、多数の書類が必要となります。主なものは、雇用契約書、支援計画書、企業概要を示す資料、納税証明書、社会保険加入証明、そして特定技能外国人本人の在留資格認定証明書交付申請書や学歴・職歴証明などです。
これらの書類は、外国人が適正に雇用され、生活や就労に支障がないことを証明するために欠かせません。不備があれば審査が長引いたり不許可となる可能性があるため、事前に必要書類を正確に準備することが重要です。
申請から許可までのプロセス
手続きは、まず企業が出入国在留管理庁に「在留資格認定証明書交付申請」を行うことから始まります。
申請後、入管は書類審査や必要に応じた確認を行い、問題がなければ在留資格認定証明書が交付されます。その後、外国人本人が海外の日本大使館・領事館でビザ申請を行い、入国・就労が可能になります。
すでに日本国内に在留している場合は「在留資格変更許可申請」の手続きとなります。審査には通常1〜3か月程度かかるため、採用計画は余裕を持って進める必要があります。
登録支援機関の活用方法
特定技能外国人を受け入れる企業は、外国人の生活や就労を支援する「支援計画」を策定する義務があります。
しかし実務的には、自社だけでこれらの支援を行うのは負担が大きいため、多くの企業は登録支援機関を活用しています。登録支援機関は、住居探しの支援、日本語学習のサポート、生活オリエンテーションの実施、行政手続きの補助などを代行してくれます。
これにより、企業は採用活動や業務管理に集中でき、外国人材にとっても安心して働ける環境が整います。適切な支援機関を選定することは、受け入れの成功を左右する大切なポイントです。
定期報告と更新時の注意点
特定技能で受け入れた外国人材については、企業が入管に対して定期的に報告を行う義務があります。
報告内容には、雇用状況、労働条件、支援計画の実施状況などが含まれます。報告を怠った場合や虚偽の内容を提出した場合、受け入れ停止や罰則の対象となることがあります。
また、在留資格は更新が必要であり、その際にも雇用契約の継続性や企業の法令遵守状況が審査されます。更新時に不備があると、外国人が就労を継続できなくなる可能性があるため、企業は日常的に適切な管理を行うことが求められます。
採用のメリットと注意点

特定技能「製造業」を活用することで、企業は人手不足を補い、安定した生産体制を維持できます。しかし一方で、制度の特性を理解せずに受け入れると、リスクやトラブルにつながる可能性もあります。ここでは、メリットと注意点を整理して解説します。
外国人材採用による人手不足解消
最大のメリットは、慢性的な人手不足の解消です。国内の若年層の労働力が減少する中で、特定技能制度は現場に即戦力となる外国人材を確保できる仕組みとして機能します。
特に製造業は、繁忙期や納期の厳しい案件が多く、人員不足が生産性の低下につながりやすい分野です。外国人材の採用により、業務の停滞を防ぎ、安定した供給体制を維持できることは大きな強みとなります。
技能実習生との比較による利点
技能実習制度と比べて、特定技能制度は「即戦力」として外国人材を雇用できる点に利点があります。
技能実習は本来「人材育成」を目的としており、就労はあくまで研修の一環という位置づけでした。そのため実務能力には限界があり、長期的な雇用も難しかったのが実情です。
一方、特定技能は制度の目的自体が「労働力確保」にあり、正規の雇用契約に基づいて働くため、企業にとって戦力化しやすいのが特徴です。また、在留資格2号に移行すれば家族帯同も可能となり、長期的な人材活用にもつながります。
制度運用で想定されるリスク
一方で、特定技能制度には運用上のリスクも存在します。例えば、申請や報告に関する事務負担が大きく、担当者にとって煩雑な作業となる可能性があります。
また、外国人材の生活支援や文化的な違いへの対応が不十分だと、早期離職や職場トラブルの原因となることもあります。さらに、試験制度の整備状況や対象分野の拡張など、制度自体が変化し続けているため、常に最新の情報をキャッチアップする必要があります。
不適切受け入れによる企業側のリスク
制度の趣旨を理解せずに不適切な受け入れを行った場合、企業には重大なリスクが生じます。例えば、労働条件の違反や支援計画の未実施が発覚すれば、受け入れ停止措置や罰則が科される可能性があります。
また、外国人材の人権侵害が疑われる事態になれば、企業の社会的信用が大きく損なわれ、取引先や地域社会からの信頼を失うリスクもあります。外国人材の雇用は「ただ人手を増やす」ものではなく、制度を正しく理解し、責任を持って受け入れることが何よりも重要です。
今後の展望と企業戦略

特定技能「製造業」は、制度の開始から数年を経て着実に広がりを見せています。今後も制度の見直しや拡充が進むことが予想される中で、企業は単なる人手確保にとどまらず、戦略的に外国人材を活用していく姿勢が求められます。
特定技能制度の拡充と見直し動向
政府は特定技能制度について、制度開始当初から対象分野の拡大や受け入れ人数枠の見直しを行ってきました。
製造業分野でも、紙器・段ボール、コンクリート製品、紡織・縫製など新たな区分が追加され、活用の幅は広がっています。また、2024年以降は制度全体の見直しが進められており、特定技能2号への対象分野拡大や、支援体制の強化といった議論も進行中です。
こうした動向は、企業にとって中長期的な人材戦略を考える上で重要な指針となります。
中長期的な人材確保戦略
人材不足が構造的な課題となっている製造業においては、短期的な労働力補充だけでなく、中長期的な視点での人材戦略が不可欠です。
特定技能1号から2号へのステップアップを活用することで、経験豊富な人材を長期にわたって確保できます。また、外国人材の育成・キャリア形成を意識した雇用管理を行うことで、企業への定着率が向上し、結果的に採用コストの削減にもつながります。
単なる「採用」から一歩進んだ「人材活用」の発想が求められる時代になっているといえるでしょう。
まとめ〜持続可能な外国人雇用に向けて〜
今後の製造業における外国人雇用は、持続可能性がカギとなります。そのためには、労働環境の改善や日本語教育の充実、生活支援の強化など、多角的な取り組みが必要です。
外国人材が安心して働き、生活基盤を築ける環境を整えることは、企業のブランド価値や地域社会との共生にもつながります。さらに、多様な文化背景を持つ人材が職場に加わることで、新しい発想や改善が生まれる可能性もあります。
持続可能な外国人雇用の実現は、企業にとって単なる義務ではなく、未来への投資ともいえるでしょう。
特定技能「製造業」は、人手不足に悩む企業にとって大きな可能性を秘めた制度です。しかし、制度を正しく理解し、適切な受け入れ体制を整えなければ、期待する成果を得ることはできません。
私たちの TSBケアアカデミー では、特定技能制度の正しい活用をサポートし、企業と外国人材がともに安心して成長できる仕組みづくりをお手伝いしています。制度の詳細を知りたい方や、実際の導入を検討している企業様は、ぜひ お問い合わせ よりご相談ください。