育成就労制度とは? ― 新しい外国人材受け入れモデルで「育てて働く」未来をつくる

日本の労働市場は、少子高齢化の進行によりかつてない人材不足に直面しています。
その中で、外国人材は産業を支える重要な存在となりつつありますが、長年運用されてきた「技能実習制度」には、実態との乖離や構造的な課題が指摘されてきました。
形式上は「技能移転」を目的としながら、現場では人手確保の手段として活用されるなど、制度の理念と現実のギャップが大きくなっていたのです。
こうした問題を根本から見直すため、政府は2027年をめどに新たな制度──「育成就労制度」──を創設します。
これは、外国人が日本で働きながら技能を磨き、企業と共に成長していくことを目指す、まったく新しい仕組みです。
本記事では、制度の背景や目的、技能実習制度からの主要な変更点、そして企業が実務で押さえるべきポイントを、わかりやすく解説します。
制度移行期を”リスク”ではなく”チャンス”として活かすために、まずはその全体像を整理していきましょう。
育成就労制度とは|背景・目的・施行まで

日本政府は、2027年をめどに「技能実習制度」を廃止し、新たに「育成就労制度」へ移行する方針を示しています。
この制度は、外国人材の”育成”を重視しながら、国内の深刻な人手不足を補う仕組みとして構築されるものです。単なる労働力の確保ではなく、キャリア形成を支援し、安定した就労・定着を実現することを目的としています。
ここでは、その背景や目的、そして施行までの流れを整理します。
なぜ見直すのか:人手不足と旧制度の齟齬
日本の労働人口は年々減少しており、とくに地方や製造・介護・建設などの分野では人材不足が深刻化しています。
技能実習制度は「国際貢献」「人材育成」を目的として導入されましたが、実際には長期就労を前提としない設計で、「実習」よりも「労働力確保」が主目的化してしまう現状がありました。
さらに、転籍(職場変更)の制限や報酬格差、監理団体による不適切な指導など、制度の硬直性と不透明さが課題とされてきました。これらの問題を是正し、「育成」と「適正就労」を両立するために、抜本的な制度改革が必要と判断されたのです。
制度の目的:人材「育成」と「確保」を同時に実現
新制度の最大の特徴は、「日本で働きながら技能を高め、キャリアを形成できる」点にあります。
育成就労制度では、従来の「技能移転」という一方向的な発想から脱却し、日本企業に定着し、特定技能1号・2号へとステップアップできる仕組みを整備します。これにより、外国人本人にとっては中長期的なキャリアの見通しが立ち、企業にとっても「短期雇用に終わらない安定人材」を育成できる環境が整います。
また、制度運用の透明性を高めるために、監理支援体制の許可制化や、費用徴収の明確化なども予定されています。これにより、適正な雇用・支援が担保された”共育型”制度への転換が進むと期待されています。
施行スケジュールと基本方針の流れ(〜2027年想定/経過措置の考え方)
政府は、2024年度中に関連法案を国会に提出し、2025年度から段階的な移行措置を始める予定です。
現行の技能実習生は、一定期間の経過措置のもとで育成就労制度へ移行できる方向で調整が進められています。対象職種や試験制度、監理支援機関の許可要件などの詳細は2026年度までに整備され、2027年度の本格施行が想定されています。
経過措置の期間中は、技能実習制度のもとで来日した実習生も、要件を満たせば新制度下での「育成就労者」として就労継続が可能になる見込みです。つまり、企業側は「実習」から「育成就労」への自然な移行を見越した採用・教育計画を立てることが求められます。
政府は、現場で混乱が生じないよう、段階的なガイドライン策定と自治体・企業への支援体制を強化していく方針です。
何が変わる?技能実習→育成就労の主要ポイント
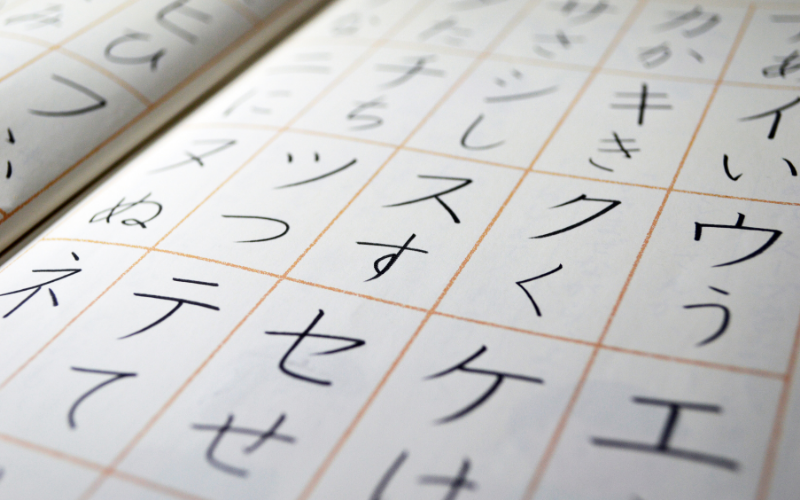
育成就労制度は、技能実習制度の延長ではなく「再設計された新制度」です。
従来の「実習生を一定期間受け入れて帰国させる」枠組みから脱し、外国人が日本で段階的にスキルアップし、長期的に働ける仕組みへと転換されます。
この章では、目的・制度構造・キャリア設計という3つの観点から主要な違いを整理します。
目的・対象分野・在留設計の違い(比較早見)
技能実習制度は「国際貢献」を掲げながらも、実際には人手不足対策として機能していました。
一方で育成就労制度は、その実態に即して「人材育成」と「就労」を正式な目的として明確化しています。つまり、”名目上の実習”から、”実質的な労働・育成制度”へと生まれ変わるのです。
技能実習制度と育成就労制度(新)の比較
| 比較項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度(新) |
|---|---|---|
| 制度目的 | 技能移転・国際貢献 | 人材の育成と確保(長期定着型) |
| 在留期間 | 最長5年 | 原則3年(特定技能への移行前提) |
| 転籍 | 原則不可(例外のみ) | 一定条件下で本人希望も可 |
| 監理体制 | 監理団体が主導 | 許可制の監理支援機関が指導・監査 |
| 対象分野 | 主に製造・介護・建設など | 特定技能16分野を中心に再構成予定 |
ポイント育成就労制度は、特定技能制度への接続を前提とした「入口」の位置づけ。企業は「3年後に特定技能として継続雇用するか」の視点で、採用・教育設計を行う必要があります。
このように、育成就労制度は特定技能制度との接続を前提とした”入口”の位置づけとなります。企業側も「3年後に特定技能として継続雇用するかどうか」という視点で採用や教育を設計する必要があります。
評価要件の段階設計:日本語(A1→A2→B1)と技能試験
育成就労制度では、「成長過程が見える制度運用」が特徴です。日本語能力・技能水準の双方に段階評価が導入され、学習進捗を客観的に把握できる仕組みになります。
具体的には、日本語能力はCEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)に基づくA1〜B1段階を採用。
- 入国時:A1レベル
- 初歩的な日常会話が可能。
- 1〜2年目:A2レベル
- 職場での基本的意思疎通が可能。
- 修了時:B1レベル
- 一定の自立的コミュニケーションが可能。
さらに、業種別に設定される技能評価試験の合格が、次段階(特定技能1号)への移行要件となります。これにより、単なる「在留期間の経過」ではなく、成果に基づく評価とキャリア移行が可能になります。
企業側は、日本語学習支援や試験対策支援など、教育コストを「育成投資」として位置づける視点が求められます。
キャリアパス:3年育成→特定技能1号→2号(家族帯同の入口)
育成就労制度のゴールは「日本企業に長期的に貢献できる人材を育てる」ことです。そのため、制度は明確にキャリアパス型へ再構築されています。
- 育成就労(3年)
- 基礎技能と日本語を修得
- 特定技能1号(5年)
- 一定の専門性と自立的業務遂行
- 特定技能2号(無期限)
- 高度技能者としての定着・家族帯同可
この流れにより、外国人本人には中長期的な生活設計の道筋が生まれ、企業にとっても「短期離職リスクの低い人材確保」が可能となります。特に2号への昇格は、家族帯同が認められる唯一の就労資格であり、生活基盤を持つ人材=長期的戦力として定着促進が期待されます。
企業は今後、「3年で終わる制度」ではなく「8年〜無期限へ続くキャリア育成の入り口」として、この制度をどう活用するかが鍵になります。
対象分野と”外れる可能性”の見極め
育成就労制度では、これまで技能実習制度の下で受け入れが認められていた職種をベースに再編されます。しかし、単純な「引き継ぎ」ではなく、”育成を通じての成長が見込める職種”のみが対象となるのが大きなポイントです。
ここでは、特定技能制度との関係性を踏まえながら、対象分野の方向性と見極めの軸を解説します。
特定技能16分野をベースにした対象設定
育成就労の対象は、原則として特定技能16分野を中心に構成される見込みです。これは、すでに日本語・技能評価試験などの仕組みが整っており、キャリアパス設計がしやすいためです。
代表的な分野には、介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、外食などが含まれます。
一方で、技能実習では受け入れがあっても、単純労働に近い業務や育成要素が乏しい職種は、対象外となる方向で検討が進んでいます。つまり、将来的に特定技能へとつながる専門性の高い領域が優先されるということです。
就労を通じた育成になじむ/なじまない業務の判断軸
新制度では、「育成」と「就労」の両立が可能かどうかが重要な判断軸になります。具体的には以下のような観点が重視されます。
- 技能の熟達性:段階的にスキルアップが可能か
- 教育可能性:企業や支援機関が体系的に育成できるか
- 業務の専門性:他業種でも応用可能な知識・技能か
- 日本語習得の実用性:業務遂行に一定の言語力が必要か
これらを満たさない業務は「単純労働」とみなされ、制度趣旨に合致しないと判断される可能性があります。したがって企業は、「単純作業を担ってもらう」ではなく、「技能を身につけて将来の戦力となる」人材を育てるという発想が求められます。
受入れ見込数(上限枠)の考え方と実務インパクト
政府は、各分野ごとに受入れ上限(キャップ)を設定する方向で検討しています。これは、労働市場への影響や地域バランスを考慮するためです。
特に介護や製造業などの主要分野では、既存の技能実習生を円滑に引き継ぐ枠組みを優先的に整備し、段階的に新規受け入れ枠を広げる見通しです。
ただし、枠の設定はあくまで国全体での方針であり、実際の採用可能数は地方自治体や地域協議会の判断に左右される場合もあります。企業にとっては、早期に制度動向を把握し、自社の採用計画や教育体制を準備しておくことが、競争優位につながるといえるでしょう。
転籍ルールの実務
育成就労制度では、技能実習制度で厳しく制限されていた「転籍(就労先の変更)」が、一定の条件のもとで認められるようになります。これは、外国人本人のキャリア形成と、企業側の受け入れ負担軽減を両立させるための大きな改革です。
ここでは、「やむを得ない事情」と「本人希望による転籍」の二つのケースに分けて、手続きや留意点を整理します。
やむを得ない事情の拡大と手続の柔軟化
これまでの技能実習制度では、受入企業の倒産やハラスメントなど、極めて限られた場合のみ転籍が認められていました。育成就労制度では、この「やむを得ない事情」の範囲がより現実的かつ柔軟に拡大されます。
例えば、以下のようなケースが想定されています。
- 企業の経営悪化や廃業、自然災害による事業停止
- 労働条件の不履行、長時間労働や賃金未払い
- パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等の人権侵害
- 健康上の理由で職場変更が必要な場合
このような場合、本人または監理支援機関が申出を行い、行政が調査の上で転籍を許可します。従来は「所属先が変わる=制度違反」とされていた構造から、適正な理由に基づく転籍を制度的に保障する形に変わります。
本人意向による転籍:就労1〜2年・同一区分・試験要件
育成就労制度の大きな転換点は、本人の希望による転籍も一定条件のもとで認められる点です。ただし、自由な転職を意味するものではなく、制度の趣旨を踏まえたルールが設けられます。
主な条件としては、
- 原則として就労1〜2年の実績を有していること
- 同一分野・同一区分の就労先への転籍であること
- 一定の技能評価試験や日本語能力試験の合格を条件とする見込み
つまり、育成段階を踏んだ上での「キャリア形成の一環としての転籍」が想定されています。企業側としては、優秀な人材を維持するために、教育・待遇・労働環境の整備が競争要素になることを意識する必要があります。
申出→あっせん→新計画認定のフロー/初期費用補填・「当分は民間紹介不可」
転籍手続きは、本人の申出を起点に、監理支援機関や行政によるあっせんを経て新たな育成計画を認定する形で進みます。このプロセスにより、制度全体の透明性と公平性が担保されます。
また、転籍に伴う企業側の初期教育費・受入費用の一部補填制度も検討されており、受入先企業の負担軽減が図られる見込みです。
ただし、制度施行当初は、混乱を避けるため「民間職業紹介事業者による転籍あっせんは禁止」とされています。
一定期間は、行政や登録支援機関を通じた公式ルートのみでマッチングを行うことになります。
この運用方針は、制度が安定するまでの安全弁的措置であり、将来的には民間参入も段階的に解禁される見通しです。
監理・支援・送出しの新体制

育成就労制度では、技能実習制度で指摘されてきた「監理団体の不正・不透明な費用構造・監督不備」を是正するため、運用体制の抜本的見直しが行われます。
制度の信頼性を確保するためには、受け入れ企業だけでなく、監理・支援・送出しの各機関が連携し、責任の所在を明確にすることが不可欠です。
監理支援機関の許可制・外部監査・独立性の確保
これまでの監理団体制度は「認可制」であり、内部運営の透明性に課題がありました。新制度では、これを「許可制」へと格上げし、国が厳格に管理・監督します。
許可の更新には、外部監査報告や財務情報の開示が義務付けられ、第三者によるチェック体制が導入されます。
また、監理支援機関は受け入れ企業から独立した立場で運営される必要があり、利害関係の排除が求められます。
- 外部監査の定期実施
- 不適正行為(過剰徴収・虚偽報告など)の厳罰化
- 職員の倫理研修義務化
これにより、支援機関は単なる「手続き代行」ではなく、適正雇用と人材育成の専門的支援者としての役割が期待されます。
外国人育成就労機構の監督・相談援助強化/自治体・地域協議会の関与
制度全体を統括するため、新たに「外国人育成就労機構(仮称)」が設立されます。この機構は、現行の外国人技能実習機構(OTIT)の機能を拡充・統合する形で設置され、以下の役割を担います。
- 監理支援機関・受入企業の指導・監査
- 外国人本人や支援機関からの相談対応窓口
- 不当行為・人権侵害の通報対応
- 教育・日本語学習支援のガイドライン整備
さらに、自治体や地域協議会の関与が強化され、地方レベルでの実態把握や、地域連携によるトラブル予防体制の構築が進められます。
地域の現場を知る行政と企業・支援機関が一体となって「見守りネットワーク」を形成することで、制度の透明性と現場対応力が飛躍的に高まると期待されています。
MOC締結国限定・手数料の透明化/不法就労助長罪の厳罰化
送り出し国との関係も、制度改革の重要な柱です。
新制度では、二国間覚書(MOC)を締結した国に限定して受入れを行う方針が明確化されます。これにより、政府間での責任分担と情報共有が強化され、違法ブローカーの介入を防ぐ狙いがあります。
また、手数料の上限や徴収方法を可視化する「費用の透明化ルール」が導入され、外国人本人が不当な負担を強いられない仕組みが整備されます。
さらに、不法就労や不当な仲介行為を助長した法人・個人に対しては、不法就労助長罪の罰則を大幅に強化。実効性のある監視・制裁システムが整備される予定です。
こうした枠組みにより、送り出しから受入れまでの一貫した公的管理体制が実現し、企業・外国人双方にとって安心できる制度運用が可能となります。
企業が押さえる実務:メリデメ・コスト・定着策

育成就労制度は、単なる制度変更ではなく、企業の採用・教育・マネジメント体制そのものを再構築する契機になります。
外国人材の長期的な活躍を見据えるうえで、メリットとリスクの両面を把握し、コスト構造や教育方針を計画的に整備しておくことが欠かせません。
以下では、企業が特に注意すべき3つの実務ポイントを整理します。
メリット:長期就労の見通し/日本語水準の底上げ
育成就労制度の導入により、企業が得られる最大のメリットは「長期雇用の見通しが立つ」ことです。
これまでの技能実習制度では、最長5年で帰国する前提があり、人材育成への投資が回収しづらい構造でした。
しかし新制度では、育成就労→特定技能1号→2号とステップアップできるため、企業は人材を長期的に育て、安定戦力として定着させることが可能になります。
さらに、制度上で日本語能力の段階評価(A1→B1)が義務化されることで、現場の安全管理・生産性・チーム内コミュニケーションが大きく改善します。
日本語教育への支援が標準化されることは、外国人本人のキャリア形成にも直結し、結果として離職率の低下にもつながるでしょう。
デメリット:採用コスト増・転職リスク・法令対応負荷
一方で、育成就労制度は「制度的に成熟した分、企業側の責任も重くなる」点に注意が必要です。
まず、採用初期にかかる費用が増加します。日本語学習・技能試験支援・監理支援機関との連携コストなど、従来よりも教育投資と事務負担が拡大する見込みです。
また、転籍が制度的に認められるため、待遇や職場環境の悪化があると人材流出のリスクも高まります。
さらに、外部監査・契約明示・記録義務などの法令対応を怠ると、許可取消や罰則の対象となるおそれもあります。つまり、これからの企業は「受け入れるだけ」ではなく、「選ばれる職場になること」が重要な競争条件になります。
対応チェック:費用項目・教育計画・賃金設計・労契明示と記録化

育成就労制度の安定運用には、以下の4つの観点を押さえた内部管理が不可欠です。
- 費用項目の明確化
-
- 受入費、監理支援費、教育費、通訳・翻訳費などを明細化し、契約書に明示。
- 費用負担の不透明化は、制度違反の原因になりやすい。
- 教育・研修計画の策定
-
- 日本語・技能教育を体系的に設計し、評価とフィードバックを記録化。
- 特定技能への移行支援を視野に入れた育成カリキュラムを整備。
- 賃金設計の適正化
-
- 日本人と同等以上の報酬を原則とし、昇給・賞与体系を明示。
- 業務範囲・責任に応じた評価基準を設定し、職務内容の不一致を防ぐ。
- 労働契約・記録の透明化
-
- 労働条件通知書・雇用契約書の多言語化対応を推進。
- 出勤簿・給与明細・指導記録などを保存し、外部監査にも対応できる体制を構築。
これらを定期的に見直し、支援機関・自治体と連携しながらPDCAを回すことが、育成就労の成功と人材定着の鍵になります。
まとめ|制度移行期をチャンスに変えるために
育成就労制度は、単なる技能実習制度の延長ではなく、外国人材と企業が「共に育つ」仕組みへの転換です。
日本社会全体が抱える人手不足に対して、より持続的で実践的な解決策として期待される一方、制度運用には企業の理解と準備が欠かせません。
制度の目的は「労働力の補充」ではなく、「人材の育成と定着」です。
したがって、採用計画の段階から日本語教育・キャリア形成・定着支援を一体化し、”短期雇用から育成型雇用へ”意識をシフトすることが重要になります。
また、転籍や監査のルールが明確化されることで、企業の法令遵守力・職場環境整備力が問われる時代に入ります。
この制度をチャンスに変えるためには、
- 制度内容の正確な理解
- 教育投資を前提とした採用設計
- 外部支援機関との適切な連携
がカギとなります。
育成就労制度=「長く働ける人材をどう育てるか」という経営課題への回答。今こそ、自社の受け入れ体制を見直すタイミングです。
外国人雇用・制度移行のご相談はTSBケアアカデミーへ
育成就労制度への対応や特定技能人材の採用・定着支援については、専門的な知識と最新の法令理解が不可欠です。
TSBケアアカデミー(https://tsb-care.com/)では、企業ごとの課題に応じた制度導入サポート・人材マッチング・教育設計などをトータルでご支援しています。
新制度への移行を「負担」ではなく「チャンス」と捉え、将来に続く人材戦略をともに構築していきましょう。
制度の詳細やご相談は、以下からお気軽にお問い合わせください。








