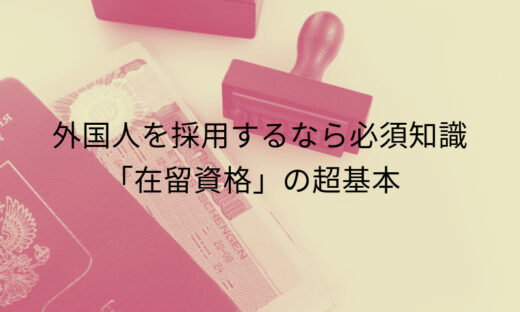特定技能の「直接雇用」とは?手続き・メリット・注意点を徹底解説!

人手不足が深刻化する中、即戦力となる外国人材を「特定技能」で雇用する企業が増えています。なかでも注目されているのが、ブローカーを介さず企業が直接雇用する形態です。
本記事では、特定技能制度における“直接雇用”の基礎知識からメリット、注意点、手続きの流れまでをわかりやすく解説します。
「直接雇用」とは?特定技能制度における基本的な考え方
特定技能制度においては、「直接雇用」が原則とされており、受け入れ企業が外国人材を自社の従業員として雇用する仕組みです。これは技能実習制度とは異なる大きな特徴であり、企業には雇用主としての明確な責任が求められます。
本章では、直接雇用と間接雇用の違いや、制度としてなぜ直接雇用が義務化されているのかについて詳しく解説します。
直接雇用と間接雇用の違いとは?特定技能制度における原則
特定技能制度では、原則として外国人材は企業と直接雇用契約を結ぶ必要があります。これは、派遣や請負といった「間接雇用」では、労働環境や待遇の管理が不十分になりやすく、技能実習制度の過去の課題を繰り返さないための対策でもあります。
直接雇用であれば、受け入れ企業が労働条件の整備や支援体制の構築に責任を持つため、外国人労働者が安心して働ける環境を作ることができます。企業にとっても、定着率の向上やスムーズなコミュニケーションの促進といったメリットが期待できるため、制度の趣旨を理解し、適切な雇用形態を選択することが重要です。
なぜ直接雇用が義務づけられているのか?制度設計の背景と目的
特定技能制度で直接雇用が原則とされているのは、技能実習制度など従来の外国人受け入れ制度における問題点を教訓とした結果です。かつては仲介機関を介した雇用が主流で、劣悪な労働環境や人権侵害、失踪者の増加などが社会問題となっていました。
こうした背景を受け、特定技能では企業が労働者と直接契約を結び、雇用主としての責任を明確にする制度設計がなされています。直接雇用とすることで、適正な賃金の支払いや生活支援の提供など、より安定した就労環境が実現しやすくなります。
制度の信頼性を高め、外国人材の安心と定着を図る狙いがあるのです。
直接雇用の流れと必要な手続きとは?

特定技能外国人を直接雇用するには、企業側が行うべき準備や手続きが多数あります。求人の出し方や採用プロセス、在留資格の申請手続きまで、段階ごとに必要な対応を理解しておくことが重要です。
ここでは、実際の採用フローに沿って、スムーズに進めるためのポイントを詳しく解説します。
事前準備から採用までの流れ(求人・選考・契約)
特定技能人材の直接雇用を行うには、まず制度に適した採用体制の整備が必要です。業務内容が「特定産業分野」に該当しているかを確認し、支援体制や労働条件を明確に整えた上で、求人活動に進みます。
採用までのおおまかな流れは以下の通りです:
- 求人票の作成(外国人向けにわかりやすく)
- 求人媒体・送り出し機関・登録支援機関などを通じて募集
- 書類選考・面接などによる人材選定
- 雇用契約の締結(母国語での契約書も必要)
雇用契約には、就労内容・報酬・勤務時間・支援内容など、特定技能制度に基づく詳細な記載が求められます。書類不備や説明不足は後のトラブルにつながるため、慎重に準備を進めましょう。
在留資格認定や申請手続きに必要な書類と注意点
外国人を特定技能で直接雇用するには、在留資格認定証明書の交付申請が必要です。この申請は採用後すぐに行うのが理想で、手続きをスムーズに進めるには、必要書類を漏れなく準備することが重要です。
主な提出書類は以下の通りです:
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 雇用契約書(日本語と母国語の両方)
- 支援計画書
- 企業の登記事項証明書、直近の決算書
- 技能試験・日本語試験の合格証明書の写し
- 労働条件通知書など労働条件に関する書類これらはすべて、地方出入国在留管理局に提出します。書類に不備があると審査に時間がかかるだけでなく、不許可になる可能性もあります。記載内容が正確で整合性が取れていることが求められるため、提出前に入念なチェックが必要です。可能であれば、行政書士や専門機関のサポートを受けると安心です。
特定技能で直接雇用するメリットとは?

外国人材の雇用には、派遣などの間接的な方法ではなく「直接雇用」が特定技能制度の基本とされています。では、直接雇用にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
コスト面だけでなく、長期的な人材定着や育成、職場の安定にも関わる重要なポイントがあります。ここでは、企業側の視点で具体的な利点を整理してご紹介します。
人材の定着率向上や育成効果に期待できる理由
特定技能制度における「直接雇用」は、企業と外国人材との間に信頼関係を築きやすく、結果として高い定着率につながる傾向があります。派遣と異なり、雇用主が直接サポートを行うことで、職場への帰属意識やモチベーションが高まりやすいのです。
また、直接雇用であれば、現場での教育やOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)も継続的に実施しやすくなり、外国人材がスキルを身につけながら成長していく環境を整えることができます。育成にかけた時間が無駄になりにくく、長期的な戦力として活躍してもらえる可能性が高まります。
さらに、制度上、転職の自由度が限られているため、労働環境を整えていれば、安定した雇用関係が築ける点も企業側の大きな利点といえるでしょう。
ブローカー排除による透明性のある雇用管理
特定技能制度では、外国人材の保護と適正な雇用環境の確保を目的として、「直接雇用」が原則とされています。その背景には、過去に問題視されてきたブローカーや悪質な仲介業者の介在を排除するという大きな意図があります。
第三者が間に入ることで、労働者が高額な手数料を負担させられたり、就業条件と異なる実態に直面したりするリスクが増大します。直接雇用を義務化することで、企業と人材との間に透明な契約関係を築き、不当な搾取や情報の不一致を未然に防ぐことが可能になります。
また、雇用主が責任を持って労務管理を行う体制が求められるため、労働条件の明示、適切な給与支払い、福利厚生の整備といった点でも制度的な健全性が確保されやすくなります。これは、企業にとっても長期的に信頼を築くうえで重要な要素といえるでしょう。
直接雇用における注意点と実務上のポイント
特定技能人材を直接雇用する際には、制度上のルールを守ることはもちろん、実際の現場で起こりやすいトラブルや誤解にも注意が必要です。労働条件の明示や生活支援体制の整備、文化的な配慮など、受け入れ企業には多面的な対応が求められます。
この章では、直接雇用における代表的な注意点と、円滑な受け入れを進めるための実務上のポイントを紹介します。
労働条件や労務管理の整備で押さえるべき法的ポイント
特定技能人材の直接雇用では、日本人と同等以上の労働条件を提供することが法的に求められます。
特に注意すべきポイントは以下のとおりです。
- 賃金水準の確認:地域の同種業務に従事する日本人と比べて不利にならないよう、基本給・手当・残業代などの条件を設定する必要があります。
- 労働契約書の作成:労働条件は、翻訳付きで明確に書面化し、本人に理解してもらうことが義務づけられています。
- 労働時間や休日の管理:36協定に基づいた残業管理や休日取得なども、きちんと実施する必要があります。
こうした法的整備を怠ると、在留資格の取り消しや企業側の罰則にもつながるため、事前の確認と整備が不可欠です。
支援計画の実施義務と外国人への生活支援の内容とは?
特定技能人材を直接雇用する企業には、「支援計画」の策定と実施が義務づけられています。これは、外国人が安心して日本で働き生活できるよう、企業側が包括的なサポートを提供する制度です。
具体的な支援内容は以下のとおりです:
- 日本語学習の機会の提供:学習教材や教室の紹介など、語学力向上を支援。
- 生活に関する情報提供:医療機関の利用方法や交通ルール、ゴミ出しルールなどを母国語で説明。
- 行政手続きの同行支援:住民登録や年金・保険の加入手続きに同行。
- 相談対応窓口の整備:労働条件や生活の悩みに対する相談体制を整える。これらの支援を怠ると、受け入れ機関としての適格性を問われる恐れがあるため、計画的な体制づくりが重要です。
受け入れの準備と社内体制の整備を進めよう

特定技能人材の直接雇用を円滑に進めるためには、採用だけでなく、受け入れ後の体制整備が不可欠です。
外国人材が働きやすく、職場になじみやすい環境を整えることで、定着率の向上にもつながります。とくに、社内の理解促進や、外部支援機関との連携体制づくりは、実務上の重要なポイントとなります。
社内説明・教育のポイントと外国人とのコミュニケーション方法
外国人材を受け入れるにあたっては、現場社員の理解と協力が欠かせません。まず、社内向けに「特定技能制度とは何か」「どのような支援が必要か」などの基礎知識を共有しましょう。
また、異文化理解や簡単なやさしい日本語での指示の出し方なども、事前に教育しておくと現場での混乱を防げます。
外国人との日常的なコミュニケーションでは、以下のような工夫が有効です:
- 難解な日本語や専門用語を避ける
- ジェスチャーや図解を交える
- 翻訳アプリや通訳者を必要に応じて活用する
- 定期的な面談や声がけで不安や不満を拾うこのような工夫を積み重ねることで、信頼関係を築きやすくなり、トラブル防止にもつながります。
外部の支援機関や登録支援機関との連携のすすめ
特定技能の受け入れに不安がある場合は、外部の支援機関と積極的に連携することで、実務負担を軽減できます。
特に登録支援機関は、生活支援業務の代行が可能で、法的要件を満たしながら受け入れ体制を整える強力なパートナーになります。
登録支援機関が対応可能な業務には、以下のようなものがあります:
- 入国前の生活オリエンテーション実施
- 行政手続きの同行支援
- 日本語学習の助言
- 生活・職場での悩み相談への対応
- 母国語での定期的な面談
中小企業では自社のみで全ての支援を賄うことが難しいケースも多いため、信頼できる支援機関との連携が、制度に準じた運用と人材の定着を実現するうえでの鍵となります。
特定技能の直接雇用は中小企業にとって大きなチャンス

人手不足に悩む多くの中小企業にとって、特定技能制度を活用した外国人材の直接雇用は、即戦力となる人材を確保できる貴重な手段です。
単なる労働力の補填にとどまらず、長期的な成長や組織の多様性にもつながる制度であることを理解し、受け入れ体制を整えることが成功の鍵となります。
制度を活かすために必要な“受け入れの姿勢”とは?
特定技能人材を受け入れるうえで、企業が最も大切にすべきなのは「人」として尊重する姿勢です。言語や文化の違いを乗り越えて協働するには、教育だけでなく信頼関係の構築が不可欠です。
たとえば、以下のような姿勢が求められます:
- 教える側の都合ではなく、相手の理解に寄り添う姿勢
- 「失敗して当たり前」という前提での丁寧なフォロー
- 意思疎通のズレを責めるのではなく、改善のチャンスととらえる柔軟性
制度を活かすには、外国人材を一時的な労働力と見なすのではなく、職場の一員として受け入れる文化が社内に根づくことが不可欠です。
今後の展望と、制度改正の動向を把握することの重要性
特定技能制度は、今後さらに拡充・改正が見込まれる制度です。たとえば、2023年には「特定技能2号」の対象分野が大幅に拡大されました。こうした動きは、長期雇用や定着を目指す企業にとって大きな追い風です。
中小企業が安定した人材確保を実現するためには、制度の最新動向を定期的にチェックし、自社の方針や採用戦略に反映させていくことが重要です。行政からの情報発信だけでなく、登録支援機関や専門家との連携を通じて、変化への対応力を高める姿勢が求められます。
こちらが記事の「まとめ」部分の短文です。読み手が内容を振り返りやすく、前向きな印象で締めくくれるよう意識しました。
まとめ
特定技能制度における「直接雇用」は、単なる人材確保にとどまらず、中小企業の成長や職場の活性化にもつながるチャンスです。制度の趣旨を理解し、丁寧な準備と受け入れ体制を整えることで、外国人材との信頼関係を築き、持続可能な雇用へとつなげていきましょう。
直接雇用に不安のある中小企業の皆さまへ
「本当に直接雇用でうまくいくの?」「制度を守れているか自信がない…」
そんな不安をお持ちの企業担当者様は少なくありません。
TSBケア・アカデミーでは、制度に準じた直接雇用のサポートから支援計画の実施代行、在留資格申請のサポートまで、ワンストップでご支援しています。
「まずは話だけ聞いてみたい」という方も大歓迎です。
▶ お問い合わせはこちらから
▶ TSBケア・アカデミー公式サイトはこちら