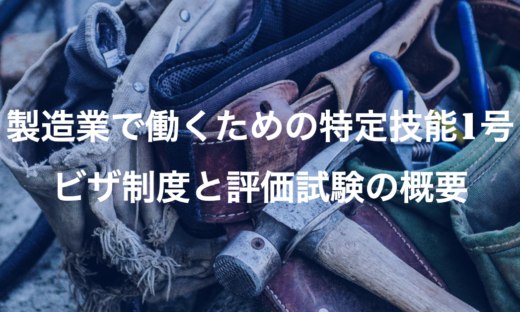外国人介護人材の在留資格を徹底解説!採用前に知っておきたいポイントまとめ

介護現場における人手不足が深刻化するなか、外国人材の採用は多くの施設にとって現実的な選択肢となっています。
しかし、外国人を介護職として雇用するには、適切な「在留資格」を取得してもらう必要があります。在留資格には複数の種類があり、制度の内容や要件、更新・転職の条件もそれぞれ異なります。
本記事では、なかでも安定した長期雇用が可能な在留資格「介護」に焦点を当て、その制度概要、取得方法、他の在留資格との違い、注意点などを詳しく解説します。
外国人介護職の採用を検討している施設の管理者・人事担当者の皆さまに向けて、制度を正しく理解し、スムーズな受け入れのための参考となる情報をお届けします。
在留資格「介護」とは?制度の基本を理解しよう
外国人が日本の介護施設などで働くためには、適切な在留資格が必要です。なかでも「介護」という在留資格は、他の就労系資格とは異なり、国家資格「介護福祉士」を取得した外国人が、介護職として長期的に安定して働ける制度です。本章では、この資格の制度概要や就労範囲について解説します。
在留資格「介護」の制度概要と導入背景
在留資格「介護」は、2017年に新設された在留資格で、介護福祉士の資格を取得した外国人が、日本の介護施設で専門職として働くことを可能にする制度です。
これは、急速に進む高齢化により深刻化する介護人材不足を背景に、日本人だけでは人手をまかなえないという現状を受けて導入されました。
この資格の大きな特徴は、「専門性の高い職種」として法的に位置付けられており、在留期間の更新に上限がなく、将来的な永住や家族帯同も視野に入れられる点にあります。
そのため、外国人本人にとっても安定的なキャリアパスを築ける在留資格であり、企業側にも長期雇用を前提とした人材戦略が可能になります。
取得すればどんな仕事ができる?介護分野での就労範囲
在留資格「介護」で就労できるのは、主に介護福祉士としての専門的な業務に限られます。具体的には、利用者の身体介護(入浴、排泄、食事など)や生活支援、介護計画の作成、他のスタッフとの連携業務など、介護施設や訪問介護における幅広い業務が含まれます。
一方で、単純労働と見なされる清掃や洗濯、調理補助などの業務を主たる業務として行うことは認められていません。
また、介護福祉士としての資格を前提としているため、未資格者がこの在留資格で働くことはできません。つまり、在留資格「介護」は、実務経験や研修を積んだ上で国家資格を取得した外国人に与えられる、プロフェッショナル向けの在留資格であるといえます。
在留資格「介護」の取得要件と申請ルート

外国人が在留資格「介護」を取得するには、特定の学歴や資格、日本語能力などが求められます。特に、介護福祉士国家試験の合格が前提であり、福祉系の学校で学ぶことが主なルートとなっています。
本章では、取得に必要な条件と、実際の申請までの流れを詳しく解説します。
必要な学歴・資格・日本語能力
在留資格「介護」の取得には、以下の要件をすべて満たす必要があります。
学歴:日本国内の福祉系専門学校(養成施設)や大学等で、介護福祉士養成課程を修了すること。修業年限は通常2年以上です。
資格:介護福祉士国家試験に合格し、介護福祉士登録を行うこと。
日本語能力:明確な試験基準はありませんが、学校の授業や国家試験、現場での業務遂行に必要な日本語力が求められます。目安としては日本語能力試験N2以上が望ましいとされています。
日本の福祉系教育機関に留学し、実習を経て国家資格を取得することが基本となるため、他の在留資格に比べて取得のハードルは高めです。その分、専門性のある在留資格として長期的なキャリア形成が可能です。
取得までのルート:福祉系留学→介護福祉士国家試験合格
外国人が在留資格「介護」を取得するまでの一般的な流れは、以下のようになります。
日本の福祉系教育機関に留学
↓
在留資格「留学」で入国し、介護福祉士養成校に2年以上通学。
↓
学業と同時に、介護施設での実習を行います。
↓
介護福祉士国家試験の受験・合格
↓
卒業見込みの年に国家試験を受験。
↓
試験に合格すると、介護福祉士としての登録が可能になります。
↓
在留資格「介護」へ変更申請
↓
国家資格を得た時点で、在留資格を「留学」から「介護」へ変更します。
これにより、正式に介護職として日本での就労が可能になります。
このルートは、しっかりと学業・実習を積み重ねた上で国家資格を取得するものであり、即戦力としての活躍が期待される制度設計になっています。
申請時に必要な書類と手続きの流れ
在留資格「介護」の申請または変更を行う際には、以下の書類が主に必要となります。
・在留資格変更許可申請書(または在留資格認定証明書交付申請書)
・パスポートおよび在留カード
・介護福祉士登録証の写し
・雇用契約書や採用内定通知書など、就労先との関係を示す書類
・勤務先の会社概要資料(登記事項証明書、会社案内など)
・卒業証明書・成績証明書(介護福祉士養成校)
・住民税の納税証明書や課税証明書(該当する場合)
手続きの流れは以下のとおりです。
必要書類を準備し、地方出入国在留管理局に申請
↓
通常1〜2か月で結果通知
↓
許可後、在留カードが「介護」に更新され、就労可能に
提出書類に不備があると審査が長引くため、学校や就職先と連携し、確実な準備が求められます。
他の在留資格との違いと比較ポイント
外国人が介護分野で働くための在留資格には、「介護」以外にも「特定技能」「技能実習」「EPA(経済連携協定)」など複数の制度があります。これらは目的や取得要件、就労期間、転職の自由度などが大きく異なります。ここでは、それぞれの違いを整理し、採用担当者が制度を選ぶ際の比較ポイントをわかりやすく解説します。
「特定技能(介護)」との違い(要件・更新・転職の自由度など)〜要件・更新・転職の自由度など〜
「特定技能(介護)」と在留資格「介護」は、いずれも介護職として就労可能ですが、制度の設計や要件に大きな違いがあります。

「特定技能」は即戦力の確保を目的としており、比較的短期的・実務的な人材確保に向いています。一方、「介護」は専門性の高い職種として長期雇用を前提とする制度です。
「技能実習(介護)」との違い(目的・雇用形態・キャリアパス)〜目的・雇用形態・キャリアパス〜
「技能実習(介護)」は、技能移転による国際貢献を目的として設けられており、制度の趣旨や就労形態は在留資格「介護」と大きく異なります。

技能実習制度は、企業側にも監理団体や計画認定などの手続きが必要であり、制度的な制限も多く存在します。継続的な雇用やキャリア形成を見据える場合は、「介護」の方が柔軟性があります。
「EPA介護福祉士候補者」との違い(経済連携協定との関係、受け入れ国)
EPA(経済連携協定)に基づく介護福祉士候補者の受け入れ制度は、政府間協定により特定の国からの受け入れを前提とした特別な制度です。日本は現在、以下の国々と協定を結んでいます。
・インドネシア
・フィリピン
・ベトナム

EPA制度は受け入れ国との外交的枠組みで動いているため、国ごとに申請枠や受け入れ条件が異なります。一方、「介護」は制度上、出身国を問わず取得可能であり、より幅広い人材採用が可能です。
在留資格「介護」で働くメリットと注意点

在留資格「介護」は、他の就労系資格と比べて専門性が高く、安定した雇用が期待できる制度です。介護福祉士の資格を取得していれば、長期的なキャリア形成や永住申請も視野に入れられます。一方で、転職時の注意点や職種の制限もあるため、採用側も制度の特徴を正しく理解しておくことが大切です。
安定した長期就労とキャリア形成が可能
在留資格「介護」の最大のメリットは、介護福祉士として専門性を活かしながら、長期的かつ安定的な雇用が可能である点です。更新制ではあるものの、要件を満たせば在留期間の制限なく働き続けることができ、将来的な永住権取得にもつながります。
また、介護福祉士は国家資格であり、スキルアップや管理職への昇進といったキャリアパスが明確に設計されています。介護現場での実績を積み重ねれば、チームリーダーや教育係としての役割を担うことも可能です。
さらに、日本国内での介護福祉士資格は国際的にも評価される傾向があり、帰国後のキャリアにも活かしやすいという利点もあります。
転職の自由度や永住申請にもつながる
在留資格「介護」を持っていれば、同一の介護業務であれば転職も可能です。他の制度(例:技能実習)と異なり、転職による在留資格の喪失リスクが少ないため、より柔軟な働き方ができます。ただし、職種が「介護業務」に限られているため、他職種への変更は原則できません。
また、介護福祉士として一定年数以上の就労実績や安定した収入があれば、永住申請の条件を満たす可能性が高くなります。これは、採用側にとっても、長期雇用を前提とした人材育成がしやすいというメリットにつながります。
一方で、転職や永住申請には都度の書類提出や審査が必要なため、専門家の支援を受けると安心です。制度理解と手続き面での支援体制の整備が、外国人職員の定着にも大きく関わってきます。
外国人介護職の活用事例と今後の展望

在留資格「介護」を活用した外国人材の受け入れは、すでに全国各地の介護施設で進んでおり、現場では戦力として活躍しています。一方で、言語や文化の壁、受け入れ体制の整備といった課題も残ります。ここでは実際の就労事例や施設側の声を紹介しつつ、今後の制度の展望についても考察します。
在留資格「介護」を取得した外国人の就労事例
在留資格「介護」で働く外国人の多くは、福祉系の日本語学校や専門学校を卒業後、介護福祉士国家資格を取得して就労しています。例えば、フィリピンやベトナム出身の職員が、デイサービスや特別養護老人ホームで以下のように活躍しています。
・ご利用者との丁寧なコミュニケーション
・排泄・入浴・食事などの身体介護
・チーム内での情報共有や記録作成
こうした職員の存在は、職場全体の多様性を高め、他のスタッフの刺激やモチベーション向上にも貢献しています。また、継続勤務によりリーダー的存在に育っている例も増えており、長期的な人材育成の観点でも効果が見られます。
受け入れ施設側の声と課題
実際に外国人介護職を受け入れている施設では、次のようなポジティブな評価が挙がっています。
積極的で素直な働きぶりに助けられている
離職率が低く、継続勤務が見込める
利用者が異文化に親しむ良い機会になった
一方で、受け入れに際しては以下のような課題も共有されています。
日本語の理解度に個人差があり、業務上の指示が伝わりづらい
宗教や食文化の違いへの配慮が必要
初期の生活サポートやメンタルケアが重要
これらの課題を乗り越えるためには、職場内の多文化共生に対する理解と体制整備がカギとなります。語学支援や相談窓口の設置など、施設全体での対応が求められています。
今後の制度改正や育成就労制度との関係
近年、外国人介護人材を取り巻く制度は変化の途上にあります。特に注目されているのが、技能実習制度に代わる新制度「育成就労制度」の導入です。これは、外国人を一時的な労働力としてではなく、将来の長期的な就労人材として育成する制度で、介護分野も対象に含まれる見込みです。
一方で、在留資格「介護」は国家資格取得者が対象であり、引き続き高度人材としての位置づけが維持されると考えられます。今後は、福祉系留学から国家資格取得、さらに在留資格「介護」への移行が、制度的にもよりスムーズになる可能性があります。
こうした制度改正により、外国人介護職の受け入れルートが多様化・柔軟化し、現場の人手不足解消に寄与することが期待されます。
まとめ
在留資格「介護」は、外国人が日本で安定して長期にわたり介護職として働くための重要な制度です。他の在留資格と比べて、キャリア形成や生活の安定につながりやすい特徴があり、介護現場の人手不足解消に向けた有効な選択肢となっています。
実際の就労事例からも分かるように、外国人介護職は利用者との信頼関係を築きながら、現場に新たな風を吹き込んでいます。一方で、言語や文化への配慮、制度理解、受け入れ体制の整備といった課題も存在します。
今後の制度改正や育成就労制度の導入を踏まえ、外国人材との共生に向けた取り組みはますます重要になります。採用を検討している施設は、制度の正確な理解とともに、共に働き成長できる環境づくりを目指すことが求められるでしょう。
外国人介護職の採用は、制度理解とサポート体制づくりが鍵です
在留資格「介護」は、長期的な雇用やキャリア形成を前提に、外国人介護人材を安定的に受け入れられる制度です。適切な支援体制と制度理解があれば、職場に新しい風を吹き込む存在として活躍が期待できます。
TSBケア・アカデミー では、特定技能をはじめとする外国人材の採用支援を行っており、制度の導入から実務までをトータルでサポートいたします。
外国人介護人材の受け入れを検討中の方は、ぜひお気軽に お問い合わせ ください。