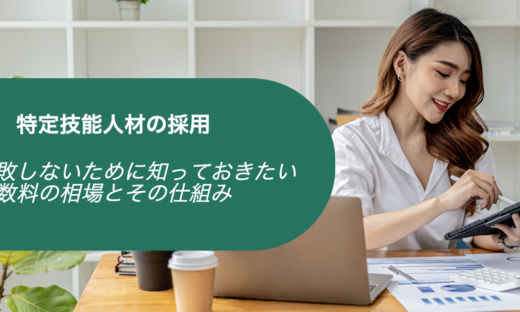【技能実習生 廃止】今後どうなる?代替制度「育成就労」と企業が取るべき対応策を解説

これまで外国人労働者の受け入れ制度として広く利用されてきた「技能実習制度」が、ついに廃止される方針となりました。
代わって新たに創設されるのが「育成就労制度」です。この制度変更は、単なる名称の変更ではなく、受け入れ企業にとっても実務面や人材戦略に大きな影響を及ぼすものです。
「これからも外国人材を受け入れたいが、何をどう見直せばいいのか分からない」「特定技能制度との違いや使い分けが気になる」といった疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、技能実習制度が廃止される背景から育成就労制度の概要、企業が取るべき対応策までをわかりやすく解説します。制度移行に戸惑うことなく、今後の外国人雇用に自信を持って臨むための第一歩として、ぜひご活用ください。
技能実習制度が廃止へ──背景と目的を正しく理解しよう
長らく外国人材の育成と労働力確保を担ってきた「技能実習制度」が、ついに廃止されることになりました。
これに代わって新たに導入される「育成就労制度」は、より実態に即した制度として注目されています。
本章では、制度の見直しに至った背景と、新制度に込められた目的について解説します。
なぜ技能実習制度は廃止されるのか?
技能実習制度はもともと、外国人に日本の技術を学んでもらい、母国の発展に役立てることを目的に1993年に創設されました。しかし、実際には深刻な人手不足を背景に、安価な労働力として外国人を雇用する“建前と実態の乖離”が問題視されるようになりました。
さらに、長時間労働・低賃金・パワハラ・失踪などの問題も相次ぎ、国内外から制度の持続性に疑問の声が高まりました。
法務省の有識者会議でも「実質的には労働力の確保が主目的」と明言され、制度の根本的な見直しが求められるようになったのです。こうした経緯を踏まえ、2023年には「育成就労制度」創設への方針が発表され、技能実習制度の廃止が正式に決まりました。
新制度「育成就労制度」が創設された目的とは?
育成就労制度の最大の目的は、「外国人を労働者として正しく受け入れ、継続的な人材育成と就労機会を両立させること」にあります。
従来のような“建前の研修制度”ではなく、最初から就労を前提とし、企業が計画的に育成しながら人材を確保できる制度として設計されています。
また、本人のキャリア形成にも重点を置いており、一定の条件を満たすことで「特定技能」などの在留資格へ移行することも可能になります。これにより、企業は単なる短期労働力ではなく、将来の戦力となる外国人を安定的に雇用する道が開かれるのです。
新たな制度「育成就労」とは?制度概要を押さえよう

「技能実習」に代わる新制度として注目される「育成就労制度」。この制度は、従来の問題点を改善しつつ、企業にとっても外国人にとっても実用的で持続可能な制度として設計されています。
本章では、その基本的な枠組みや、技能実習との違いについて整理していきましょう。
育成就労制度の基本的な仕組みと在留資格の位置づけ
育成就労制度は、「日本の職場で働きながら技能を身につける」ことを明確な目的とし、外国人が3年間の就労・育成期間を経て、より高度な在留資格(たとえば「特定技能」)にステップアップできる構造となっています。
この制度では、企業側に「育成計画の作成」や「段階的な教育」が求められ、ただ働かせるだけではなく、スキル習得とキャリア支援が義務づけられます。
また、送り出し機関の役割は縮小され、仲介コストの削減や労働者の自由度向上も期待されています。在留資格としては新たに「育成就労」という区分が創設され、出入国在留管理庁の管理のもとで制度運用される予定です。
技能実習との違いは?育成就労制度の特徴を比較
技能実習制度との大きな違いは、「制度の建前」と「実態」のギャップを埋める点にあります。技能実習が“国際貢献”を掲げていたのに対し、育成就労は“労働力としての就労”を明確に前提としています。
また、技能実習では転職が原則禁止でしたが、育成就労では一定条件のもとでの転職も認められ、人権侵害や不当な拘束のリスクが軽減されます。
さらに、企業には育成の進捗管理が求められ、外国人がスキルアップできる仕組みが制度内に組み込まれている点も大きな特徴です。
つまり、技能実習の「不透明な監理構造」や「閉鎖的な雇用環境」が問題だったのに対し、育成就労は“開かれた、透明性のある制度”として期待されています。
企業にとって何が変わる?実務・運用面のポイント
技能実習制度から育成就労制度への移行により、受け入れ企業側の対応にも大きな変化が求められます。ただ制度を“切り替える”だけではなく、受け入れの考え方や実務の体制そのものを見直す必要があります。
本章では、企業にとって特に重要な実務面での変化と対策を整理します。
受け入れ企業が準備すべき変更点とは?
育成就労制度では、企業は「育成計画」の作成と実施が義務となり、単なる労働力確保の枠を超えた“人材育成の担い手”としての責任を負うことになります。
具体的には、以下のような準備が求められます。
・業務ごとのスキル定義と段階的な育成内容の設計
・就労環境の整備(言語サポートや教育機会など)
・受け入れ体制の整備(指導担当者の配置、労務管理体制の強化)
また、監理団体に頼っていた実務の一部を、企業自らが担うケースも増えると予想されるため、制度理解と社内教育の徹底が重要です。
採用から受け入れ支援までの実務フローの見直し
育成就労制度では、採用から育成、評価、次の在留資格への移行支援に至るまで、企業側に一貫したフローの設計が求められます。従来のように、受け入れから現場配属までを監理団体任せにしていた体制では対応が難しくなります。
・採用時:職種ごとの育成計画を提示し、マッチングの透明性を高める
・配属後:定期的な面談や進捗確認により育成の質を担保
・在留期間終了時:育成成果の評価と、特定技能などへの移行サポート
このように、企業が主体的に関与する場面が増えるため、人事・現場・経営が連携した制度運用が不可欠になります。
「特定技能」との使い分けは?制度選択の判断材料に

育成就労制度と並んで存在する「特定技能制度」は、すでに多くの企業で導入されている在留資格の一つです。
両者には目的や仕組みに明確な違いがあるため、自社にとってどちらが適しているかを見極めることが重要です。ここでは、それぞれの制度の併用・移行の可能性と、判断のポイントを整理します。
特定技能制度との併用や移行の可能性
育成就労制度は「人材育成」に重きを置く一方、特定技能は「即戦力の確保」に焦点を当てています。そのため、育成就労で一定のスキルを習得した外国人が、特定技能1号や2号に移行する流れも想定されています。
併用のパターン:企業によっては、現場で即戦力を求める部署では特定技能、育成に時間をかけられる部署では育成就労を使う、といった併用も可能です。
制度間の移行:育成段階を経て、特定技能への移行を支援することで、長期的な人材確保にもつながります。このように、企業の戦略や現場の状況に応じて、柔軟に使い分けることがカギとなります。
自社に合うのはどちら?制度選びのポイント
自社にとって育成就労制度と特定技能制度のどちらが向いているかを判断するには、以下の観点から検討するのが効果的です。
人材ニーズの性質:即戦力が必要か、育成を前提に迎える余裕があるか
職場の教育体制:育成支援を行える体制が整っているか
定着支援への関心:長期的な雇用関係を築きたいか、短期の労働力確保が目的か
制度の選び方次第で、企業の将来の人材戦略も変わってきます。現場の声や将来の事業計画とも照らし合わせながら、最適な制度を選ぶことが重要です。
制度移行のスケジュールと今後の見通しを把握しよう
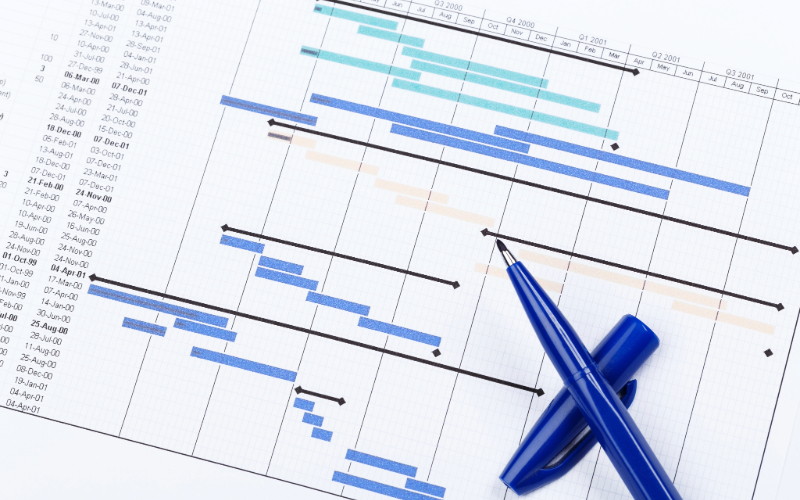
技能実習制度の廃止と育成就労制度の導入は、企業にとって重要な転換期となります。いつから、どのように制度が切り替わっていくのかを正しく理解することが、スムーズな受け入れと体制整備の第一歩です。
この章では、移行スケジュールと今後の制度動向を整理していきます。
技能実習から育成就労への移行時期と対応スケジュール
政府は、技能実習制度を段階的に廃止し、育成就労制度へと移行する方針を打ち出しています。施行は2027年を目途に完全移行が予定されており、それまでに新制度の法整備や準備が進められます。
現行制度との併存期間:育成就労制度が本格施行されるまでは、技能実習制度が一定期間継続されます。その間に受け入れ企業側は、必要な体制変更や情報収集を行うことが求められます。
実務的対応:既存の技能実習生の取り扱い、移行希望者への対応、新規受け入れ計画の見直しなど、順次対応すべきタスクが発生します。早めにスケジュールを把握し、移行期間を計画的に活用することが成功のカギとなります。
今後の制度改正や受け入れ枠の動向
制度移行にあわせて、受け入れ枠の見直しや関連法令の改正も段階的に行われる予定です。とくに注目されているのは、受け入れ対象業種の拡大や、育成期間中の支援体制に関する基準の強化です。
・業種別の対応差:一部の業種ではすでに特定技能制度への移行が進んでおり、今後は育成就労とのすみ分けが課題になります。
・外国人の定着促進策:制度設計の中には、日本語教育やキャリア支援の充実が盛り込まれる見込みで、これらが企業の採用活動にも影響を与える可能性があります。
制度の最新動向にアンテナを張り、今後の改正に柔軟に対応できる準備が不可欠です。
企業に求められる意識改革と持続可能な外国人雇用のあり方
育成就労制度は、単なる制度変更ではなく「外国人と共に働く社会づくり」の第一歩です。受け入れ企業には制度を“使う側”ではなく、“共に働き、育てる側”としての姿勢が求められています。この章では、今後の企業に必要な視点と実践ポイントを掘り下げます。
育成と共生を前提にした受け入れ体制をつくる
育成就労制度では、“育成”というキーワードが制度の中核を担っています。単なる労働力確保ではなく、職業能力の段階的な向上と安定雇用の実現が求められます。
・日本語や生活面の支援、職場内教育の整備
・外国人社員へのフィードバックの仕組みづくり
・差別や孤立を生まないコミュニケーション体制
といった「人を育てる視点」に立った取り組みが、これまで以上に評価されるようになります。
企業の社会的責任と持続可能な雇用の実現
制度の形だけ整えても、職場に馴染めず離職してしまうケースは後を絶ちません。今後は、外国人労働者のキャリア設計を視野に入れた受け入れが企業の信頼につながります。
・外国人が働きやすく、成長できる「場」をどう整えるか
・長く働きたいと思ってもらえる会社づくり
・地域や家族も含めた支援ネットワークの構築
など、企業の社会的責任(CSR)の一環として外国人雇用を捉えることが求められます。
よくある質問Q&Aで不安を解消しよう

制度移行に関する疑問や混乱を抱える企業担当者は少なくありません。ここでは、育成就労制度や技能実習の廃止に関連する、よくある疑問を取り上げてわかりやすく整理します。
今いる技能実習生はどうなる?制度移行後の扱いは?
現在受け入れている技能実習生は、経過措置としてそのまま在留を続けられる可能性があります。ただし、契約期間満了や更新タイミングに応じて、育成就労への移行が必要になるケースも。移行の可否や方法は制度施行後の詳細通知を注視しましょう。
育成就労と特定技能は同時に受け入れられる?
はい、可能です。ただし、それぞれ制度の目的と運用が異なるため、在留管理や支援体制、雇用契約の区分に注意が必要です。混同せず、制度別にしっかりと管理しましょう。
制度変更に伴う注意点とトラブル回避のヒント
新制度導入に伴う混乱や誤解を避けるためには、事前の準備と正しい理解が不可欠です。ここでは、よくあるつまずきポイントや見落としがちな点を整理し、円滑な対応のヒントを提示します。
旧制度の感覚で対応するとトラブルのもとに
技能実習制度は「技術移転」が名目でしたが、育成就労制度では「労働者としての受け入れ」が前提です。これまでの“建前と実態のギャップ”をそのまま引き継ごうとすると、法的・倫理的な問題につながる可能性もあるため注意が必要です。
支援計画や教育体制の不備が指摘されるリスク
育成就労制度では、日本語支援やキャリア形成支援が義務化される予定です。支援が形式的に終わっていた技能実習と異なり、企業の姿勢と実行力が問われます。登録支援機関との連携強化も視野に入れて準備を進めましょう。
まとめ:制度移行をチャンスに変え、持続可能な外国人雇用へ
技能実習制度の廃止と「育成就労制度」への移行は、企業にとって大きな変化である一方、人材確保の在り方を見直す絶好のタイミングでもあります。
これまでの制度が抱えていた課題を踏まえ、今後は“ただの労働力”としてではなく、“育成を前提とした人材”として外国人を受け入れる姿勢が求められます。
新制度の目的を正しく理解し、労務管理や支援体制を整えることで、企業の信頼性や採用力の向上にもつながります。また、今後も制度の見直しや運用変更がなされる可能性があるため、常に最新情報に目を配り、柔軟に対応できる体制づくりが重要です。
育成就労制度は、単なる制度移行ではなく、企業の外国人雇用をより持続可能なものへと発展させるためのチャンスなのです。
技能実習制度の見直しに、早めの対応をお考えの企業様へ
育成就労制度へのスムーズな移行や特定技能との使い分けについて、TSBケアアカデミーが実務レベルでサポートいたします。
制度変更に備えた準備は、お問い合わせからお気軽にご相談ください。