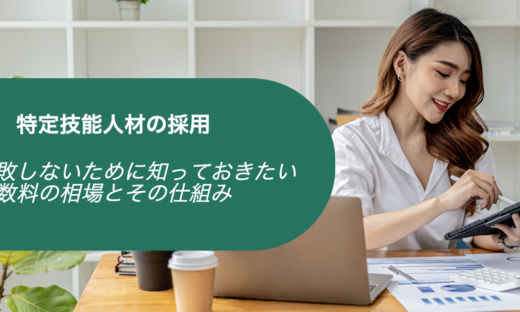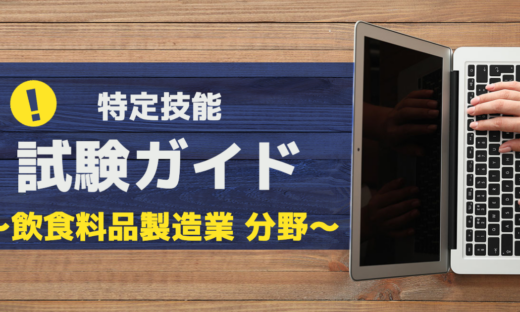技能実習から特定技能へ移行するには?手続き・要件・成功のポイントを徹底解説!

外国人材の受け入れ制度として長年利用されてきた「技能実習制度」が、大きな転換期を迎えています。制度の名の通り“実習”という建前に支えられてきた仕組みは、さまざまな問題や課題を抱え、現在はより実態に即した「特定技能制度」への移行が進められています。
「これから外国人材を受け入れたいが、どの制度を使えばいいのか分からない」「技能実習から特定技能へどう移行するの?」「制度の変更によって今後何に注意すべき?」――そんな不安や疑問を抱える企業の人事担当者や経営者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、技能実習から特定技能への移行ルートや条件、制度の違い、今後導入予定の「育成就労制度」までをわかりやすく解説。制度の変化をチャンスに変え、持続可能な外国人雇用につなげるためのポイントを一つひとつ整理していきます。
技能実習制度から特定技能制度への移行が進む背景

近年、日本における外国人労働者の受け入れ制度が大きく見直されつつあります。その中心にあるのが、「技能実習制度」から「特定技能制度」への移行です。
かつては「人材育成」という建前のもと、実質的な労働力として活用されてきた技能実習制度ですが、その構造的な課題が明らかになり、制度の根本的な見直しが求められるようになりました。
本章では、制度移行の背景となる問題点と、それに対する政府の方針について詳しく解説します。
技能実習制度における問題点と批判
技能実習制度は、1993年に「開発途上国への技術移転」を目的としてスタートしましたが、実際には建設業・農業・介護・製造業など、人手不足の業界での労働力確保の手段として機能してきました。そのため、以下のような問題が指摘されてきました。
人権侵害や不適切な労働環境:低賃金・長時間労働、不当な罰則や監禁、パスポートの取り上げなど、労働者の権利が侵害される事例が相次ぎました。
実習という名の労働:制度の名目は「実習」ですが、実態は単純労働であり、教育的な要素が薄くなっていたとの批判が根強くあります。
転職の自由がない:技能実習生は原則として受け入れ企業を変更できないため、劣悪な環境にあっても我慢せざるを得ない状況が生まれていました。
制度の不透明性:監理団体や送り出し機関による高額な手数料や、不明瞭な契約条件などが、制度の信頼性を損なう要因となっていました。
こうした構造的な問題により、国内外から制度改革の必要性が強く求められるようになったのです。
制度見直しの方向性と移行の目的
政府は、これらの問題を受けて「技能実習制度の廃止」と「特定技能制度への一本化・再編」を進める方針を固めました。移行の主な目的は以下の通りです。
・実態に即した制度設計:実習という名の労働ではなく、最初から「労働力の受け入れ」を前提とした在留資格に一本化することで、制度の透明性と信頼性を高めます。
・労働者の権利保護:転職の自由や、生活支援、相談体制の整備など、外国人労働者が日本で安心して働ける環境の整備が進められています。
・即戦力人材の確保:特定技能制度は、技能実習と異なり、一定のスキルと日本語力を有する即戦力の人材を受け入れる制度として設計されており、人手不足の業界にとっても利点があります。
技能実習から特定技能への主な移行ルートと要件

技能実習制度から特定技能制度へとスムーズに移行できるルートが用意されていることは、受け入れ企業・外国人労働者双方にとって大きなメリットです。特に、技能実習2号を修了した人材は、一定の条件を満たせば特定技能1号に移行できる特例が設けられています。
本章では、実際にどのような要件を満たせば移行できるのか、また、試験や日本語能力に関する緩和措置について解説します。
技能実習2号修了者が特定技能に移行する条件
技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能1号へ移行する際に、通常必要となる技能試験・日本語試験の一部が免除されるという特例措置があります。これは制度の連続性と実習生のキャリア形成を重視した取り組みです。
移行のための主な条件は以下の通りです。
・対象業種が一致していること
技能実習で従事していた業種と、特定技能での就業予定業種が一致または関連していることが必要です(例:食品製造業、建設、介護など)。
・技能実習2号を良好に修了していること
「良好な修了」とは、実習期間をきちんと終え、実習内容や出勤状況に問題がないと評価されている場合を指します。
・引き続き在留資格を変更できること
在留期限が切れる前に申請を行い、必要書類が整っていることが求められます。
この制度設計により、技能実習で得た知識や経験を活かして日本国内で中長期的に活躍することが可能となっています。
試験免除と日本語要件の緩和について
特定技能1号への移行時には、原則として「技能評価試験」と「日本語能力試験(JLPT N4以上またはJFT-Basic)」の合格が求められますが、技能実習2号を修了している場合、これらの試験が免除される特例があります。
免除の対象となる内容は以下の通りです。
・技能評価試験の免除
同一業種で実習2号を修了した場合、その業務に必要な技能が既に証明されているとみなされ、技能試験が免除されます。
・日本語要件の緩和
一部の業種では、実習時の研修や業務経験を通じて日本語能力が身についていると判断され、あらためての語学試験が不要とされるケースもあります(※ただし介護分野など、一部の業種では日本語要件が厳格に求められる)。
このような特例措置によって、技能実習制度と特定技能制度との間にスムーズな移行ルートが形成され、制度の一本化に向けた実務的な基盤が整えられつつあります。
移行後の就労条件と制度の違いを把握しよう

技能実習制度から特定技能制度へ移行した後は、在留資格の性質や就労条件、転職の可否などが大きく変わります。受け入れ企業にとっても、これまでとは異なる管理や支援体制が求められるため、制度の違いをしっかりと把握することが重要です。
本章では、特定技能1号への移行後に注意すべき主な制度上の違いについて解説します。
在留資格の違いと在留期間の延長可能性
技能実習制度は“人材育成”を目的とした制度であり、在留期間も最長5年で、原則として延長はできませんでした。一方、特定技能1号は“労働力の確保”を目的としており、実質的な就労資格として位置づけられています。
特定技能1号の在留期間に関する主な特徴は以下のとおりです。
1回の許可期間は最大1年、更新により最長5年間の在留が可能
分野によっては、特定技能2号への移行によって更なる延長・永住への道も開かれている
このように、在留資格としての性格が大きく異なるため、企業側も外国人材の中長期的な戦力化を見据えた計画が必要になります。
転職の可否と企業側の対応範囲
技能実習制度では、実習先を変更することは原則として認められておらず、転職は非常に制限されていました。しかし、特定技能1号では、一定の条件下で同一分野内での転職が認められているという大きな違いがあります。
特定技能における転職の特徴:
・同一分野・同一業務であれば転職が可能
・転職の際は、登録支援機関や新しい受け入れ企業の体制整備が必要
・適切な引継ぎ・届出が行われないと不法就労とみなされるリスクもある
企業側としては、受け入れた外国人が他社に移る可能性があることを想定し、より良い職場環境や支援体制を整えることが重要になります。また、外国人本人が安心して働き続けられるよう、労務管理やキャリア相談の充実も求められます。
移行時に企業が注意すべきポイント

技能実習から特定技能への移行をスムーズに進めるためには、企業側にも多くの準備と対応が求められます。制度変更に伴う手続きや支援体制の見直しはもちろん、労働条件の再確認やトラブル防止策も重要です。
この章では、企業が移行時に押さえておくべき実務面のポイントを解説します。
必要な支援体制と書類整備
特定技能1号で外国人を雇用する企業は、登録支援機関と連携するか、自社で支援体制を構築する義務があります。これは、技能実習とは異なり、より“労働者としての生活支援”を重視した制度設計のためです。
企業が整備すべき主な支援項目:
・生活ガイダンスの実施(来日前・直後)
・日本語学習機会の提供
・住居確保支援や生活相談対応
・母国語での相談体制の整備
また、雇用契約書や支援計画書など、必要な書類を日本語と母国語の両方で準備する必要がある点も技能実習制度との違いです。不備があると入管審査で不許可となる場合もあるため、提出書類の内容と整合性を事前に十分確認しましょう。
労働条件・待遇面での留意点
特定技能では、外国人労働者に対して日本人と同等以上の報酬・労働条件を保証する義務があります。これは「教育・研修」を目的とする技能実習制度よりも、より強い“労働者保護”が意識された制度になっているためです。
企業が注意すべきポイント:
・最低賃金を下回らない給与設定(地域・業種ごとの基準に要注意)
・労働時間、残業、休暇の管理を日本人と同等に行う
・労働条件通知書や就業規則の整備と説明義務
・社会保険・労働保険への適切な加入
不適切な待遇や契約条件があると、ビザの不許可や在留資格取消のリスクがあるだけでなく、外国人材の離職・転職の引き金にもなりかねません。法令順守と職場環境の見直しを並行して行うことが、安定した雇用に繋がります。
育成就労制度への移行と今後の展望

技能実習制度は、国際的な批判や国内の課題を受けて、政府によって廃止の方針が決定され、新たに「育成就労制度」が創設されることになりました。これは単なる名称変更ではなく、制度の根幹を見直す大改革です。
ここでは、育成就労制度の概要と、技能実習・特定技能との違いや関係性について整理しておきましょう。
育成就労制度の導入予定と概要
2027年度までに本格導入が予定されている「育成就労制度」は、技能実習制度を廃止し、その代替制度として設計された新しい外国人雇用制度です。
従来の「国際貢献・技能移転」ではなく、人材確保と人材育成の両立を目的としており、より現実的で持続可能な外国人労働者の受け入れ制度となることが期待されています。
育成就労制度の主なポイント:
・受け入れ目的は「人材育成」と「労働力確保」
・分野ごとの制度運用を柔軟化
・一定条件を満たせば転職が可能
・最長5年間の在留期間を確保
・特定技能への移行を前提とした仕組み
特に大きな特徴は、転職が一定の条件で認められる点です。これにより、労働者の人権保護やキャリア形成が重視され、ブラック企業への依存状態を改善する狙いがあります。
技能実習・特定技能・育成就労の関係と整理
これまでの外国人雇用制度では、「技能実習 → 特定技能」への移行が基本的なルートとされてきましたが、今後は「育成就労 → 特定技能」へと切り替わる見込みです。
つまり、育成就労制度は特定技能制度と連携しながら、外国人労働者の段階的な就労キャリアを支える仕組みとして整備されます。
| 比較項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 | 特定技能制度 |
|---|---|---|---|
| 制度目的 | 技能移転 | 人材育成・労働力確保 | 即戦力としての雇用 |
| 転職の可否 | 原則不可 | 条件付きで可 | 条件付きで可 |
| 在留期間 | 最長5年 | 最長5年(予定) | 1号:最長5年、2号:無期限 |
| 制度後の移行先 | 特定技能 | 特定技能 | 2号または永住への可能性 |
このように、育成就労制度は「技能実習の欠点を補い、特定技能へと繋げる橋渡し役」として設計されており、今後の外国人雇用政策の中心的な制度となっていくと予想されます。企業にとっても制度の理解と早期対応が求められる局面です。
まとめ:制度の変化を正しく理解し、持続可能な外国人雇用を

技能実習制度から特定技能制度、そして今後の育成就労制度へと、日本の外国人雇用制度は大きな転換期を迎えています。
これらの制度は、それぞれ目的や在留要件、雇用形態などに明確な違いがあり、企業が適切に制度を理解し、柔軟に対応していくことが求められます。
特に技能実習から特定技能への移行は、企業と外国人双方にとってチャンスである一方で、移行条件や支援体制、労働条件の整備といった現場対応が鍵となります。
また、育成就労制度の導入に備え、長期的視点での人材育成や定着支援の仕組みを整えておくことが、持続可能な外国人雇用につながります。
制度の変化は不安要素にもなり得ますが、正しく理解し、準備を進めれば、企業の人手不足解消や職場の多様性推進にもつながる大きな力になります。
今後も制度動向を注視し、変化に強い受け入れ体制を構築していきましょう。
外国人雇用の制度は複雑で、法改正や運用変更への対応も簡単ではありません。自社に合った制度選びや、円滑な移行・定着支援には専門的な知識と経験が不可欠です。
TSBケア・アカデミーでは、特定技能を中心とした外国人材の受け入れ支援を専門に行い、制度選びから採用後の定着支援まで一貫してサポートしています。
「自社に合った制度を知りたい」「移行手続きの進め方を相談したい」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせページからご相談ください。制度の変化に強い体制づくりを、私たちが全力でお手伝いします。