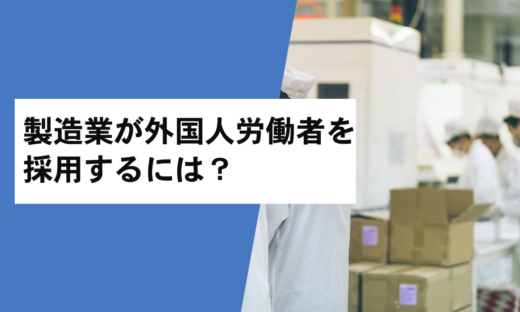特定技能「漁業」徹底ガイド!外国人雇用の流れと成功のポイント

日本の漁業は、高齢化や若手の担い手不足により深刻な人手不足の問題を抱えています。
そこで注目されているのが「特定技能」制度です。特定技能「漁業」は、一定の技能と日本語能力を持つ外国人労働者を受け入れることで、漁業の安定的な運営を支援する制度として設けられました。
しかし、外国人雇用には制度の理解や適切な受け入れ体制の整備が必要不可欠です。
本記事では、特定技能「漁業」の概要や取得条件、具体的な業務内容、採用プロセス、雇用形態、労働条件などを詳しく解説します。
外国人雇用を検討している漁業関係者にとって、実際の導入に役立つ情報を提供し、成功のポイントをわかりやすくまとめています。
特定技能「漁業」制度を正しく理解し、効果的に活用することで、人手不足の解消と安定した事業運営を実現しましょう。
特定技能「漁業」とは?概要と制度の目的

日本の水産業は、近年の労働力不足が深刻化しており、特に沿岸漁業や養殖業では高齢化が進み、若手人材の確保が大きな課題となっています。この状況を打開するために導入されたのが「特定技能」制度です。
特定技能「漁業」は、外国人労働者が日本の漁業・養殖業に従事するための在留資格であり、実際の現場で一定の専門知識や技能を持つ人材が働くことを目的としています。
この制度により、漁業関係者は即戦力となる外国人を雇用できるようになり、人手不足の解消や生産性向上が期待されています。
特定技能制度の背景と漁業分野の現状
日本の漁業は、近年深刻な人手不足に直面しています。特に沿岸漁業や養殖業では、担い手の高齢化が進み、若年層の漁業従事者が減少しているのが現状です。
このままでは漁業の生産量が低下し、地域の水産業の存続そのものが危ぶまれる状況にあります。こうした課題を解決するため、日本政府は2019年に「特定技能」制度を創設しました。
この制度の目的は、一定の専門知識や技能を持つ外国人労働者を受け入れ、即戦力として日本の産業を支えることです。
漁業分野においても、外国人労働者を積極的に活用することで、慢性的な人手不足の解消を図ることが期待されています。
特定技能「漁業」の特徴と他業種との違い
特定技能「漁業」は、他の特定技能分野と比べていくつかの特徴的な点があります。
特に、業務の特殊性、就労環境、求められるスキルといった側面において、他業種とは異なる点が多く見られます。
1. 海上での作業が中心となる特殊な業務
漁業分野の特定技能では、漁船に乗り込み沖合や遠洋で操業する「漁業」と、陸上で水産動植物の養殖や管理を行う「養殖業」の2つの業務があります。
特に漁業の現場では長期間にわたる洋上での作業が求められ、天候や海の状況に大きく左右される環境での労働となる点が、他業種とは異なります。
2. 体力や適応力が求められる労働環境
特定技能「漁業」では、早朝からの作業や長時間労働が発生することが多く、また、天候の影響でスケジュールが変動しやすいのが特徴です。
そのため、一定の体力や、変則的な労働環境に適応できる柔軟性が求められます。
3. 独特の技術や経験が必要になる
漁業分野では、網を仕掛ける技術や、魚の種類ごとの処理方法、船上での作業ルールなど、専門的な知識や経験が必要になります。
他業種と比べても、実際の現場で経験を積みながら技術を習得するケースが多い点が特徴です。また、危険を伴う作業もあるため、安全管理の知識も重要視されます。
このように、特定技能「漁業」は他の業種に比べて過酷な環境や専門的な技能が求められる一方で、経験を積めば高度な技術を習得できる分野でもあります。
特定技能「漁業」で従事できる業務内容
特定技能「漁業」では、漁業と養殖業の2つの業務分野に分かれており、それぞれ異なる作業内容が求められます。
漁業では、海上での操業や漁獲物の処理が主な業務となり、一方の養殖業では、魚や貝類の育成管理や水質調整などが中心となります。
これらの業務は、日本の水産業の安定的な発展に欠かせないものであり、経験を積むことで専門的なスキルを身につけることができます。
漁業での主な業務と関連業務
特定技能「漁業」における漁業分野では、主に海上での操業や漁獲物の処理などが求められます。具体的には、以下のような業務が含まれます。
1. 漁獲作業
漁船に乗船し、漁網や釣り具を使用して魚介類を捕獲する業務です。対象となる漁法には、底引き網漁、延縄漁、定置網漁などがあり、漁業の種類によって作業内容が異なります。
2. 漁獲物の処理
水揚げされた魚介類の選別、サイズごとの仕分け、鮮度保持のための冷却作業などを行います。また、衛生管理を徹底し、市場への出荷準備を整えることも重要な業務のひとつです。
3. 船舶の管理・メンテナンス
漁業では、船の安全な運航が不可欠です。そのため、エンジンの点検、漁具の修理、清掃作業などのメンテナンス業務も行います。
特に、荒天時に備えた準備や、長時間の航海に耐えるための船内設備の管理が求められます。
このように、漁業分野では海上での業務が中心となりますが、漁獲後の処理や船の管理など、幅広い関連業務が含まれます。
養殖業での主な業務と関連業務
特定技能「漁業」では、養殖業も対象となっており、主に魚介類や海藻の生産に関わる業務を担当します。
海上や陸上の養殖施設で行われる業務には、以下のようなものがあります。
1. 魚介類の育成・管理
養殖では、魚や貝類の**餌やり、健康管理、水質チェックが重要な業務となります。適切な水温や酸素濃度を維持しながら、成長段階に応じたケアを行い、病気の予防や治療を徹底します。
2. 収穫・選別・出荷準備
一定のサイズまで育った魚介類を収穫し、選別、計量、梱包する業務です。市場のニーズに応じて、品質管理を徹底しながら適切な形で出荷準備を行います。
3. 養殖設備の管理・メンテナンス
養殖場の設備は常に適切な状態を保つ必要があります。生簀(いけす)や網の清掃・修理、給餌装置やポンプの点検・交換などの作業が含まれます。また、台風や赤潮などの自然災害に備えた対策も重要です。
4. 繁殖・種苗生産
一部の養殖場では、親魚から卵を採取し、稚魚や稚貝を育てる種苗生産も行います。人工ふ化や飼育技術が求められるため、専門的な知識が必要になります。
このように、養殖業では魚や貝類を計画的に育成するための管理業務が中心となります。次のセクションでは、漁業と養殖業に共通する業務や、それぞれの違いについて詳しく解説します。
特定技能2号で可能な業務と1号との違い
特定技能制度には「1号」と「2号」があり、特定技能2号はより高度な技能や経験を持つ外国人が対象となります。
漁業分野においても、特定技能2号に移行することで、より専門的な業務に従事することが可能になります。ここでは、特定技能1号との違いや、2号で可能な業務について詳しく解説します。
1. 特定技能1号と2号の違い
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 在留期間 | 1年・6ヶ月・4ヶ月ごとの更新(最長5年) | 無期限(定期更新あり) |
| 家族の帯同 | 原則不可 | 配偶者・子どもの帯同可能 |
| 必要な技能水準 | 基本的な業務ができるレベル | 高度な技術・管理能力が求められる |
| 業務範囲 | 定められた作業を実施 | 指導・管理業務も含む |
特定技能2号は、一定の経験と技能を持ち、現場のリーダー的な役割を担える人材が対象となります。そのため、単純な作業だけでなく、より高度な業務への従事が可能です。
2. 特定技能2号で可能な業務
特定技能2号では、1号よりも高度な管理業務や専門作業が求められます。
– 漁業の計画・指導(漁獲計画の立案、労働者指導)
– 漁獲・養殖技術の向上(効率的な漁法、水産資源管理)
– 船舶・設備の管理(船の操縦補助、設備メンテナンス)
– 品質管理・市場対応(漁獲物の品質管理、販売調整)
2号に移行すると、単なる作業員ではなく、**専門性を持つ管理者**としての役割が期待されます。
特定技能「漁業」の雇用形態と受け入れ要件

特定技能「漁業」分野で外国人を雇用する際には、雇用形態の選択や受け入れ機関としての要件を正しく理解することが重要です。
雇用形態には直接雇用と派遣雇用の2種類があり、それぞれの特性を踏まえた上で適切な方法を選ぶ必要があります。
また、外国人労働者を受け入れる事業者は、法令順守や適正な労働環境の提供が求められます。
受け入れ要件を満たしていないと特定技能外国人の雇用が認められないため、制度のルールを理解し、適切な準備を進めることが不可欠です。
直接雇用と派遣雇用の違い
特定技能「漁業」の雇用形態には直接雇用と派遣雇用があり、それぞれに特徴があります。
直接雇用とは?
事業者が外国人労働者と直接契約を結ぶ形態。
メリット
– 労働者の教育・指導がしやすい
– 定着率が高まりやすい
– 仲介手数料がかからない
デメリット
– 在留資格申請や生活支援の負担がある
– 突発的な人員確保が難しい
派遣雇用とは?
派遣会社が雇用し、事業者へ労働者を派遣する形態。
メリット
– 採用の手間が省ける
– 短期雇用にも対応しやすい
– 在留資格の手続きを派遣会社が代行
デメリット
– 派遣手数料が発生しコスト増
– 労働者の定着が難しい
どちらを選ぶべきか?
長期雇用なら直接雇用、短期確保なら派遣雇用が適しています。特定技能1号の場合、登録支援機関の活用が必須なので、その点も考慮が必要です。
受け入れ機関が満たすべき要件
外国人を雇用する事業者は、法令を遵守し、適切な雇用環境を整えることが求められます。
1. 法令順守と適正な雇用管理
– 最低賃金や労働基準法を守る
– 社会保険・労働保険への加入
– 過去5年以内に重大な法令違反がないこと
2. 安定した経営基盤
– 事業の継続性があること(直近の財務状況も審査対象)
– 倒産リスクが低いこと
3. 外国人の生活支援
– 居住環境や生活サポートの提供
– 日本語学習の支援
受け入れ機関が要件を満たさない場合、特定技能外国人の雇用が認められないため、事前準備が不可欠です。
漁業特定技能協議会への加入義務とその役割
1. 漁業特定技能協議会とは?
漁業特定技能協議会は、特定技能制度の適正な運用を目的として、農林水産省が関与する形で設立された組織です。特定技能外国人を受け入れる全ての事業者が加入し、**定期的な報告義務や情報共有を通じて、外国人雇用の適正化を推進**します。
主な目的
– 外国人労働者が適正な労働環境で働けるよう監視・指導
– 受け入れ事業者間の情報共有と連携強化
– 技能向上や日本語教育の支援体制を整備
– 不正行為や違反の防止
2. 加入義務の詳細
特定技能「漁業」分野で外国人を雇用する企業は、特定技能外国人の雇用開始前に協議会へ加入しなければなりません。加入しない場合、特定技能外国人の受け入れが認められないため、必ず手続きを行う必要があります。
加入の流れ
1. 協議会へ加入申請(指定の書類を提出)
2. 承認後、定期的な報告義務が発生(雇用状況、労働環境の維持など)
3. 協議会の指導に従い、適正な運営を継続
3. 漁業特定技能協議会の役割
協議会は、特定技能外国人を雇用する企業に対し、定期的な監査や指導を行い、問題の早期発見と是正を促す役割を担っています。
具体的な役割
– 定期報告の管理:企業からの報告を集約し、政府機関へ提出
– 労働環境の監査:受け入れ企業の実態調査を行い、不適切な雇用がないか確認
– 研修や情報提供:外国人雇用に関する勉強会や、日本語教育支援の提供
– 問題発生時の対応支援:外国人労働者と事業者間のトラブル対応
4. 加入のメリットと注意点
メリット
– 適正な雇用管理ができる:協議会のガイドラインに従うことで、労働基準法違反などのリスクを軽減
– 情報共有ができる:他の事業者と外国人雇用のノウハウを共有し、業界全体の質を向上
– 監査・指導が受けられる:法令遵守のサポートを受けられるため、安心して雇用できる
注意点
– 加入しないと外国人労働者の雇用ができない
– 定期報告の義務を怠ると、改善指導や罰則の対象になる
– 協議会費用や手続きの負担が発生する
特定技能「漁業」分野で外国人を雇用するためには、漁業特定技能協議会への加入が必須です。この協議会を通じて、適正な雇用管理を行い、外国人労働者の権利を守ることが求められます。
加入しないと雇用が認められないため、事前に手続きを行い、定期的な報告義務を遵守することが重要です。
特定技能1号・2号の取得条件と試験概要
特定技能「漁業」には、特定技能1号と特定技能2号の2つの区分があり、それぞれ取得条件や試験内容が異なります。
特定技能1号は、基本的な漁業技能と日本語能力を証明する試験に合格することで取得できるのに対し、特定技能2号は、より高度な技能を持ち、実務経験を積んだ外国人が対象となります。本項では、それぞれの取得条件と試験概要について詳しく解説します。
特定技能1号・2号の取得条件と試験概要
特定技能1号の取得条件と試験概要
特定技能1号を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。
– 技能試験の合格
特定技能「漁業」1号評価試験に合格することが必須です。この試験では、漁業または養殖業における基本的な知識や技術の習得度が問われます。
– 日本語能力試験の合格
日本語能力試験(JLPT)N4以上、またはJFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)に合格することが求められます。
– 年齢制限なし
特定技能1号には年齢制限はなく、一定の技能と日本語能力があれば取得可能です。
– 実務経験不要
実務経験は必須ではなく、試験合格により取得できます。
特定技能2号の取得条件と試験概要
特定技能2号は、特定技能1号よりも高度な技能が求められ、取得には以下の条件を満たす必要があります。
– 技能試験の合格
特定技能2号では、漁業または養殖業に関する**熟練した技術**を有することが条件であり、実技試験などを通じて評価されます。
– 日本語能力試験の要件なし
特定技能2号には日本語試験の要件はなく、技術の習得が重視されます。
– 実務経験の要件
一定期間の実務経験が求められます。具体的には、特定技能1号としての経験を経た後に特定技能2号へ移行する形が一般的です。
– 在留期間の更新が可能
特定技能1号は最長5年の在留期間に制限がありますが、特定技能2号は更新が可能で、事実上の永続的な就労が認められます。
特定技能2号を取得することで、長期的に日本の漁業分野で働くことが可能となり家族の帯同も認められるなど、より安定した雇用環境が整います。
特定技能「漁業」の採用プロセスと必要な手続き
特定技能「漁業」の外国人を採用するには、制度の要件を満たし、適切な手続きを進める必要があります。企業側は、受け入れ体制を整えたうえで、採用から在留資格の取得、入国後のフォローまで一連の流れを把握することが重要です。
日本国内在住外国人を採用する流れ
日本国内にすでに在留している外国人(技能実習修了者など)を特定技能「漁業」として採用する場合、比較的スムーズに手続きを進められます。主な流れは以下のとおりです。
1. 候補者の選定:技能実習修了者や留学生など、特定技能1号の条件を満たす外国人を選定。
2. 雇用契約の締結:労働条件を明記した契約を結ぶ(日本人と同等以上の待遇が必要)。
3. 在留資格の変更申請:出入国在留管理庁へ「特定技能1号」への在留資格変更を申請。
4. 審査・許可取得:許可が下りた後、特定技能としての就労が可能に。
海外からの採用フローと手続きのポイント
海外から新たに特定技能外国人を採用する場合、渡航前後の手続きが必要になります。
1. 候補者の選定・試験合格:特定技能評価試験と日本語試験に合格した人材を選定。
2. 雇用契約の締結:受け入れ企業が契約を交わし、特定技能の条件を満たすことを確認。
3. 在留資格認定証明書の申請:企業が出入国在留管理庁へ申請し、証明書を取得。
4. ビザ申請・入国:現地の日本大使館・領事館でビザを取得し、日本へ入国。
5. 入国後の手続き:住民登録や社会保険加入、生活支援などを実施。
採用後のフォローと義務的支援内容
特定技能外国人を雇用した後は、円滑な就労と生活を支援するため、企業に支援義務があります。
– 生活オリエンテーション:労働環境や生活ルールについて説明。
– 相談窓口の設置:労働条件や生活上の問題に対応。
– 日本語学習支援:職場での円滑なコミュニケーションをサポート。
– 転職支援(特定技能1号のみ):やむを得ない事情で転職する場合のサポート。
適切なフォローを行うことで、特定技能外国人の定着率を高め、安定した雇用につなげることができます。
特定技能「漁業」の給与・労働条件と転職の可否

特定技能「漁業」分野で外国人を雇用する際、企業は適切な給与水準や労働条件を保証する必要があります。特に、日本人労働者と同等以上の待遇が義務付けられており、労働環境の整備も求められます。
また、転職についても特定の条件下で可能ですが、手続きを適切に行うことが重要です。本章では、給与・労働条件の基本ルールと、転職の可否について解説します。
日本人との同等以上の給与基準
特定技能「漁業」で働く外国人の給与は、日本人労働者と同等以上であることが義務付けられています。
これは最低賃金以上であることはもちろん、同じ業務に従事する日本人と比較して不当に低い待遇にならないようにするための規定です。基本給のほか、残業手当や各種手当も同様の基準で支給される必要があります。
転職が可能な条件と注意点
特定技能1号は、同じ業種内であれば転職が可能ですが、転職先の企業も特定技能の受け入れ要件を満たしている必要があります。
一方、特定技能2号は転職や更新の制限がなく、長期的な就労が可能です。
転職時には以下の点に注意が必要です。
・転職後も特定技能の条件を満たす必要がある
・在留資格の変更手続きが必要
・受け入れ企業のサポートが必要な場合がある
・適切な手続きを行うことで、安定したキャリア形成が可能となります。
まとめ
特定技能「漁業」制度は、日本の漁業分野における深刻な人手不足を補うために設けられた制度であり、外国人労働者を受け入れることで漁業の持続的な発展を支える役割を果たします。
本記事では、特定技能「漁業」の制度概要、対象となる業務内容、雇用形態、取得条件、採用プロセス、給与・労働条件について詳しく解説しました。
特定技能1号では、一定の技能試験と日本語能力が求められ、特定技能2号へ移行することで、より高度な業務への従事や在留期間の更新が可能になります。
また、受け入れ機関は適切なサポート体制を整え、漁業特定技能協議会への加入が義務付けられるなど、外国人労働者が安心して働ける環境づくりが求められます。
今後、特定技能「漁業」を活用した外国人雇用を検討する事業者は、制度の詳細を正しく理解し、適切な採用・雇用管理を行うことが重要です。
特定技能制度を有効に活用することで、外国人労働者とともに持続可能な漁業経営を目指しましょう。
外国人雇用に関するご相談はTSBケア・アカデミーへ
特定技能「漁業」制度の導入や運用に関して、具体的なサポートをご希望の方は、TSBケア・アカデミーの公式サイトをご覧ください。
制度の活用方法や、漁業分野での採用実績に基づいたノウハウをご提供しています。
導入をご検討中の方や、ご不明な点がある場合は、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
制度の初歩から採用後のサポートまで、丁寧に対応いたします。