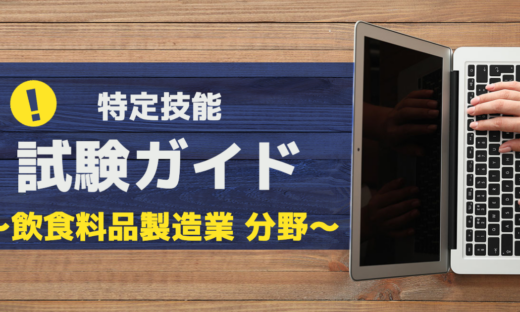特定技能で有料老人ホームの人手不足解消!採用手順と成功のポイント

日本の有料老人ホームでは、慢性的な人材不足が深刻化しており、介護職員の確保が大きな課題となっています。こうした状況の中、即戦力となる外国人材を受け入れる手段として「特定技能」制度が注目されています。
本記事では、特定技能外国人の採用方法や手続き、雇用のメリットについて詳しく解説し、有料老人ホームの運営者や人事担当者がスムーズに導入できるようサポートします。
特定技能「有料老人ホーム」とは?

日本の有料老人ホームでは、深刻な人材不足が続いており、安定した介護サービスの提供が課題となっています。その解決策の一つとして注目されているのが「特定技能」制度です。特定技能「介護」の概要と、有料老人ホームにおける適用範囲を整理し、なぜこの制度が注目されているのかを解説します。
特定技能「介護」とは?
特定技能「介護」では、一定の介護スキルと日本語能力を持つ外国人が、有料老人ホームや特別養護老人ホームなどの施設で働くことが可能です。従来の技能実習制度と異なり、労働者として正式に雇用されるため、長期的な戦力として期待されています。
有料老人ホームにおける適用範囲
特定技能「介護」を活用できる有料老人ホームは、介護サービスを提供する施設に限られます。有料老人ホームには「介護付き」「住宅型」「健康型」の3種類がありますが、特定技能の外国人を雇用できるのは 「介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)」 に限定されています。
・特定技能の適用対象となる施設
介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設)
施設内で介護職員が直接、入居者に対して介護サービスを提供
食事・入浴・排泄介助などの身体介護業務が発生
・適用対象外の施設
住宅型有料老人ホーム(外部の訪問介護事業者がサービスを提供)
健康型有料老人ホーム(基本的に介護サービスを提供しない)
なぜ特定技能が有料老人ホームで注目されているのか
日本の高齢化が進む中、有料老人ホームの需要は年々増加しています。しかし、それに比例して介護職員の不足が深刻化しており、多くの施設が人材確保に苦慮しています。こうした背景から、特定技能「介護」制度を活用し、外国人労働者を積極的に受け入れる動きが広がっています。
1. 介護人材不足の深刻化
厚生労働省の推計によると、2025年度には約32万人の介護人材が不足する とされています。特に有料老人ホームは、介護報酬の関係で人材確保が難しく、離職率の高さも課題となっています。日本人のみで人材を確保するのは限界に近づいており、外国人介護士の活用が急務 となっています。
2. 特定技能なら即戦力の人材を確保できる
特定技能「介護」は、技能実習制度とは異なり、即戦力となる人材を確保できる点が最大のメリット です。技能実習生は教育・訓練の要素が強いのに対し、特定技能は 日本語能力や介護技術をすでに習得している人材 が対象となるため、入社後すぐに現場での業務を任せることができます。
3. 長期間の安定雇用が可能
特定技能「介護」の在留資格は、最長5年間の就労が可能 です。また、介護福祉士資格を取得すれば、在留資格「介護」に切り替えることができ、長期間の雇用継続も可能となります。これにより、有料老人ホームの人材不足解消だけでなく、長期的な人材育成の選択肢 も広がります。
特定技能外国人の採用要件と受け入れ条件
特定技能「介護」を活用して外国人を採用するには、施設側が満たすべき条件や、採用する外国人に求められる基準があります。
受け入れ可能な有料老人ホームの条件
特定技能「介護」で外国人を受け入れられる有料老人ホームには、いくつかの条件があります。すべての有料老人ホームが対象となるわけではなく、施設の種類や提供するサービスによって受け入れ可否が異なります。
1. 介護サービスを提供する施設が対象
特定技能「介護」の対象となるのは、介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護) のみです。この施設では、入居者に対して日常的な介護サービスを提供しており、特定技能外国人が業務に従事することが認められています。
2. 施設の運営体制や法令遵守が求められる
特定技能の外国人を受け入れるには、施設側が適切な雇用管理体制を整え、労働法や社会保険に関する法令を遵守していること が求められます。また、特定技能協議会への加入も義務付けられており、適正な受け入れが可能な施設のみが対象となります。
事業者側の要件
特定技能外国人を受け入れる事業者は、以下の条件を満たす必要があります。
・労働関係法令や社会保険法令を遵守していること
・特定技能協議会に加入すること(義務)
・雇用契約を継続して履行できる経営基盤を持つこと
・外国人労働者に対し、適切な生活・就労支援を行うこと
採用する外国人の条件
① 介護技能評価試験・日本語試験の合格者
・特定技能「介護」の在留資格を取得するためには、次の2つの試験に合格することが必須です。
・介護技能評価試験:介護に関する基本的な知識や技術を確認する試験
・日本語試験:以下のいずれかの試験で一定の基準を満たすこと
・日本語能力試験(JLPT)N4以上
・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2レベル以上
・介護日本語評価試験(介護現場で必要な日本語の理解度を確認)
② 技能実習2号を修了した外国人
・技能実習2号(介護分野)を修了した外国人は、試験を受けることなく特定技能「介護」に移行可能です。
・技能実習生として3年以上の実務経験を積んでいるため、即戦力として活躍できる人材が多いのが特徴です。
③ 介護福祉士養成施設を卒業した外国人
・日本国内の介護福祉士養成施設を卒業した外国人も、特定技能「介護」の要件を満たしています。さらに、介護福祉士国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更でき、長期的な雇用が可能になります。
④ EPA(経済連携協定)介護福祉士候補者
・EPA(フィリピン・インドネシア・ベトナムとの経済連携協定)に基づく介護福祉士候補者が、国家試験に合格せずに在留期限を迎えた場合、特定技能「介護」に移行することが可能です。
採用時のポイント
・試験合格者は初心者が多いため、入職後の研修が重要
・技能実習2号修了者は即戦力になりやすいが、転職の可能性も考慮する必要あり
・介護福祉士資格を取得できるキャリアプランを用意することで、長期定着が期待できる
・特定技能「介護」で外国人を採用する際には、これらの条件を確認し、自社の方針に合った人材を選定することが大切です。
特定技能外国人の採用手順

有料老人ホームで特定技能外国人を採用するには、適切な準備と手続きを踏むことが重要です。
採用までの流れ
特定技能外国人を有料老人ホームで採用するためには、計画的に手続きを進めることが重要です。
受け入れ計画の策定
施設の人員配置や必要な人数を確認し、特定技能外国人の採用計画を立てます。
登録支援機関の活用(任意)
受け入れ企業は、外国人労働者の生活・就労支援を行う義務があります。支援を自社で対応するのが難しい場合は、登録支援機関に委託することも可能です。
求人募集・面接
現地の人材紹介会社や日本国内の求職者向けサイトを活用し、特定技能外国人を募集します。日本語レベルや介護の経験、技能試験の合格有無を確認し、面接を実施します。
雇用契約の締結
採用が決まったら、特定技能外国人と正式な雇用契約を締結します。雇用条件が日本人と同等以上であることを確認し、適正な労働条件を整えます。
ビザ申請・在留資格取得
雇用契約をもとに、出入国在留管理庁へ**「特定技能1号」の在留資格申請**を行います。必要な書類を準備し、許可が下りるのを待ちます(通常1〜3カ月)。
入国・雇用開始
在留資格が許可されると、外国人は日本に入国できます。入国後はオリエンテーションを実施し、職場環境や業務内容を丁寧に説明することでスムーズな受け入れにつなげましょう。
在留資格申請のポイント
特定技能外国人を有料老人ホームで雇用するためには、在留資格「特定技能1号」の申請が必要です。申請にはいくつかの重要なポイントがあります。
1. 必要書類の準備
在留資格申請には、以下の書類が必要です。
雇用契約書(雇用条件が適正であることを証明)
受け入れ計画書(特定技能外国人の業務内容・指導体制を記載)
給与支払い証明(日本人と同等以上の報酬であることを証明)
技能試験・日本語試験の合格証明書
特定技能協議会の加入証明書(加入が義務付けられている)
書類に不備があると審査が遅れる可能性があるため、正確に準備しましょう。
2. 申請の流れと期間
在留資格申請は、出入国在留管理庁に提出します。審査期間は通常1〜3カ月ですが、申請の混雑状況によってはさらに時間がかかる場合もあります。
申請から許可までの流れ
企業(または登録支援機関)が書類を準備し、地方出入国在留管理局へ提出
出入国在留管理庁が審査を実施(追加資料の提出を求められることも)
許可が下りたら**「在留資格認定証明書(COE)」**が発行される
COEをもとに外国人が査証(ビザ)を申請し、日本へ入国
3. 申請時の注意点
給与や労働条件が不適切だと不許可の可能性あり
→ 日本人と同等以上の待遇であることが求められる
過去に問題を起こした受け入れ機関は審査が厳しくなる
→ 法令違反や外国人労働者の失踪がある企業は要注意
特定技能協議会への加入は必須
→ 加入していないと申請が通らないため、早めに手続きを
入国後の流れと雇用開始
特定技能外国人が在留資格を取得し、日本に入国した後は、スムーズに業務を開始できるよう、適切なサポートと手続きが必要です。ここでは、入国後の流れと雇用開始のポイントを解説します。
1. 入国時の手続きと初期サポート
外国人労働者が日本に到着したら、まず以下の手続きを進めます。
在留カードの受け取り(空港で交付)
住民登録の手続き(市区町村役所で転入届を提出)
健康保険・年金の加入(事業所が手続きをサポート)
銀行口座の開設・携帯電話の契約(生活基盤の整備)
2. 事業所でのオリエンテーションと研修
有料老人ホームでの勤務を開始する前に、日本の職場文化や介護業務に適応するためのオリエンテーションを実施します。
就業規則・労働条件の説明(勤務時間・給与・休暇・福利厚生)
介護業務の基礎研修(施設のルール、利用者対応、介護技術の確認)
安全衛生・感染症対策の指導(事故防止・衛生管理のルール)
日本語コミュニケーションのサポート(簡単な敬語や業務用語の指導)
これらの研修は職場への適応をスムーズにし、長期定着を促進できます。
3. 配属と業務開始
研修後、配属先の施設で実際の業務を開始します。
OJT(On-the-Job Training)を活用
先輩職員がマンツーマンで業務を指導
少しずつ仕事の範囲を広げ、段階的に慣れてもらう
日常業務の確認
食事・入浴・排泄介助などの身体介護
レクリエーションや生活支援の実施
利用者とのコミュニケーションを意識
4. 定着支援の継続
雇用開始後も、特定技能外国人が安心して働き続けられるよう、継続的なサポートを行います。
月1回の面談・ヒアリング(仕事や生活の悩みを確認)
日本語学習のサポート(業務に必要な日本語力向上)
キャリアアップの支援(介護福祉士資格取得へのアドバイス)
特定技能外国人が安心して働ける環境を整えることで、人材の定着率向上と長期雇用の実現につながります。
特定技能外国人を雇用するメリット

有料老人ホームの人手不足を解消する手段として、特定技能外国人の採用が注目されています。特定技能制度を活用することで、介護の即戦力となる外国人材を確保し、安定した運営を実現できます。
人材不足の解消
日本の有料老人ホームでは、深刻な人手不足が続いており、特に介護職員の確保が大きな課題となっています。特定技能外国人の採用は、この課題を解決する有効な手段の一つです。
1. 慢性的な人材不足の現状
厚生労働省の発表によると、介護業界では2025年までに約37万人の介護職員が不足すると推計されています。特に有料老人ホームでは、利用者の増加に伴い、安定した人材確保が急務となっています。
2. 特定技能外国人が即戦力となる理由
特定技能外国人は、一定の知識や経験を持っています。そのため、採用後すぐに現場で活躍できる即戦力として期待できます。
3. 雇用の安定性
特定技能「介護」の在留期間は最長5年間であり、この期間は基本的に同じ施設で働くことが前提です。そのため、一般の介護職員と比べて短期間での離職が少なく、安定した雇用が見込めます。
人手不足に悩む有料老人ホームにとって、特定技能外国人の受け入れは、施設の運営を安定化させる大きなメリットとなるでしょう。
離職率の低さ
介護業界では離職率の高さが大きな課題となっていますが、特定技能外国人を採用することで、比較的長期的に安定した雇用を実現できます。
1. 介護職全体の離職率の現状
厚生労働省のデータによると、介護職員の離職率は**約15%**と高めで、特に若手職員の定着が難しいとされています。有料老人ホームにおいても、入職してもすぐに辞めてしまうケースが多く、継続的な人材確保が課題となっています。
2. 特定技能外国人の離職率が低い理由
特定技能外国人は、特定技能1号の在留資格を取得すると、最長5年間の在留が可能で、基本的には同じ職場で働くことが前提です。そのため、日本人介護職員と比べて短期間で転職するリスクが低いといえます。
さらに、介護福祉士の資格を取得すれば在留資格「介護」に移行でき、長期間日本で働き続けることも可能です。このため、日本でのキャリアを築こうとする意欲が高い傾向があります。
3. 安定雇用を実現するためのポイント
離職率の低さを維持するためには、雇用側のサポートも重要です。以下のような取り組みで、特定技能外国人の定着率をさらに高めることができます。
日本語教育の支援(業務に必要な言葉を学べる環境の整備)
文化・生活面でのサポート(住居の手配や生活相談の提供)
キャリアアップの支援(介護福祉士資格取得のサポート)
このようなサポートを充実させることで、外国人介護職員のモチベーションを維持し、長期間活躍してもらうことが可能になります。
他の介護人材制度との比較
特定技能外国人の採用を検討する際、他の外国人介護人材制度と比較することが重要です。ここでは、「特定技能」「技能実習」「EPA(経済連携協定)」「在留資格『介護』」の違いを解説します。
1.比較表

2. 特定技能「介護」のメリット
最短で即戦力となる(試験に合格すれば就労可能)
転職が可能(より良い職場環境を求めて転職できる)
特定の施設で広く受け入れが可能(有料老人ホームを含む介護施設全般)
3. 特定技能と技能実習の違い
技能実習制度では実習生の育成が目的であり、受け入れ企業は「指導」と「教育」を行う必要があります。一方、特定技能は実際の業務に従事する即戦力として雇用されるため、雇用後すぐに戦力として活躍できます。
4. 特定技能とEPAの違い
EPA介護福祉士候補者は、介護福祉士の資格取得を前提としているため、一定の研修期間を経てから現場で働く流れになります。一方、特定技能は、資格がなくても試験合格で就労可能なため、よりスムーズな採用が可能です。
雇用成功のポイントと注意点
特定技能外国人を有料老人ホームで採用する際には、受け入れ体制の整備や、職場環境の調整が重要です。特に、言語の壁や文化の違いに対応する工夫をしなければ、せっかく採用した人材が定着せず、早期離職につながるリスクもあります。
受け入れ体制の整備
スムーズな業務遂行ができる環境を整えることが必要です。
1. 研修・OJTの充実
特定技能外国人は一定の介護スキルを持っているものの、日本の介護施設の運営方法に慣れていない場合があります。その場合、実際の業務に適応できるように研修やOJTを実施することが重要です。
入職時研修(施設のルールや日本の介護文化を学ぶ)
OJT(実務研修)(先輩スタッフが付き添いながら指導)
定期的なフォローアップ研修(業務改善やスキルアップ支援)
2. 日本語サポートの強化
特定技能外国人は日本語能力試験(JLPT)N4以上が求められますが、業務で使う専門用語には慣れていない場合が多いです。以下のようなサポートはスムーズな業務遂行につながります。
施設内用語集の作成(「ナースコール」「離床」などの介護用語のリスト)
業務マニュアルの簡易日本語版の提供
定期的な日本語学習支援(社内勉強会・外部スクールとの連携)
3. 生活面のサポート
特定技能外国人は、母国を離れ日本での新生活に適応する必要があるため、生活面でのサポートも重要です。
住居の確保(外国人が入居しやすい住宅の紹介)
役所手続きの支援(在留カード取得、住民登録、銀行口座開設)
地域の生活情報の提供(スーパーや病院の案内)
コミュニケーションの工夫
外国人スタッフとのコミュニケーションは文化の違いを理解し、適切な伝え方を意識することが重要です。
1. 簡潔でわかりやすい言葉を使う
外国人スタッフには、難しい表現や曖昧な指示を避けることがポイントです。例えば、「臨機応変に対応してね」ではなく、「利用者さんがトイレに行きたそうだったら、ナースコールを押してください」と具体的に伝えます。
2. 多言語マニュアルの活用
介護業務の手順や緊急時の対応方法について、英語・ベトナム語・インドネシア語などの多言語で記載したマニュアルを用意すると業務を理解しやすくなります。
3. 定期的な意見交換の場を設ける
外国人スタッフは、職場の雰囲気や働き方に対して不安や疑問を抱えていることが多いです。定期的にミーティングや個別面談を実施し、業務上の悩みや改善点を話し合う機会を設けましょう。
「何か困っていることはない?」と定期的に声をかける
チームミーティングで意見を出しやすい雰囲気をつくる
外国人スタッフ同士の交流会を開催し、情報交換の場を提供
「伝える」だけでなく、「話を聞く」ことが重要です。
よくあるトラブルと対策
特定技能外国人を雇用する際には、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。
1. 転職リスクへの対応
特定技能外国人は転職が可能なため、より良い条件の施設に移るケースもあります。
➡ 対策:「働き続けたい」と思える環境を整える
キャリアアップ支援(介護福祉士資格取得のサポート)
給与や待遇の見直し
良好な人間関係の構築(相談できる環境をつくる)
2. 文化の違いによるトラブル
例えば、宗教上の理由で特定の食事を避ける必要があったり、価値観の違いから利用者対応にギャップが生じることがあります。
➡ 対策:相互理解を深める
入職時に文化の違いを事前に共有
外国人スタッフ向けのマナー研修を実施
日本人スタッフにも外国文化を学ぶ機会を設ける
3. 業務ミスの防止
言語の違いや日本の介護方式への不慣れから、業務ミスが発生することもあります。
➡ 対策:ダブルチェック体制の導入
初期の業務はペアで対応し、確認しながら進める
マニュアルの活用と実践的な研修の実施
利用者への対応時には、経験豊富な職員がフォローする
事前にトラブルを予測し、適切な対策を講じることで、スムーズな業務運営と定着率向上につながります。
今後の法改正の動向
・特定技能制度は、介護業界における人材不足の深刻化を背景に、さらなる拡充が検討されています。
訪問系介護サービスの解禁(2025年以降の可能性)
現在、特定技能「介護」は訪問系サービスには適用されていませんが、深刻な人材不足を受けて、厚生労働省が解禁の方向で議論を進めています。
2024年6月の有識者会議で、2025年度からの解禁を目指す方針が示されました。
特定技能2号への拡大の可能性
現在、特定技能「介護」は特定技能1号(最長5年の在留資格)のみですが、特定技能2号(在留期限なし・家族帯同可)への拡大が期待されています。
もし適用されれば、特定技能外国人の長期雇用が可能となり、より安定した人材確保が実現します。
外国人介護人材の受け入れ枠の拡大
日本政府は2024年までに介護分野で6万人の特定技能外国人を受け入れる方針を掲げていますが、今後さらに受け入れ枠が拡大される可能性があります。
まとめ
特定技能外国人の導入は、有料老人ホームにおける人手不足の解消に向けた有効な手段の一つです。特定技能の活用によって、介護サービスの質を維持しながら、持続可能な人材確保を実現していきましょう。
介護現場の人材不足、お困りではありませんか?
「特定技能の受け入れに興味はあるけれど、何から始めていいかわからない」
「本当に外国人スタッフが現場に馴染めるのか不安…」
そんなお悩みをお持ちの施設運営者・ご担当者様へ。
TSBケア・アカデミーでは、有料老人ホームでの介護人材の受け入れ実績をもとに、採用から在留資格手続き、支援計画の立案までワンストップでご支援いたします。
外国人介護士の受け入れが初めての方でも、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
“わかりやすく、丁寧に、安心できる”――TSBケア・アカデミーがしっかりサポートいたします。