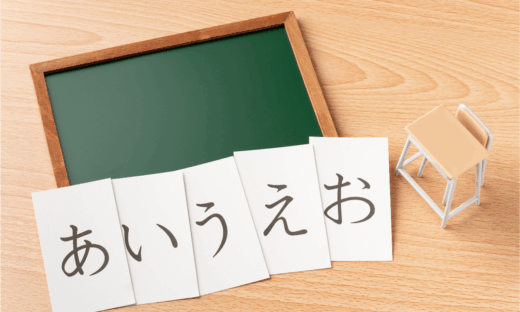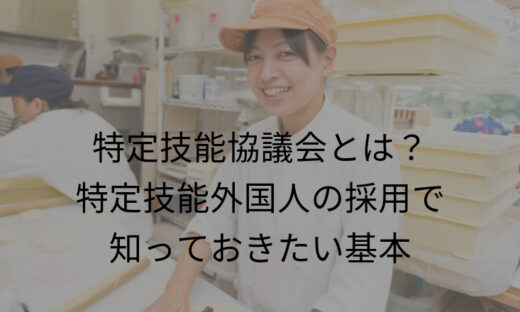外国人が日本で普通免許を取るには?取得条件・切替方法・注意点をわかりやすく解説【2025】

日本で生活や仕事をする外国人にとって、自動車の運転免許は「移動手段」以上の大切な役割を持ちます。特に地方では、通勤・買い物・業務に車が欠かせない場面が多く、運転免許の有無が生活の自由度や就労機会に直結します。
しかし、日本の交通ルールや免許制度は母国と異なる点が多く、手続きも複雑になりがちです。
本記事では、外免切替・国際免許・新規取得の違いから、特定技能との関係、企業がサポートすべきポイントまで、外国人が日本で安全に運転するために知っておきたい実務情報をわかりやすく解説します。
外国人が日本で運転免許を取得するには?基本の3つの方法
日本で自動車を運転するには、日本国内で有効と認められた運転免許証が必要です。
外国人の場合、運転免許の取得方法は大きく分けて「海外免許を日本の免許に切り替える」「国際運転免許証を利用する」「日本で新たに免許を取得する」の3つがあります。
それぞれ条件や手続きが異なるため、自分の状況に合った方法を選ぶことがポイントです。まずは各方法の特徴と注意点を整理しましょう。
海外免許を外免切替で日本の免許にする方法
海外で取得した運転免許証を、日本の免許に切り替える手続きが「外免切替」です。
国によっては技能試験が免除される場合もありますが、多くの国では実技試験・知識確認試験が必要になります。申請は住んでいる地域の運転免許センターで行い、必要書類はパスポート、在留カード、海外免許証、日本語訳文(大使館やJAF発行)などです。
切替では「その国で3カ月以上滞在して取得したこと」が条件とされており、取得時の滞在実績が確認されます。また、試験では日本特有の交通ルールや安全確認の厳しさが問われるため、事前に日本の道路事情に慣れておくと合格しやすくなります。
すでに海外で運転経験がある人にとって、最も負担の少ない方法です。
国際運転免許証で日本を運転する条件と注意点
国際運転免許証は、ジュネーブ条約加盟国で発行された免許証を持つ人が、日本で一定期間運転できる制度です。
ただし有効期間は「発行日から1年間」であり、さらに日本で住民票を取得した場合は国際免許証の使用が認められなくなる点に注意が必要です。あくまで短期間の滞在者向けであり、日本で継続的に生活・就労する予定がある外国人には適しません。
また、すべての国の国際免許が通用するわけではなく、非加盟国の国際免許証は無効となります。使用できるケースが限定されているため、「短期出張」「観光」「留学初期」など期間が決まっている場合のみ有効な手段といえます。
長期滞在者は早めに外免切替か日本での新規取得に進むことが望ましいです。
日本で普通免許を新規取得するには
海外免許を持っていない外国人が日本で車を運転するためには、国内で普通自動車運転免許を新規取得する必要があります。
新規取得には「指定自動車教習所に通って取得する方法」と「運転免許試験場で直接試験を受ける“一発試験”」の2つの方法があります。一般的には教習所に通う方法が主流で、費用はかかるものの合格率が高く、最も安全で確実な取得ルートです。
それぞれの特徴を理解し、自分の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
教習所に通う流れと費用・期間
日本で最も一般的な普通免許の取得方法が、指定自動車教習所(自動車学校)に通う方法です。
教習所では学科教習・技能教習を段階的に受け、仮免許を取得して路上教習へ進む流れとなります。全ての課程を修了すると、卒業検定を受け、合格後に運転免許センターで最終試験(学科のみ)に合格すれば免許取得となります。
費用は地域や教習所によって異なりますが、普通車ATで25〜35万円前後が一般的で、期間は1〜2カ月が目安です。外国人の場合、日本語での学科試験が壁になりやすいため、多言語教材を用意している教習所を選ぶと安心です。
教習所はスケジュール管理や段階的なサポートが手厚いため、運転に自信のない人や確実に取得したい人に向いています。
一発試験で取得する場合と合格の難易度
コストを抑えたい人や短期間で取得したい人が選ぶ方法が「運転免許試験場で直接試験を受ける“一発試験”」です。
学科試験と技能試験をいきなり受ける形式で、教習所に通う必要がないため費用は大幅に安くなります。しかし、技能試験は教習所の路上コースとは異なる厳密な採点基準があり、安全確認・徐行・進路変更など細かい動作を正確に行わなければならず、合格率は低めです。
また、日本語の試験であることから、外国人にとっては学科・技能の両面で難易度が高くなる傾向があります。事前に練習場での教習や模擬試験を活用することで合格可能性は上がりますが、「短期で取れる反面リスクも大きい」方法であることを理解して選ぶことが重要です。
特定技能と自動車免許の関係
特定技能で就労する外国人の中には、業務上「普通免許」や「第二種免許」が必要となるケースがあります。
特に自動車運送業では、運転免許は単なる付帯資格ではなく“業務遂行に必須の条件”となるため、免許の種類や取得ルートを正しく理解することが重要です。また、特定技能外国人には「受験資格特例教習」という制度があり、日本人より早く免許に挑戦できる場合があります。
ここでは業界ごとの免許要件と、免許取得を早める方法について整理します。
特定技能「自動車運送業」と普通免許・二種免許
特定技能「自動車運送業」は、トラックドライバー・バス運転手・タクシー乗務員などの業務を対象とするため、業務内容に応じた運転免許が必須になります。
一般的な配送業務では「普通免許」または「準中型免許」が求められ、旅客運送(バス・タクシー)では「第二種免許」が必要です。
特定技能で働く外国人の場合、まず普通免許または準中型免許を取得し、その後に二種免許へ進む流れが一般的です。
ただし二種免許の受験には条件があり、通常は「普通免許取得から3年以上の運転経歴」が必要とされています。企業が採用を検討する際には、候補者の運転経験や免許取得状況を事前に確認しておくことが重要で、免許がない場合は就業開始後の計画的な取得支援が必要です。
受験資格特例教習で免許取得を早める方法
特定技能外国人は、一部の教習所で実施されている「受験資格特例教習」を活用することで、普通免許や二種免許の取得に必要な運転経歴期間を短縮できる制度があります。
本来、第二種免許は「普通免許取得後3年」が条件ですが、特例教習を修了することで2年に短縮でき、早期に旅客運送業務へ就くことが可能になります。この特例は特定技能外国人の就業促進を目的に設けられた制度で、企業にとっては即戦力化につながる大きなメリットです。
とはいえ、教習内容は高度であり、日本語での学科理解や安全確認への強い意識が求められるため、企業側のフォローも不可欠です。特例教習を活用することでキャリア形成の幅が広がり、外国人材が長期的にスキルアップできる環境づくりにもつながります。
外国人が注意すべき日本の交通ルール・更新制度
日本で安全に運転するためには、交通ルールだけでなく保険・罰則・免許更新など、法律に基づいた運転管理が欠かせません。
特に外国人の場合、母国とのルールの違いや更新制度を誤解してトラブルになりやすいため、事前に日本の制度を正しく理解しておくことが重要です。
ここでは、日本で運転するうえで注意すべき基本ルールと、免許更新のしくみ、外国人に起こりやすいトラブルについて整理します。
交通ルール・法律・保険のポイント
日本の交通ルールは、国によって大きく異なる点が多いため、外国人が最も注意すべきポイントのひとつです。
日本では左側通行であり、歩行者優先の原則が強く、横断歩道での一時停止義務が徹底されています。また、飲酒運転・ながら運転(スマホ操作)に対する罰則は非常に厳しく、企業の業務中であれば会社に対しても責任が及ぶ場合があります。
さらに、自賠責保険は全車両加入が義務であり、任意保険にも加入していないと事故時の補償が不十分になります。母国では任意保険に入らない人も多いですが、日本では加入が一般的であり、企業が安全面から加入を必須としているケースも珍しくありません。
こうした基本ルールを理解し、安全確認を徹底することが日本での安全運転の第一歩です。
免許更新の流れとよくあるトラブル
日本では運転免許の更新が義務付けられており、更新時期は「誕生日の1カ月前〜誕生日後1カ月」の2カ月間です。
更新手続きは各地の免許センターで行い、視力検査・講習受講・写真撮影などを経て新しい免許証が発行されます。外国人が特に注意すべきなのは、住所変更を忘れていると更新通知が届かないことです。
結果として更新期限を過ぎ、免許が失効してしまうケースは非常に多く、再取得には学科試験や技能試験を受け直す必要が生じることもあります。また、長期帰国中に更新期限が過ぎるトラブルも起こりやすいため、出国前に免許センターへ相談しておくと安心です。
「更新通知が届かない=更新しなくていい」という誤解が原因で免許が使えなくなるケースが多いため、更新期限は本人が必ず管理する必要があります。
外国人の免許取得支援は企業の定着にもつながる
運転免許は特定技能をはじめとする多くの外国人材にとって、通勤や業務遂行に欠かせない重要な資格です。
企業が免許取得に必要な情報提供やサポートを行うことで、外国人が安心して働き続けられる環境が整い、結果として定着率向上にもつながります。
特に自動車を使用する業務では、早期に免許を取得できるよう企業が伴走することが大切です。
企業がサポートすべきポイント
外国人が日本で運転免許を取得するには、手続きや言語面で多くのハードルがあります。
企業ができる支援としてまず挙げられるのは、「外免切替が可能かどうかの判断」「必要書類・手続きの案内」「日本語での学科試験へのフォロー」などの情報提供です。
また、免許取得のためのスケジュール調整や、教習所選びのサポートも有効です。特に特定技能の場合、日本語試験の理解、交通ルールの違い、安全運転意識など、外国人がつまずきやすいポイントが多いため、企業が寄り添って説明したり、専門機関を紹介したりすることが重要です。
こうした支援は「企業が大切にしてくれている」という安心感につながり、定着率にも大きく影響します。
まとめ
TSBケアアカデミーでは、外国人材を受け入れる企業がスムーズに準備を進められるよう、特定技能制度の仕組みや在留手続きの流れ、受け入れ時の注意点など、幅広い情報提供を行っています。
免許取得が必要な業務の場合には、外免切替の可否判断や必要書類、日本での手続きの流れなど、事前に知っておきたいポイントをわかりやすく案内し、企業が適切な判断ができるようサポートします。
また、外国人本人の生活面での不安や、企業側の受け入れ体制についても相談できる体制を整えており、必要に応じて外部機関との連携も可能です。
免許取得そのものを直接行うわけではありませんが、企業と外国人材が安心して働ける環境づくりを“寄り添いながら”支えることを大切にしています。
ご相談はTSBケア・アカデミーへ
外国人材の受け入れには、在留資格、生活面のサポート、そして業務に必要な資格取得など、多くの手続きや準備が必要です。TSBケアアカデミーでは、特定技能制度に関する情報提供から受け入れ準備、外国人材と企業双方のフォローまで、伴走型でサポートしています。
「免許取得が必要な業務だけど、どこから説明すればいい?」「特定技能の受け入れ準備が不安…」という企業の方は、どうぞお気軽にご相談ください。
👉 TSBケアアカデミー
👉 お問い合わせはこちら
専門家と一緒に進めることで、外国人材の受け入れも、職場での定着もぐっとスムーズになります。まずはお気軽にご相談ください。