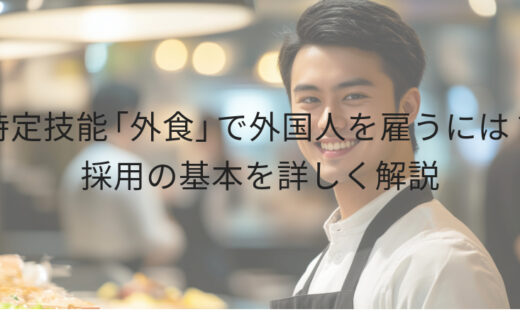高度人材ポイント制とは?外国人採用のメリットと申請の流れをわかりやすく解説!

「優秀な外国人を採用したい。でも制度が複雑すぎて…」——そんな声をよく耳にします。
実は、日本での外国人雇用を大きく後押しする制度が存在します。それが「高度人材ポイント制」。一定のスキルや経験を持つ外国人材を“高度専門職”として優遇し、企業の国際競争力を高めるために設けられた制度です。
しかし、制度の内容を一度調べ始めると、「ポイント計算って?」「永住権との関係は?」「申請に必要な書類は?」といった疑問が次々と湧いてくるはず。
中小企業の人事担当者や経営者にとっては、日々の業務の合間に制度を一から学ぶのはハードルが高く、つい後回しになりがちです。
この記事では、高度人材ポイント制の仕組みから企業が得られるメリット、申請の流れや注意点までを、できるだけわかりやすく丁寧に解説します。読み終わる頃には「これなら自社でもチャレンジできそう」と思えるはず!
日本で活躍する外国人材を、未来の“チームメンバー”として迎える第一歩を、ここから一緒に踏み出してみませんか?
高度人材ポイント制とは?制度の目的と導入背景

「高度人材ポイント制」は、日本にとって“優秀な外国人材”を積極的に受け入れるための制度です。少子高齢化で人材不足が深刻になるなか、専門知識や技術を持つ外国人の力を借りて、産業の活性化やイノベーションを促進しようというのが目的です。
この制度はポイント制で評価されるユニークな仕組みを持っており、要件を満たせば在留の優遇措置が受けられます。
高度人材ポイント制の概要と導入の経緯
「高度人材ポイント制」は、2012年に導入された外国人向けの在留優遇制度です。
ポイント制という仕組みを使って、学歴・職歴・年収・日本語力などをスコア化し、合計70点以上の人材を「高度人材」として優遇します。
背景には、日本の労働人口減少という課題があります。特に研究・IT・経営などの分野では、高度な知識や技術を持つ人材が国内だけでは足りません。
そこで、日本の成長に貢献してくれそうな外国人を積極的に呼び込み、働きやすい環境を整えることで、他国との“人材獲得競争”にも対応しようとしたのです。
この制度は、単に「人を集める」だけではなく、「優秀な人が長く日本に定着し、活躍できるようにする」ことも目的としています。
対象となる活動類型と在留資格の種類
高度人材ポイント制では、外国人が行う活動を大きく3つのタイプに分けています。それぞれに該当する活動内容や在留資格が異なります。
高度学術研究活動(高度専門職1号イ)
→ 大学での研究や教育に携わる教授・研究者など。
高度専門・技術活動(高度専門職1号ロ)
→ ITエンジニアや設計、国際業務など、専門的な知識・スキルを活かす職種。
高度経営・管理活動(高度専門職1号ハ)
→ 企業の経営者やマネージャーとして事業を担う人材。
これらの活動類型に応じて、求められる経験やスキル、加算されるポイント項目も変わってきます。
また、一定の条件を満たせば、「高度専門職2号」というさらに強い在留優遇が得られる仕組みもあり、日本での長期定着を目指す人にとっても魅力的です。
ポイント計算の仕組みを理解しよう

高度人材ポイント制では、学歴・職歴・年収などを「点数化」して評価します。
この制度のカギは、合計70点以上を獲得すること。点数の付け方にはルールがあり、自社に迎え入れたい外国人が制度の対象となるかどうかを判断するうえでも、仕組みをきちんと理解しておくことが大切です。
ここでは、評価される項目と、点数が変動するポイントについて解説します。
ポイント加算の評価項目と加点基準
ポイント制では、以下のような項目ごとに加点が設定されています:
・学歴(最大30点):博士号で30点、修士号で20点、学士で10点など
・職歴(最大20点):3年以上の実務経験で5点、10年以上で20点
・年収(最大40点):年齢ごとに基準が異なり、たとえば30代で500万円以上から加点対象
・年齢(最大15点):若いほど加点が高く、29歳以下で15点
・日本語能力(最大15点):JLPT N1保持で15点、N2は条件次第で加点あり
・研究実績・特許・受賞歴など(加点対象)
これらの評価を組み合わせて70点以上を目指す構成です。ポイントが足りなくても、特別加算などで届くケースもあります。採用候補者の履歴書や経歴書から、ある程度の見積もりが可能です。
特別加算や年齢・年収による影響とは
通常のポイント項目に加えて、特別加算という“プラスアルファの優遇”も用意されています。たとえば:
・日本の大学・大学院卒業で加点
・国の指定する優遇プログラムや支援事業の対象となっている大学・機関での実績があると加点
・スーパーグローバル大学卒業・JICA研修修了者なども対象
また、年齢や年収の条件によって、加点の難易度が変わるのも大きなポイント。たとえば、40歳以上になると年収の加点基準が800万円以上と厳しくなるため、企業側が提示する報酬額によって合否ラインが左右されるケースもあります。
つまり、この制度を活用するには、「候補者の経歴」と「企業側が提示できる待遇」のバランスを見極めることがカギ。逆に言えば、加点対象の項目を押さえていけば、優秀な人材をよりスムーズに採用できるチャンスにもつながります。
企業が高度人材を採用するメリット
高度人材ポイント制は、優れた外国人を日本に呼び込むための制度であると同時に、企業側にとっても多くの恩恵があります。ここでは、高度人材を採用することで得られる具体的なメリットについて、在留資格の優遇措置と家族支援という2つの視点から解説します。
在留資格の優遇措置による採用面の利点
高度人材に認定されると、最長5年の在留期間が一律で付与されるほか、複合的な業務活動が可能になるなど、通常の就労ビザにはない柔軟性があります。
これにより、企業は安定的かつ長期的な雇用計画を立てやすくなり、即戦力としての高度人材をより戦略的に活用できます。入国・在留手続きの優先処理も、採用スピードの面で大きな強みとなります。
配偶者就労・親の帯同など家族支援の魅力
高度人材の配偶者には、学歴や職歴に関係なくフルタイムでの就労が認められるほか、条件を満たせば親の帯同も可能になります。これにより、高度人材本人が安心して働ける環境が整い、採用後の離職リスクを下げることにもつながります。
家族を大切にする外国人材にとって魅力的な制度であり、結果的に企業の人材定着にも貢献します。
高度人材ポイント制を活用する申請手続きの流れ

高度人材ポイント制を使って外国人を採用・在留させるには、通常のビザとは異なるルールや準備が必要です。さらに、この制度は永住権の取得にも直結するため、きちんと流れを理解しておくことが重要です。
ここでは「在留資格の取得〜永住申請」までの具体的な流れと、企業が押さえるべきポイントを丁寧に解説します。
在留資格の取得・変更に必要な書類とステップ
外国人を高度人材として採用するには、「在留資格認定証明書の申請」もしくは「在留資格の変更申請」がスタート地点になります。
ポイント制の申請では、学歴・職歴・年収・日本語能力などに基づいた「ポイント計算表」の提出が必須で、それを証明するための書類もすべて揃える必要があります。
たとえば学歴の証明には卒業証書や学位記、年収には見込み収入証明書など、項目に応じて準備する書類が細かく決められています。しかも、日本で発行される証明書は“発行から3ヶ月以内”でなければならないなど、細かいルールがあるため、書類の準備は「逆算して」進めることが大切です。
また、家族を呼び寄せる予定がある場合には、扶養関係や収入証明など追加書類も必要になります。このように、制度の優遇を得るにはしっかりとした準備が欠かせません。
永住許可申請におけるポイント制の活用方法
高度人材ポイント制の最大の魅力の一つが、「永住申請の要件緩和」です。通常なら10年以上の在留歴が必要ですが、ポイントが70点以上なら3年、80点以上なら最短1年で申請できる特例があります。ただし、ポイント制による申請は一筋縄ではいきません。
重要なのは、「申請時点」と「過去のある時点」(1年前または3年前)の両方で基準点数をクリアしていること。つまり、ポイントは“ずっとキープ”していなければならないのです。
年収が一時的に下がったり、日本語資格の期限が切れてしまうと、申請のチャンスを逃してしまうことも。
さらに永住申請では、税金・年金・保険の納付状況や素行要件なども審査対象になります。つまり、「ポイントが足りている=必ず通る」というわけではありません。
企業としては、外国人本人が申請可能かをあらかじめ確認し、必要があれば専門家に相談するのが安心です。
採用企業が知っておくべき注意点と支援制度

高度人材ポイント制を活用して外国人を採用する際、企業側にも準備すべきことがたくさんあります。優秀な人材を受け入れるには、制度の理解だけでなく、社内体制の整備や、必要に応じた外部支援の活用が欠かせません。
ここでは採用前に知っておきたい実務的な注意点と、企業をサポートする支援制度について解説します。
人材受け入れ体制と社内準備のポイント
「採用はできたけど、うまく定着しなかった」――そんな声が少なくないのが外国人採用です。特に高度人材の場合、スキル面では十分でも、言語や文化、職場慣習の違いに戸惑うこともあります。そのため、企業側にも“受け入れの準備”が求められます。
たとえば、採用前には「日本語での業務指示に支障がないか」「相談しやすい社内環境があるか」をチェックしましょう。また、日本人社員向けに外国人との接し方を共有する“受け入れ側の教育”も大切です。
さらに、入社後すぐに生活の不安を感じないように、住居や生活サポートについても情報提供しておくと、安心感がぐっと高まります。高度人材は、ただ雇うだけでなく「活かして定着させること」が企業の実力につながります。
自治体による特別加算や支援制度の活用
高度人材ポイント制では、一部の自治体が企業の受け入れを後押しするための支援制度を設けています。たとえば、自治体から“イノベーション促進企業”などの認定を受けた場合、その企業で働く外国人にポイント加算(+10点)が認められるケースもあります。
この加点があることで、通常なら少し届かない人材も「高度人材」の基準をクリアする可能性が広がります。認定企業になるには要件や申請がありますが、採用活動の幅を広げる有効な手段です。
また、自治体によっては「外国人社員向けの日本語研修」や「定着支援セミナー」などを開催していることも。制度の導入を検討している企業は、自社の所在する自治体の支援策を一度チェックしてみると良いでしょう。
小さな助成や情報提供が、採用成功への一歩になります。
まとめ:高度人材ポイント制を活かして優秀な外国人材を採用しよう

高度人材ポイント制は、日本の企業にとって“即戦力となる優秀な外国人材”を迎え入れるための強力な制度です。ただし、そのメリットを最大限に引き出すには、制度の正しい理解と、企業側の受け入れ体制の整備が欠かせません。
最後に、制度活用のために押さえておきたいポイントを振り返ります。
制度理解と事前準備が成功の鍵
高度人材ポイント制は、一見すると複雑に思えるかもしれませんが、基本的な仕組みを理解しておけば決して手が届かない制度ではありません。
大切なのは、「どのような人材が対象か」「ポイントはどう加算されるか」といった根本を押さえたうえで、自社にとってどんな人材を求めているのかを明確にすることです。
そして、採用後の活躍・定着を見据えた社内環境の整備も忘れてはいけません。言語の壁や生活面の不安を乗り越える支援体制を整えることで、高度人材が本来の力を存分に発揮できるようになります。
この制度を“制度としてだけ”見るのではなく、“人と企業の未来をつなぐ仕組み”として活用することが、成功の第一歩です。
専門家の活用でスムーズな運用を目指す
高度人材ポイント制に関わる手続きやポイント計算は、想像以上に細かい部分が多く、「初めて」の企業にとっては不安もあるでしょう。そんなときは、行政書士やビザ専門のコンサルタントなど、制度に詳しい専門家にサポートを依頼するのもひとつの方法です。
専門家に依頼することで、自社では気づきにくい書類の不備や、見落としがちなポイント加算のチャンスも的確に拾ってもらえる可能性が高くなります。また、「今すぐ申請すべきか、あと半年待った方がよいか」といった戦略的なアドバイスを受けられるのも、大きなメリットです。
手間をかけるべきところにはしっかり時間を使い、必要な部分はプロに任せて、無理なく高度人材の採用を成功させましょう!
高度人材の採用でお悩みの企業様へ|まずは無料相談で不安を解消しませんか?
高度人材ポイント制を活用した採用にチャレンジしたいけれど、「制度が複雑でよく分からない」「うちでもできるの?」とお悩みではありませんか?
TSBケアアカデミーでは、高度人材のポイント計算や申請サポート、企業に必要な受け入れ準備まで、丁寧にご案内いたします。はじめての方も安心して進められるよう、お問い合わせより【無料相談】を承っております。
ぜひお気軽にご相談ください!