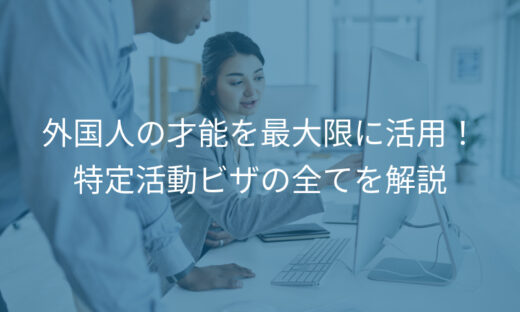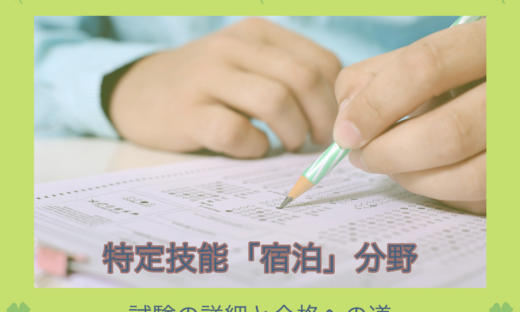外国人採用のはじめ方ガイド|在留資格の種類から雇用のメリット・注意点まで徹底解説!

近年、日本国内の人手不足はますます深刻化しており、特に中小企業では「人材確保」が大きな経営課題となっています。
そんな中、注目されているのが外国人労働者の採用です。国籍を問わず優秀な人材を迎え入れることで、業務の安定化や組織の活性化にもつながる可能性があります。
とはいえ、「どんな在留資格があるの?」「何から始めればいいの?」といった不安を抱える方も多いのではないでしょうか。
この記事では、外国人採用を検討している企業に向けて、採用の流れ・制度の基礎知識・活用メリット・注意点までを徹底的に解説します。
制度の仕組みを正しく理解し、自社に合った人材を採用・定着させるためのヒントをつかんでください。
外国人採用を検討すべき理由とは?

日本の労働人口が減少し続ける中で、人手不足は中小企業にとって深刻な課題となっています。そんな中、外国人採用は単なる労働力確保にとどまらず、企業の成長や多様性の推進にもつながる重要な手段として注目されています。外国人雇用を検討するべき背景を理解し、前向きな第一歩を踏み出しましょう。
外国人労働者の増加と日本の労働市場の現状
日本では少子高齢化により生産年齢人口が急速に減少しており、あらゆる業界で人材確保が困難になっています。この状況を受けて、政府は外国人材の受け入れを制度的に整備し、企業も積極的に採用を進めています。
2023年時点での外国人労働者数は過去最多を更新しており、今や彼らは多くの職場で欠かせない存在です。特に介護、建設、製造などの分野では、日本人だけでは人手が足りず、外国人の力が必要不可欠となっています。このような背景を正しく理解することが、外国人採用の第一歩です。
中小企業にとって外国人採用が有効な理由
大手企業と比べて人材確保に苦戦する中小企業にとって、外国人採用は現実的かつ戦略的な選択肢です。
言語や文化の違いを乗り越える支援体制を整えることで、長期的に戦力となる人材を確保できる可能性があります。また、海外市場との接点を持つことができたり、職場に多様性が生まれたりすることで、企業の競争力向上にもつながります。
実際に外国人を採用して定着させている中小企業では、生産性の向上や従業員満足度の向上が見られる例もあります。適切な採用と支援によって、中小企業が抱える人手不足という課題に対する有効な解決策となるでしょう。
雇用前に必ず理解しておきたい「在留資格」
外国人を採用する際に最も重要なのが「在留資格」の確認です。
どんなに優秀な人材でも、就労が認められない資格のままでは違法雇用となってしまいます。採用前に必ず「どの在留資格で」「どんな仕事ができるか」を理解し、ミスマッチを防ぎましょう。
就労可能な主な在留資格とその特徴
外国人が日本で働くには、就労可能な在留資格を取得している必要があります。在留資格にはいくつかの種類があり、それぞれ就ける職種や条件が異なります。代表的な就労系の在留資格には、以下のようなものがあります。
| 在留資格 | 主な対象職種 | 特徴 |
|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 通訳、翻訳、エンジニア、営業など | 専門知識を活かすホワイトカラー職 |
| 特定技能(1号・2号) | 介護、外食、建設、農業などの14分野 | 現場作業が中心。日本語や技能試験の合格が必要 |
| 高度専門職 | IT・研究・経営など | 永住権取得が早く、家族帯同も柔軟 |
| 経営・管理 | 企業経営者・マネージャー | 起業や事業経営に従事する外国人向け |
このように、職種や業種によって必要な資格は異なります。採用予定の業務に合った在留資格であるか、事前に確認しておくことが必須です。
在留資格ごとの就労範囲と注意点
在留資格によって就労できる範囲は細かく決まっており、許可された業務内容以外で働かせることは違法となります。また、留学生や家族滞在のビザを持つ人は原則就労不可で、アルバイト等は「資格外活動許可」が必要です。
注意すべきポイント:
・在留カードを確認し、資格内容と期限を把握する
・就労資格証明書を入手しておくと安心(特に職種変更時)
・定期的に在留期限を確認し、更新漏れがないよう管理する
・資格外活動や、資格範囲外での就労は「不法就労助長罪」の対象になることも
制度への理解不足がトラブルの原因になるケースも少なくありません。採用時には、行政書士などの専門家に相談するのも一つの方法です。
外国人を採用する際の具体的なステップ

外国人の採用は、日本人の採用とは異なるプロセスや法的な手続きが必要です。ルートによって進め方が大きく異なるため、まずは「どこから人材を確保するか」を明確にし、採用から入社までの全体の流れを把握しておくことが大切です。
外国人を採用する主なルート(国内・海外)
外国人採用には「国内在住の外国人を雇う方法」と「海外から呼び寄せる方法」の2つのルートがあります。
それぞれメリットや注意点が異なるため、自社の状況や目的に応じて選びましょう。
国内採用の特徴:
・すでに在留資格を持っているため、比較的スムーズに採用可能
・留学生や転職希望者が多い
・日本語能力や文化への適応度が高い傾向
海外採用の特徴:
・特定技能や技能実習、EPAなどの制度を活用できる
・人材の幅が広がるが、在留資格の取得や書類手続きが煩雑
・入国後の生活支援・教育体制も重要
・採用後の定着率や教育コストも見据えた上で、どのルートが自社に適しているか検討しましょう。
採用から在留手続きまでの流れ
採用が決まったら、在留資格の確認・取得、書類提出などの正式な手続きが必要です。
以下は一般的な採用〜入社までの流れです。
外国人採用の基本的な流れ:
募集・面接・採用決定
↓
求人媒体、紹介機関などを通じて募集
↓
在留資格の確認
↓
国内在住者の場合は「在留カード」で確認
↓
海外採用は「在留資格認定証明書交付申請」が必要
↓
必要書類の準備
↓
雇用契約書、会社概要、業務内容説明書など
↓
入管への申請手続き
↓
在留資格変更・認定の申請(1〜3か月かかる)
↓
許可後の入国・就労開始
↓
許可されたら入国→入社前のオリエンテーションを実施
手続きには時間がかかるため、余裕を持ったスケジューリングが鍵です。
申請が通らないケースもあるため、制度に詳しい外部専門家と連携しながら進めるのも有効な手段です。
外国人採用のメリットと企業成長への効果

人手不足を補うだけでなく、外国人材の雇用は企業にとって“成長のエンジン”にもなり得ます。
多様な価値観やスキルが組織にもたらす効果を理解し、外国人採用を単なる「労働力確保」以上の視点で活用することが重要です。
外国人雇用がもたらす組織へのプラス効果
外国人を採用することで、企業は単なるマンパワーの補充以上の恩恵を受けることができます。例えば、以下のような効果が期待されます。
職場の多様性向上:異なる文化や視点を持つ人材が加わることで、社内に柔軟性や新しい発想が生まれやすくなります。
グローバル対応力の強化:外国語対応や異文化理解が求められる業務に強くなり、海外展開やインバウンド対応にも有利です。
日本人社員の成長機会創出:外国人社員との協働を通じて、マネジメント力やコミュニケーション力が養われます。
また、外国人材は勤勉で向上心が高い傾向があり、長く活躍してくれる人材に育てることで企業の中核となるケースも少なくありません。
成功事例に学ぶ:外国人材の活躍と定着のコツ
実際に外国人を採用し、職場で活躍している企業には共通点があります。彼らは単に採用するだけでなく、受け入れ体制や人材育成に力を入れているのです。
定着・活躍の成功ポイント:
入社前の日本語研修や生活支援の充実
OJTだけでなく、丁寧な業務マニュアルの整備
相談窓口の設置など、心理的な安心感の確保
日本人スタッフへの異文化理解の教育
こうした取り組みによって、外国人材は自信を持って業務に取り組めるようになり、結果として生産性や職場の一体感も向上します。
定着率が上がれば、採用コストの回収だけでなく、リーダー候補の育成にもつながるという好循環が生まれます。
採用前に知っておきたい注意点とリスク管理
外国人採用には多くのメリットがありますが、その一方で法的・実務的な注意点を見落とすと、企業側が罰則やトラブルの当事者になるリスクもあります。
トラブルを未然に防ぎ、安定した雇用環境を整えるためには、法令理解と慎重な準備が欠かせません。
違法就労のリスクと在留資格確認の重要性
外国人を採用する際に最も注意すべき点が、「在留資格と許可された活動内容が一致しているか」です。
在留カードの確認だけでは不十分で、実際に就労可能かどうかを入国管理局のガイドラインに沿ってチェックする必要があります。
もし、在留資格に反する業務に従事させた場合、本人だけでなく企業側にも以下のようなリスクがあります:
・違法就労助長罪に問われ、懲役刑や罰金刑の対象になる
・社名公表や行政指導、許可の取消しリスク
・社内外の信頼失墜による事業への影響
採用前には、「資格外活動許可」の有無や就労制限の範囲、在留期間の確認も徹底しましょう。また、確認記録を残しておくことで、後々のトラブル回避にもつながります。
労働条件・賃金・支援義務などの法令遵守
外国人労働者を採用する企業には、日本人と同等以上の待遇を保証する義務があります。たとえば特定技能や技能実習では、法律で以下のような義務が定められています:
賃金は日本人と同等以上であること
週労働時間・残業・休日などが就業規則と整合していること
生活支援(日本語学習、住居確保支援など)を実施すること(特定技能の場合)
また、契約内容や労働条件はできる限り母国語でも説明し、理解を得たうえで雇用契約書に署名してもらうのが望ましいです。
法令を守るだけでなく、相手の安心感や信頼感を得ることが、長期雇用や職場定着の第一歩になります。
外国人材の定着と活躍を促す工夫
外国人を採用しても、すぐに離職されてしまうケースや、職場になじめないまま退職に至るケースも少なくありません。
こうした課題を防ぐには、企業側が受け入れ体制を整え、異文化への理解を深めながら、長期的に働ける環境づくりを進めることがカギとなります。
社内体制づくりとコミュニケーションの工夫
外国人材が安心して働けるようにするためには、社内の受け入れ体制やコミュニケーション方法の見直しが必要です。
言葉の壁だけでなく、文化や習慣の違いに配慮する姿勢が、信頼関係の構築につながります。
具体的な工夫の例:
・業務マニュアルの多言語化(日本語+母国語)
・やさしい日本語の活用によるスムーズな意思疎通
・定期面談や1on1ミーティングによる不安のヒアリング
・社内勉強会や異文化理解の研修を導入し、職場全体の理解促進
また、現場のリーダーが外国人と日々接する中で、ちょっとした配慮(あいさつ、声かけ、誤解の早期解消)を心がけるだけでも、離職防止に大きな効果があります。
外部支援機関の活用と長期的な人材戦略
企業単独で外国人材の定着を図るのが難しい場合は、登録支援機関や地域の支援団体のサポートを積極的に活用するのがおすすめです。
特に特定技能人材を受け入れる場合には、登録支援機関による生活支援や定着支援が義務化されていることもあります。
外部機関が提供する支援内容の一例:
・日本語教育・生活ガイダンスの実施
・住居や行政手続きのサポート
・文化的トラブルへの対応相談
・定着支援の報告・助言
さらに、中長期的な視点での人材活用には、キャリアパスの設計や昇進制度の整備も重要です。「短期間で帰国する人材」ではなく、「組織に貢献するメンバー」として成長できる道筋を示すことで、モチベーションも高まります。
まとめ:外国人採用を成功させるには、理解・準備・共創の姿勢がカギ

外国人採用は、単なる人手不足の解消手段にとどまらず、企業に新たな視点や多様性をもたらすチャンスでもあります。とはいえ、言語や文化、制度の違いに戸惑う場面も少なくありません。
だからこそ、制度や在留資格の正しい理解、受け入れ準備、そして「共に働く」という意識が不可欠です。
特に中小企業にとっては、「はじめの一歩」を慎重かつ柔軟に進めることが、採用成功と長期定着への近道になります。法令の遵守や支援体制の整備はもちろん、社内の意識改革や外部機関との連携も積極的に活用しましょう。
今や外国人材の活躍は、製造業や飲食業をはじめ、幅広い業種で不可欠な存在となっています。このガイドを通じて、少しでも不安を解消し、貴社にとって最適な人材との出会いと成長のきっかけとなれば幸いです。ぜひ、貴社の新たな一歩にお役立てください。
「外国人採用を始めたいけれど、何から手をつければいいのかわからない…」そんなときこそ、専門的なサポートを活用しましょう。
TSBケア・アカデミーでは、在留資格の選定から採用後の支援まで、企業に寄り添ったトータルサポートを提供しています。外国人採用を成功に導く第一歩として、まずはお気軽にご相談ください。