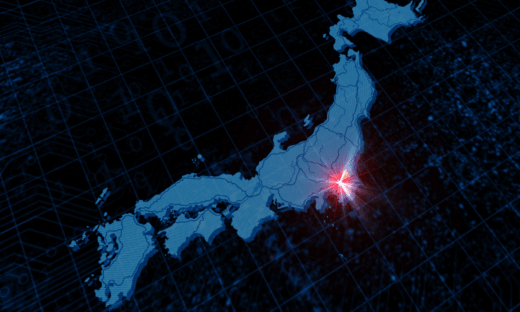外国人の一時脱退金とは?支給条件・計算方法・企業が押さえるべきポイントを解説

外国人労働者が日本で働いた後、帰国する際に「一時脱退金(脱退一時金)」という年金の払い戻し制度があることをご存じでしょうか?
この制度は、年金に一定期間加入した外国人が日本を離れる際に、支払った保険料の一部を受け取ることができる大切な権利です。
しかし、一時脱退金の仕組みや申請手続きは複雑で、条件を知らなければ支給されないこともあります。企業としても、従業員の安心した帰国を支えるために、制度への理解と適切なフォローが求められます。
本記事では、一時脱退金の制度概要から申請方法、支給されないケース、企業が果たすべきサポートまでをわかりやすく解説します。外国人雇用を行うすべての企業にとって、ぜひ押さえておきたい内容です。
外国人が受け取る「一時脱退金」とは?制度の基本を知ろう

外国人労働者が日本で働き、一定期間を経て帰国する際に受け取れる「脱退一時金(いちじだったいきん)」。これは、日本の公的年金制度に一定期間加入していた外国人が、将来的な年金給付の代わりに受け取れる制度です。
技能実習や特定技能などで日本に滞在した外国人にとって、帰国後の生活を支える貴重な収入源となります。制度の内容を正しく理解し、外国人本人への説明や企業としての支援につなげることが、トラブル防止と信頼関係の構築につながります。
一時脱退金の制度概要と目的
一時脱退金とは、日本の公的年金制度(厚生年金保険および国民年金)に加入していた外国人が、日本を出国して帰国する際に受け取れる給付金です。
本来、日本の年金制度は老後に年金を受け取ることを前提としていますが、短期間の滞在により将来的な受給資格を得られない外国人労働者に対して、保険料の一部を払い戻す仕組みが用意されています。
この制度の目的は、「短期間だけ保険料を納めた外国人に対して、納付実績に応じた一定の給付を行うことで、不公平感を減らし、制度への納得性を高めること」です。
特に、技能実習生や特定技能外国人のように2〜5年程度の在留期間で働く人々が、制度の対象として多く存在しています。
対象となる外国人の条件とは?
脱退一時金を受け取るためには、いくつかの明確な条件があります。主に以下のような外国人が対象となります:
・日本を出国していること(再入国の予定がない場合)
・日本国籍を持っていないこと
・公的年金制度に6か月以上加入していたこと(国民年金、厚生年金など)
・年金を一度も受給していないこと
・最後に年金制度から離脱してから2年以内に申請を行うこと
また、特定技能外国人や技能実習生だけでなく、留学生や技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで働いていた人も条件を満たせば対象となります。
企業としては、これらの条件を把握し、帰国時のサポートの一環として従業員に正しく伝えることが重要です。
とくに「申請期限が2年以内」である点や、「一時金を受け取ると年金加入期間がリセットされる」点などは、帰国後に再来日を検討する場合に影響するため、丁寧な説明が必要です。
一時脱退金の支給額や計算方法を理解しよう

一時脱退金は、加入していた年金制度やその期間、納付状況によって支給額が変わります。実際にいくらもらえるのか、どう計算されるのかは、外国人本人にとっても大きな関心ごとです。
企業側も「どのくらい戻ってくるのか?」をあらかじめ理解しておくことで、従業員への説明やサポートがスムーズになります。ここでは、一時脱退金の支給額とその計算方法の基本を見ていきましょう。
脱退一時金の金額はどのくらい?計算の目安
脱退一時金の金額は、年金の加入期間と納付額に応じて決まります。特に厚生年金の場合は、標準報酬月額に基づいて決まる保険料額が支給額の算定に影響します。
例として、厚生年金加入期間が3年の場合、2024年度の支給目安は約15〜20万円前後です(賃金水準によって上下します)。国民年金のみ加入していた場合は、月ごとに定額(年度によって変動)で支給され、1年あたり約5万円前後が目安になります。
また、支給金額の上限は「5年分(60か月)」までとなっており、それ以上の加入期間があっても加算されません。これにより、多くの技能実習生や特定技能外国人がフルで支給を受け取ることができる設計になっています。
支給対象となる年金の種類と加入期間との関係
脱退一時金の支給対象になる年金制度は、大きく分けて次の2つです:
・国民年金:主に自営業者や無職の期間、または就学中の人などが加入
・厚生年金:企業等に勤める従業員が加入する制度(技能実習生・特定技能外国人の多くはこちら)
加入していた年金の種類によって、支給額の計算方法や申請先が異なるため注意が必要です。また、両方に加入していた場合(例:留学中は国民年金、就職後は厚生年金)には、それぞれの制度に応じた金額が合算されることもあります。
ただし、加入期間が6か月未満の場合や、年金を一度でも受給していた場合には支給対象外となるため、事前に加入期間をしっかり確認することが大切です。
申請手続きと必要書類のポイント

一時脱退金の受給には、本人による申請が必須です。制度は整っていても、正しい手続きを踏まなければ支給されません。
企業としては、従業員がスムーズに申請できるよう、流れや必要書類をしっかり案内しておくことが大切です。この章では、申請のステップや注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
申請時の流れと所要期間
一時脱退金の申請は、日本年金機構への郵送申請が基本です。オンライン申請はできません。大まかな流れは以下の通りです:
・日本を出国
・必要書類を揃える
・帰国後、日本年金機構に申請書類を郵送
・審査・処理(通常3〜6か月)
・本人の海外口座へ送金
申請は、年金資格喪失日から2年以内に行う必要があります。申請が遅れると時効で受給できなくなるため、企業が「期限内申請」の重要性を強調しておくことが望ましいです。
なお、支給までは平均して約4か月前後かかりますが、申請内容に不備があるとさらに遅れることもあります。外国人本人が日本を離れてからも申請対応を続けることになるため、帰国前の準備が鍵になります。
必要書類と記入時の注意点
申請には以下の書類が必要です(2024年現在):
・脱退一時金請求書(日本年金機構の公式様式)
・パスポートの写し(出入国スタンプのあるページ含む)
・在留カードの写し
・年金手帳または基礎年金番号通知書の写し
・銀行口座情報(国外の本人名義口座)
・マイナンバー関連書類(日本に住民票があった期間がある場合)
請求書は日本語または英語で記入可能ですが、不備や記入漏れがあると差し戻されるため、企業で事前に記入方法を説明しておくと親切です。
特に注意したいのは、出国スタンプの確認と、銀行口座情報の正確性です。外国人本人が持っている口座が、日本からの海外送金に対応しているかを事前に確認しておくと安心です。
支給されないケースとその理由を把握しておこう
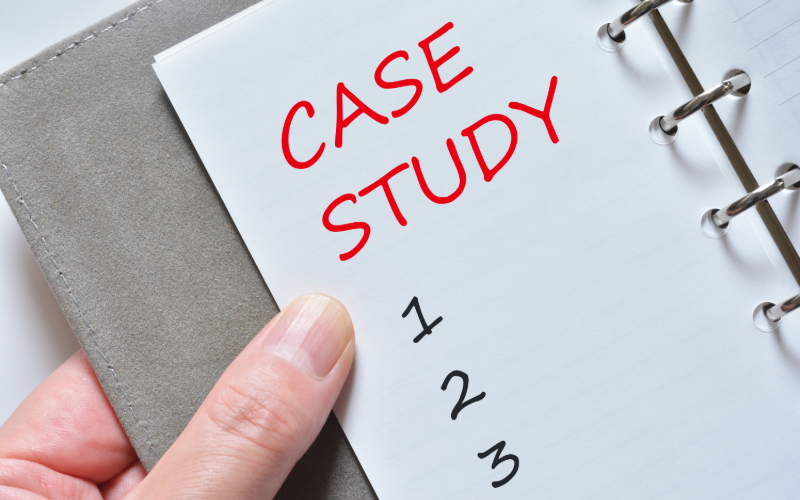
一時脱退金は条件を満たせば受給できる制度ですが、申請しても「支給されない」ケースも少なくありません。
申請のタイミングや在留資格、加入記録の不備など、思わぬ要因が原因になることがあります。
ここでは、具体的な支給不可の理由とその予防策を整理し、外国人労働者への適切な案内と企業側のリスク回避に役立てましょう。
二重加入・在留資格の影響など注意点
一時脱退金の支給に関しては、加入記録と在留資格の内容が重要な審査対象になります。以下のようなケースでは、支給対象外または減額対象になることがあります:
・年金に6か月未満しか加入していない場合
→制度上、6か月以上の加入が必要。端数切り捨てとなるため注意。
・一時脱退金をすでに受給した後に再来日し、再び加入した場合
→初回分しか受給できず、再度の申請は不可(脱退金を受け取った時点で加入期間がリセットされるため)。
・出国後に再入国してしまった場合
→「出国して再入国の予定がないこと」が条件のため、再入国記録があると不支給となる。
・在留資格が「永住者」「特別永住者」の場合
→制度の対象外となっており、一時脱退金は申請できない。
また、申請時にパスポートの出国印が確認できない場合や、記録に不整合があると、申請が差し戻されることもあります。
よくある支給不可の事例とその対策
実際に多く見られる支給不可の事例は、以下のようなパターンです:
・帰国後に申請を忘れ、2年の申請期限を過ぎてしまった
→対策:退職時や帰国前に必ず説明し、申請スケジュールを紙面で共有しておく。
・年金番号や基礎年金番号が分からず、加入記録の確認ができない
→対策:在職中に企業が年金番号を確認し、従業員に伝えておく。
・銀行口座の情報が不正確で振込ができなかった
→対策:口座の名義・SWIFTコード・住所などをきちんと確認し、控えを残す。
・出国記録がパスポートに押されていない(自動化ゲート使用時)
→対策:自動化ゲート通過前に、有人ブースで出国印を押してもらうよう指導する。
これらのケースは、企業の一言で防げるものが多く、在職中の情報共有と退職時のサポート体制が大きなカギになります。
企業が果たすべきサポートの役割

一時脱退金は、外国人本人が自ら申請する制度ですが、適切な申請を支える企業のサポートが不可欠です。
特に退職・帰国時はさまざまな手続きが重なるため、本人だけでは必要な情報や流れを正しく把握できないことも少なくありません。
ここでは、企業側が担うべきサポートの具体的な内容と、その重要性について整理します。
離職前後のフォローで企業ができること
外国人労働者が安心して一時脱退金の手続きを進められるように、企業は離職前からの支援体制を整えておくことが求められます。特に以下の点が有効です:
・退職時に一時脱退金制度について説明する
→支給対象・申請条件・申請先・期限をわかりやすく解説する資料を配布。
・出国日と在留期限の確認をサポート
→「在留資格喪失日」が正しく反映されないと支給されないことがあるため、帰国スケジュールを正確に把握。
・年金手帳や基礎年金番号通知書の保管確認
→再発行が難しいため、本人に確実に持たせる。
・自動化ゲート利用時の“出国印”の案内
→出国スタンプが必要なことを事前に説明し、有人ブースでの通過を促す。
・申請書の記入支援(企業が代理提出は不可)
→書き方見本の提供や、退職面談時の記入サポートなどが有効。
このように、実務的な手続きの“抜け”を防ぐ工夫が、企業と本人双方にとってメリットとなります。
制度理解を深めるための社内教育・情報提供
一時脱退金制度は、総務・人事担当者にとっても専門的な分野であり、対応に不安を感じることもあるでしょう。そこで必要なのが、社内での情報共有と教育の充実です。
・外国人雇用に関する勉強会の実施
→制度の基礎、申請フロー、支援の範囲などを社内で共有。
・マニュアル・チェックリストの整備
→退職時に確認すべきポイントや、配布資料のフォーマットを標準化。
・登録支援機関や専門家との連携
→難しいケースは外部の支援を活用して対応精度を高める。
・外国人本人への多言語対応資料の準備
→日本語が苦手な従業員でも理解できるよう、英語・ベトナム語・中国語などで制度解説を行う。
企業にとっても、一時脱退金に関する支援体制の整備は「信頼される雇用主」としての評価にもつながります。定着支援の一環として、
”制度の“正しい伝達”を意識しましょう。
まとめ:制度を正しく理解し、円滑な帰国支援を

一時脱退金は、外国人労働者が日本でまじめに働いた証として受け取ることができる、非常に重要な制度です。正しく申請すれば、帰国後の生活を支えるまとまった資金となる一方で、条件を満たさなかったり、申請に不備があると一円も受け取れないまま失効してしまうリスクもあります。
企業側がこの制度について十分に理解し、外国人従業員の離職や帰国にあたって必要な情報提供と実務的なフォローを行うことは、雇用主としての責任でもあります。
特に注意すべき点としては、
・申請には期限がある(出国後2年以内)
・申請書の不備・記入ミスは差し戻しの原因に
・出国スタンプがないと申請が通らない
・脱退一時金の受給後は再来日しても年金加入期間がリセットされる
など、見落としやすい落とし穴が多いことが挙げられます。
だからこそ、外国人雇用を行う企業は、一時脱退金について“事前に”案内し、“帰国前に”サポートすることが大切です。小さな説明や配慮が、従業員の安心や満足度につながり、企業の信頼にも直結します。
人手不足の中、外国人材の力は今後ますます欠かせない存在です。だからこそ、働いてくれた彼らの“出口支援”もおろそかにせず、制度を正しく活用して、最後まで丁寧に寄り添う姿勢を大切にしましょう。
外国人従業員へのサポート体制を強化したい、帰国前の対応に不安がある——
そんな時は、外国人雇用支援の専門機関「TSBケアアカデミー」にご相談ください。
各種在留資格に関する制度解説から、採用・定着・離職支援まで、企業の実務を丁寧にサポートいたします。
詳しくは TSBケアアカデミー公式サイト をご覧ください。
具体的なご相談やお問い合わせは、こちらのフォーム からお気軽にどうぞ。