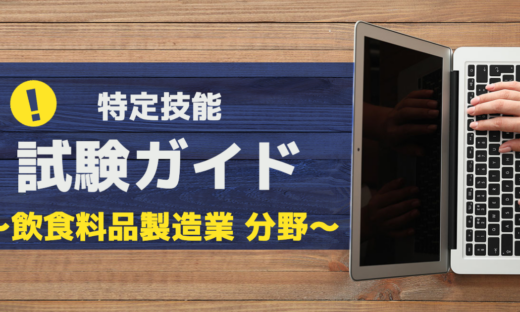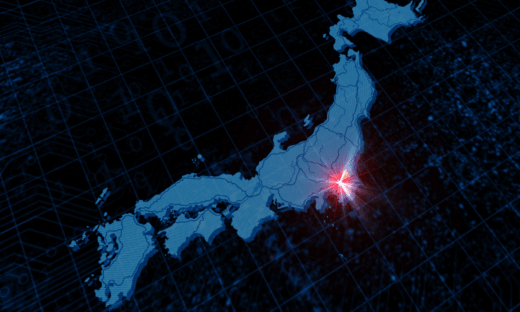就労ビザで家族は呼べる?帯同できる条件と手続きをわかりやすく解説!

外国人が日本で働くとき、「家族を日本に呼び寄せられるのか?」という点は本人にとっても企業にとっても大きな関心事です。就労ビザの種類によって帯同できるかどうかが異なるため、制度を正しく理解することが欠かせません。
本章では、帯同が認められる在留資格と認められないケースを整理します。
就労ビザで家族は帯同できるのか?
結論から言えば、すべての就労ビザで家族帯同が認められるわけではありません。家族を日本に呼ぶには「帯同が可能な在留資格」を持っている必要があり、さらに経済的な安定や生活基盤の整備も求められます。
制度の理解不足はトラブルや申請不許可につながるため、雇用企業も基本的なルールを押さえておくことが重要です。
帯同が認められる在留資格の種類
家族帯同が認められる代表的な就労ビザは、以下のような「高度専門職・専門性の高い活動」が中心です。
技術・人文知識・国際業務
経営・管理
高度専門職
研究・教育・医療などの専門分野
これらの在留資格を持つ外国人は、配偶者や子どもを「家族滞在ビザ」で呼び寄せることが可能です。特に高度専門職は優遇措置があり、家族帯同の要件が緩和されている点も特徴です。
加えて、これらの在留資格を持つ外国人は、日本国内で比較的長期に安定して働くことを前提としています。
そのため、入管庁の統計によると「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」といったカテゴリーは就労ビザ全体の中でも大きな割合を占めており、家族帯同の申請も多く見られます。特にITエンジニアや通訳、外資系企業の管理職などは、配偶者や子どもと共に日本で生活するケースが一般的です。
また、「高度専門職」については、他の在留資格と比べて優遇措置が設けられており、たとえば在留期間が最長5年で一括付与される点や、永住許可の要件が短縮される点が特徴です。これにより家族が安心して生活基盤を築けるため、長期的な定着を促す制度設計となっています。
帯同が認められないケース
一方で、以下のような在留資格では原則として家族帯同は認められていません。
技能実習:人材育成を目的とした制度のため、家族帯同は不可。
特定技能1号:即戦力としての就労は可能だが、家族帯同は認められない。
短期滞在・留学(原則):一時的な滞在や学習を目的とするため帯同不可。
ただし、特定技能2号は例外的に家族帯同が認められるため、制度改正と併せて今後注目される分野です。【数字】(→特定技能2号の対象分野数や実績数を入れると有効)
家族を呼び寄せるための在留資格
外国人本人が就労ビザを持っていても、そのまま家族が自動的に日本に滞在できるわけではありません。帯同する家族は、別途「家族滞在ビザ」や「配偶者・子どもの在留資格」を取得する必要があります。
ここでは、それぞれの仕組みを整理します。
家族滞在ビザの仕組み
「家族滞在ビザ」は、就労ビザを持つ外国人が配偶者や子どもを日本に呼び寄せる際に利用される在留資格です。対象となるのは主に配偶者(法律上の結婚相手)と未成年の子どもで、両親や兄弟は原則含まれません。
このビザで帯同する家族は、原則として日本でフルタイムの就労はできませんが、「資格外活動許可」を取得すれば週28時間以内のアルバイトは可能です。生活の中心は「扶養されること」にあり、就労が主目的ではない点に注意が必要です。
配偶者ビザ・子どもの在留資格
配偶者が日本人、永住者、定住者のいずれかである場合には、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」といった在留資格が認められます。これらの資格では、家族滞在ビザとは異なり、就労制限がなく自由に働くことが可能です。
また、子どもについては出生や養子縁組の状況に応じて「日本人の子ども」「永住者の子ども」などの在留資格が付与されます。こうした在留資格は、安定的に日本で生活するための権利を保障するものであり、家族滞在ビザよりも幅広い活動が可能です。
家族帯同に必要な条件と審査ポイント
家族を日本に呼び寄せるためには、就労ビザの種類だけでなく、生活を維持できるだけの条件を満たしているかどうかが審査されます。
特に重要なのは「経済的安定性」と「住居や生活環境の整備」の2点です。これらを証明できなければ、家族滞在ビザの申請が不許可になる可能性もあります。
経済的安定性と収入基準
家族を帯同する際、最も重視されるのが経済的な安定性です。申請者本人が安定した収入を得ており、家族を扶養できるだけの経済力があることを示さなければなりません。
入管庁が明確な金額を公表しているわけではありませんが、目安としては 年間250万〜300万円程度の収入 が一つの基準とされています。
証明のためには、給与明細、雇用契約書、課税証明書、納税証明書などが必要になります。これらを揃えて提出することで、安定的に家族を養える体制があることを示すことができます。
なお、この収入基準は「家族の人数」によって変動する可能性がある点にも注意が必要です。たとえば扶養する家族が1人であれば年間250〜300万円程度でも許可されやすい一方、2人以上を帯同する場合には、それ以上の収入が求められる傾向があります。
入管庁の明確なガイドラインはありませんが、実務上は「最低限の生活を営むために十分な収入があるか」が総合的に判断されます。
また、収入の安定性を示すためには「直近の年収」だけでなく、勤務先企業の規模や雇用形態(正社員かどうか)、継続雇用の見込みなども考慮されます。
そのため、派遣社員や契約社員の場合でも、雇用契約の更新実績や企業からの推薦文を添付することで、審査を有利に進められる場合があります。
住居や生活環境の整備
経済的な基盤に加えて、家族が安心して暮らせる住居の確保も重要な審査ポイントです。
単身者向けの狭い住居では帯同が難しく、家族の人数に応じた間取りや設備が整っていることが求められます。また、学校や医療機関など、生活インフラが整った環境であることも審査の際に重視されます。
さらに、住居契約書や住民票などを提出し、居住環境が安定していることを客観的に示す必要があります。こうした準備を怠ると、たとえ収入基準を満たしていても不許可となる可能性があるため注意が必要です。
さらに、審査においては「子どもが健やかに成長できる環境かどうか」も間接的に見られることがあります。
たとえば、保育園や小中学校へのアクセス、病院や公的サービスの利用のしやすさなど、生活インフラが整っている地域に住んでいるかどうかが評価につながります。特に小さな子どもを帯同する場合、教育機関の空き状況や医療体制は重要なチェックポイントです。
また、家族用の住宅を借りる際には「連帯保証人が必要」「外国籍の入居に制限がある」といった日本特有の住宅事情に直面することも少なくありません。
こうした壁をクリアするために、企業や専門支援機関が不動産会社との間を仲介し、住居確保を後押しするケースも増えています。受け入れ企業が事前に地域の住宅環境や生活支援制度を調べておくと、申請手続きもスムーズになります。
家族帯同の手続きの流れ
家族を日本に呼び寄せるためには、在留資格を取得するための申請から入国後の各種手続きまで、複数のステップを踏む必要があります。特に「在留資格認定証明書」の申請は最初の重要なポイントとなります。
在留資格認定証明書の申請手続き
家族を日本に帯同させる際、まず必要となるのが「在留資格認定証明書(COE)」の申請です。これは、日本に滞在するための資格があることを法務大臣が証明するもので、原則として日本にいる就労ビザ保持者が申請人となります。
申請は地方出入国在留管理局で行い、必要書類としては扶養者の在留カードや雇用契約書、収入証明、家族関係を示す戸籍や婚姻証明書などが求められます。審査には通常 1〜3か月程度 かかるのが一般的です。
また、申請の際には「審査期間中に家族が一時的に来日できない」という点を理解しておく必要があります。つまり、COEが交付されるまでは原則として帯同家族が日本に滞在することはできず、観光ビザなどを利用して短期的に滞在する方法も制限があります。
こうした事情を知らずに渡航スケジュールを組むと、想定外のトラブルにつながりかねません。
さらに、書類不備による差し戻しも珍しくなく、追加書類の提出を求められるケースもあります。例えば、婚姻証明書の和訳や出生証明書の公的認証など、母国での手続きに時間を要する場合が多いため、余裕を持った準備が不可欠です。
企業が外国人本人と連携して必要書類を早めにチェックし、サポート体制を整えることが、円滑な帯同実現につながります。
入国後の在留カード交付と各種手続き
家族が日本に入国すると、空港で在留カードが交付されます。これが正式に日本での滞在資格を証明する書類となります。その後、14日以内に住居地を市区町村役場に届け出る必要があり、住民登録を行うことで健康保険や年金制度の利用が可能になります。
さらに、銀行口座開設や携帯電話契約など、生活基盤を整えるための手続きも順次必要となります。これらのサポートを企業が直接担う義務はありませんが、受け入れ企業が一定のサポートを行うことで、外国人本人と家族の定着につながり、結果的に就労の安定にも寄与します。
企業が理解しておくべきサポート
外国人本人が就労ビザを持ち、家族帯同が認められたとしても、生活基盤が整わなければ不安やトラブルにつながりやすくなります。企業が家族の存在も含めてサポートすることは、本人の就労継続や定着率の向上に直結します。ここでは企業が押さえておくべきサポート内容を整理します。
帯同家族への生活支援
家族帯同では、生活の立ち上げに多くの支援が必要となります。具体的には、住居探しのサポート、行政手続きの案内、学校や保育園に関する情報提供などがあります。特に子どもがいる場合、教育機関や医療機関の利用について丁寧に説明することが求められます。
また、家族が孤立しないように地域コミュニティや外国人支援団体を紹介するのも効果的です。こうした配慮は、外国人本人の安心感を高め、長期的な就労意欲を維持することにつながります。
福利厚生・就労規則の整備
帯同家族の存在は、企業の福利厚生制度や就労規則にも影響します。例えば、家族を扶養に入れる場合の社会保険手続き、住宅手当や家族手当の適用範囲をどのように設定するかを明確にしておくことが重要です。
また、外国人本人が育児や家族の事情で勤務に制約が生じるケースもあるため、柔軟な勤務形態や休暇制度を整えることで、離職を防ぐ効果が期待できます。企業側がこうした体制を整備することは、採用力の向上にも直結します。
まとめ
就労ビザを持つ外国人が日本で家族を帯同するには、在留資格の種類や審査条件を正しく理解することが不可欠です。家族滞在ビザや配偶者ビザなどを通じて帯同は可能ですが、収入や住居といった生活基盤の安定が求められます。
手続きも複数のステップを踏む必要があり、申請準備から入国後の生活まで企業が一定の理解を持つことで、本人とその家族の定着につながります。
外国人本人にとって「家族と共に暮らせる安心感」は、長期的に働き続けるうえで大きなモチベーションになります。そのため、雇用する企業にとっても家族帯同の仕組みを知り、必要なサポートを検討することが人材戦略上の強みとなるのです。
👉 外国人材の家族帯同や就労ビザに関するサポートについて詳しく知りたい方は、TSBケア・アカデミー の お問い合わせ からご相談ください。専門スタッフが制度理解から実務支援まで丁寧にサポートいたします。