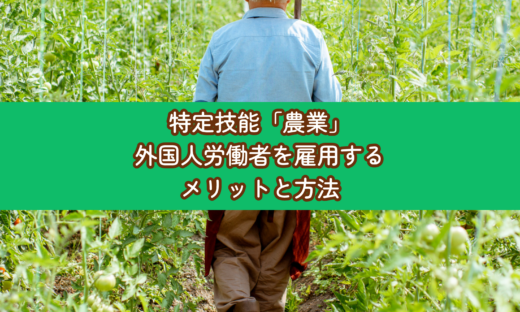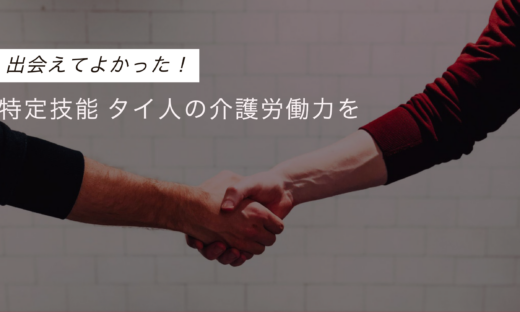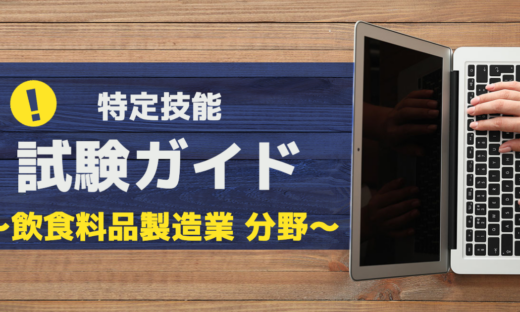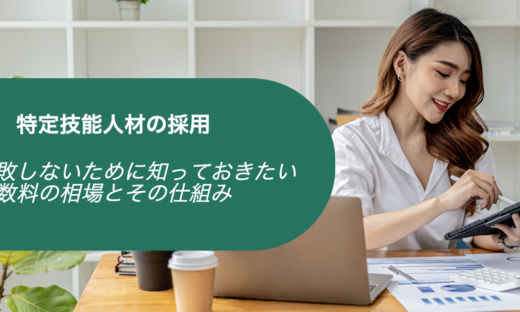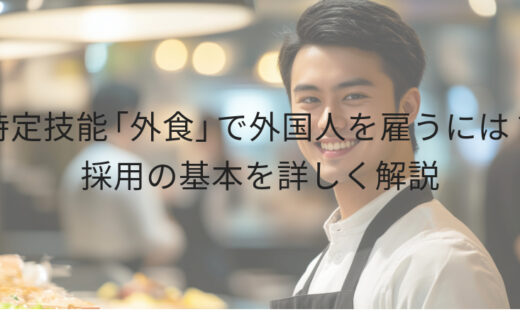特定技能の送り出し機関とは?役割・国別一覧・注意点をわかりやすく解説!

海外からの人材受け入れが進む中で、企業がまず直面するのが「送り出し機関」との関わり方です。
外国人採用において送り出し機関は、候補者の募集や日本語教育、渡航手続きなどを担う重要なパートナーですが、その仕組みや役割を正しく理解していないと、思わぬトラブルにつながることもあります。
本記事では、送り出し機関の基本的な仕組みから、認定基準、トラブル事例、そして信頼できる機関を選ぶためのポイントまでをわかりやすく解説します。
特定技能制度を活用したクリーンで持続的な外国人雇用を目指す企業の皆さまは、ぜひ最後までご覧ください。
送り出し機関とは?基本的な役割と位置づけ

外国人材を採用する際、まず関わってくるのが「送り出し機関」です。
送り出し機関とは、日本で働きたい外国人を自国で募集・選抜し、日本企業へ送り出す役割を担う海外の組織を指します。単に人材を紹介するだけでなく、来日前の教育や手続きのサポートまで担う重要な存在です。
日本の労働力不足を背景に、アジア諸国を中心に多くの送り出し機関が設立されてきました。しかし、その数が増える一方で、業務の質や信頼性には大きな差があります。優良な機関を選ぶことが、外国人雇用を円滑に進める第一歩といえるでしょう。
送り出し機関の定義と主な業務内容
送り出し機関は、現地の求職者と日本の受け入れ企業・監理団体をつなぐ橋渡し役です。
主な業務には、以下のようなものがあります。
現地での求人募集・面接・選抜
日本語や生活マナーなどの事前教育
在留資格取得や渡航に関する手続きの支援
入国後の問い合わせやトラブル対応
これらを通じて、候補者が安心して来日し、スムーズに就労を開始できるようサポートします。
また、送り出し機関は日本政府と送り出し国政府との「二国間協定(MOC)」に基づいて運営されるため、政府による監督・認定制度が設けられています。
ただし、実際には教育やサポートの質が十分でない機関や、金銭的な負担を過度に求める悪質なケースもあります。送り出し機関を通じて採用する企業側も、信頼性を慎重に見極める必要があります。
技能実習・特定技能など在留資格ごとの関与の違い
送り出し機関が関わる在留資格は複数ありますが、代表的なのは「技能実習」と「特定技能」です。
技能実習制度では、送り出し機関の利用が原則必須です。技能実習生を日本に呼び寄せる際には、現地の送り出し機関が求職者を選抜し、日本の監理団体や受け入れ企業との面接調整を行います。
さらに、日本語教育や生活指導、渡航準備など、来日前の支援を包括的に担います。
一方で、特定技能制度では送り出し機関の利用は必須ではありません。
日本にすでに在留している外国人を直接採用することが可能であり、企業が独自に採用・手続きを行うケースもあります。
ただし、一部の国(例:ベトナム・フィリピン・ミャンマーなど)では、政府が認定した送り出し機関を経由しなければならないというルールが設けられています。
つまり、在留資格の種類や出身国によって、送り出し機関の関与範囲は大きく異なるのです。企業としては、それぞれの制度や国のルールを正確に理解したうえで採用計画を立てることが大切です。
技能実習制度と特定技能制度における違い

外国人材を受け入れる制度の中でも、「技能実習」と「特定技能」は混同されやすい制度です。どちらも日本で働くことを目的としていますが、制度の目的や運用の仕組み、送り出し機関の関与の有無などに明確な違いがあります。
この章では、それぞれの制度の特徴を整理しながら、送り出し機関の役割がどのように異なるのかを見ていきましょう。
技能実習では送り出し機関が必須になる理由
技能実習制度は、「開発途上国への技術移転」を目的として設けられた制度です。日本の企業や団体が外国人を受け入れ、一定期間の実習を通じて技術や知識を学ばせ、帰国後に母国の発展に役立ててもらうことが狙いとされています。
この制度で外国人を受け入れる際には、送り出し機関の関与が必須です。技能実習生を募集し、面接の調整、日本語教育、出国手続き、そして日本到着後の初期フォローまで、送り出し機関が一貫してサポートします。
また、技能実習制度では「監理団体」が実習生を受け入れる企業を支援する仕組みとなっており、送り出し機関はその監理団体と密接に連携します。つまり、送り出し機関は技能実習制度の根幹を支える存在なのです。
ただし、この構造が複雑であるがゆえに、関係者の間での情報の齟齬や、責任の所在が曖昧になるケースも少なくありません。そのため、監理団体・受け入れ企業・送り出し機関の三者が適切に連携し、透明性を確保することが求められます。
特定技能では「不要」だが例外もある仕組み
一方で、特定技能制度は「人手不足分野における労働力確保」を目的とした制度です。技能実習と違い、雇用契約に基づいて労働する在留資格であり、実務の担い手として即戦力となる外国人を受け入れる仕組みです。
この制度では、送り出し機関を必ず利用しなければならないわけではありません。日本企業が直接採用を行い、在留資格申請や雇用契約を自社で完結させることが可能です。
特に日本国内にすでに在留している外国人を採用する場合は、送り出し機関を経由する必要がありません。
ただし、一部の国では例外的に、政府が認定した送り出し機関を経由することが義務付けられています。たとえば、ベトナム・フィリピン・ミャンマーなどの国々では、二国間協定(MOC)により、現地の認定送り出し機関を通すことが条件となっています。
このように、特定技能制度は柔軟性が高い一方で、国ごとに採用ルールが異なるのが実情です。企業は採用対象国の協定内容や制度運用を事前に確認し、誤った手続きによる不許可リスクを回避することが重要です。
送り出し機関が多い国と二国間協定の仕組み

送り出し機関の多くは、アジアを中心とした新興国に設置されています。
これらの国々と日本は、外国人労働者の受け入れを円滑かつ適正に行うために、「二国間協定(MOC:Memorandum of Cooperation)」を結んでいます。
この協定は、送り出し機関の認定や監督のルールを明確化し、不正な仲介業者の排除や外国人労働者の保護を目的としています。
二国間協定(MOC)の目的と役割
二国間協定は、日本と送り出し国の政府が公式に取り交わす労働者受け入れの枠組みです。
協定の内容には、送り出し機関の認定基準、費用徴収の上限、手続きの流れ、トラブル発生時の対応方法などが定められています。
主な目的は次の3つです。
悪質な仲介業者の排除
候補者から高額な手数料を徴収したり、虚偽の契約を結んだりするブローカーを排除する。
適正な受け入れと帰国支援の促進
技能実習や特定技能の目的に沿って、学んだ技術を母国で活かす仕組みを整える。
情報共有と相互監督の強化
日本と送り出し国の政府が連携し、送り出し機関の活動状況を随時確認できる体制を整える。
この協定があることで、日本側は信頼できる送り出し機関を選びやすくなり、送り出し国側も不正の温床となる行為を防止できます。
つまり、二国間協定は「透明で持続可能な人材交流のルールブック」といえるのです。
主要締結国の特徴と現地ルールの違い

現在、日本と特定技能に関する二国間協定を締結している国は、ベトナム・フィリピン・インドネシア・ミャンマー・カンボジア・タイ・ネパールなど16カ国前後です。
いずれも若年層が多く、日本語教育への関心が高い国々です。
たとえば:
ベトナム:送り出し機関の数が最も多く、政府が厳格な認定制度を導入。違反行為があれば免許取り消しとなる。
フィリピン:労働雇用省(DOLE)が送り出し事業を統括し、海外労働者管理庁(DMW)がライセンスを発行。手数料や契約条件も細かく規定されている。
ミャンマー:内務省の監督下で許可を受けた機関のみが送出可能。政府管理が厳しく、政治情勢による影響も受けやすい。
カンボジア・ネパール:認定基準が緩やかな反面、現場の教育体制にばらつきがある。
このように、国ごとに制度運用や認定基準が異なるため、企業が採用対象国を選ぶ際には、協定内容や現地制度をしっかり確認しておくことが不可欠です。
また、二国間協定を結んでいない国からの採用は、在外公館(日本大使館・領事館)への事前確認が必要となる場合があります。制度外の採用はトラブルにつながるおそれがあるため、慎重に対応することが求められます。
認定送り出し機関の条件と審査基準
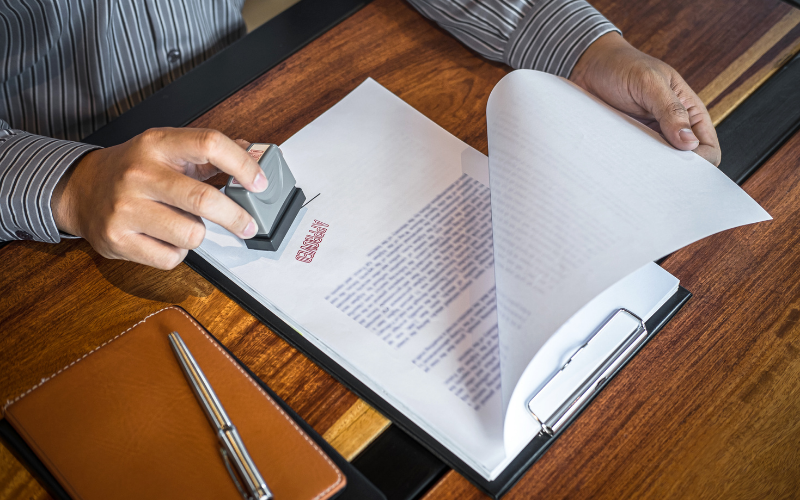
送り出し機関として活動するためには、各国政府および日本側の要件を満たし、正式な認定を受ける必要があります。
この認定制度は、外国人労働者の保護と適正な技能移転を確保するための根幹であり、透明性と公正性を担保する仕組みです。
日本と送り出し国双方で求められる認定要件
送り出し機関の認定要件は、主に日本側では「外国人技能実習法施行規則(第25条)」に基づき、送り出し国では二国間協定(MOC)の内容に沿って定められています。
日本が求める基本的な条件は、以下のようなものです。
公的機関からの推薦を受け、適正に技能実習の申込みを取り次げる能力があること
技能実習生の保護を最優先し、不当な契約・金銭管理を行わないこと
徴収費用の算出基準を明確化・公表し、実習生本人に説明責任を果たすこと
帰国後の就職支援や技能活用のためのサポート体制を整えていること
過去5年以内に法令違反がないこと
一方で、送り出し国側でも、政府が定めるライセンス制度を設けており、教育施設の有無、職員の日本語スキル、財務健全性などを総合的に審査します。
このように、両国の制度が連動することで、一定の水準を満たした機関だけが「認定送り出し機関」として活動できる仕組みになっています。
認定取り消しの要因と注意すべき違反行為
認定を受けた送り出し機関であっても、違反行為があれば認定が取り消されることがあります。
特に多いのは、次のようなケースです。
実習生や家族から保証金・違約金を徴収する行為
虚偽書類の作成・提出による認定申請
監理団体や企業への過剰な手数料請求
実習生の賃金未払い・強制労働などの人権侵害
これらはすべて制度の趣旨に反する行為であり、悪質な場合は政府認定の取り消し、さらには業務停止・刑事罰に至ることもあります。
企業側としても、こうした背景を理解し、**「認定リストに掲載されているか」「最近の取り消し情報がないか」**を確認しておくことが重要です。
外国人技能実習機構(OTIT)のウェブサイトでは、各国政府が認定した送り出し機関一覧や違反事例が公開されています。採用前に一度チェックしておくことで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
送り出し機関の問題点とトラブル事例

送り出し機関は、日本で働きたい外国人と受け入れ企業をつなぐ重要な存在ですが、実際の現場では課題や不正も少なくありません。ここでは、企業が特に注意すべき代表的な問題点とトラブル事例を整理します。
高額な費用徴収・借金負担の実態
もっとも深刻な問題のひとつが、来日前に課される高額な費用負担です。
多くの送り出し機関は、渡航手続きや日本語教育、仲介手数料などの名目で外国人から数十万円を徴収しています。出入国在留管理庁の調査では、実習生が平均50万円前後の費用を支払っているという結果もあります。
一部では、現地で借金をして費用を賄うケースも多く、来日後の生活を圧迫しています。借金返済のために長時間労働や転職を余儀なくされる人もおり、制度全体の健全性を揺るがす要因になっています。
企業としては、費用の内訳や徴収方法が適正かを確認し、不当な負担を強いる送り出し機関との契約を避けることが重要です。
日本語教育・フォロー体制の不備
送り出し機関には、出国前に日本語や生活習慣を指導する教育機能が求められます。
しかし、実際には教育体制が整っていない機関も多く、短期間・低品質の授業や、経験不足の講師による指導が行われているケースもあります。その結果、来日後に日本語での意思疎通が難しく、職場での誤解やトラブルにつながることも。
また、入国後のフォローを監理団体任せにしてしまい、アフターケアが欠如している例も見られます。
良質な送り出し機関は、教育担当者に一定の日本語能力を求め、生活指導や文化理解まで含めたサポートを行っています。採用前に教育内容・期間・講師のスキルを確認することが、トラブル防止の第一歩です。
不正なキックバックやブローカー問題
もう一つの大きな課題が、送り出し機関と監理団体・企業間の癒着です。
現地では、契約獲得を目的とした過剰な接待や、違法な手数料(いわゆるキックバック)の授受が行われることがあります。こうした不正な資金の流れは、最終的に外国人本人の負担増として跳ね返るケースが多いです。
また、認定を受けていない「ブローカー」が仲介に入る事例も後を絶ちません。ブローカーを通すことで、費用の上乗せや虚偽契約、行方不明(失踪)といった深刻な問題が発生することもあります。
このような不正を防ぐためには、政府認定の送り出し機関を選定すること、および契約内容・費用・担当者情報を明確に文書化することが不可欠です。
信頼できる送り出し機関を選ぶポイント

送り出し機関を選定する際は、単に「紹介してもらえるかどうか」ではなく、法令遵守・教育体制・フォローアップの質まで確認することが欠かせません。
ここでは、企業が見極めに役立てられる実践的なポイントを紹介します。
政府認定・日本拠点・教育レベルを確認する
まず最初に確認すべきは、政府による正式な認定を受けているかどうかです。
二国間協定に基づく「外国政府認定送り出し機関一覧(OTIT公式サイト掲載)」に名前があるかを確認しましょう。
認定を受けていない機関を利用すると、虚偽契約やトラブル発生時に適切な対応が得られないリスクがあります。
また、日本国内に支社や駐在事務所を持つかどうかも重要な判断基準です。日本側で直接やり取りできる窓口があると、入国後のサポートが速かつ柔軟に行えます。
さらに、教育内容の質も要チェック。
教育期間(例:3か月以上の日本語・マナー研修)
講師の資格・経験
生活指導や文化教育の有無
といった点を確認し、単なる座学に終わらない、実践的な教育を行っているかを見極めましょう。
担当者対応・情報開示・口コミをチェックする
実際に担当者と話す際の対応も、信頼度を測る大きなヒントです。
質問への回答が明確で迅速か、費用やスケジュールを正直に説明しているかなど、透明性のある対応ができているかを確認しましょう。
さらに、費用の内訳・契約条件・サポート内容をすべて文書化し、開示してくれるかどうかも重要です。口頭説明だけで済ませる機関は注意が必要です。
最近では、SNSや現地コミュニティを通じて口コミや評判を確認することも有効です。実際に利用した実習生や企業の声から、サポート体制やトラブル対応力の差が見えてくることがあります。
トラブルを避けるための実践的チェックリスト
最後に、送り出し機関選びの際に確認すべきチェック項目をまとめます。
✅ 送り出し機関選定チェックリスト
政府認定を受けているか(OTIT・各国労働省の公式リスト参照)
日本に拠点があり、連絡が取りやすい体制か
費用の内訳・契約内容が明示されているか
教育期間・内容・講師の経歴が適正か
問い合わせや説明時の対応が誠実・迅速か
トラブル対応窓口が設置されているか
実習生・企業双方からの口コミ・評判が良好か
これらを事前に確認することで、不正やトラブルを防ぎ、信頼できる外国人採用のパートナーを見つけることができます。
まとめ:送り出し機関に頼らない雇用の可能性
これまで見てきたように、送り出し機関は外国人材の採用を支える重要な存在ですが、一方で不正や負担の温床となるリスクもあります。
今後は、企業が主体的に採用・教育・支援の仕組みを整えることが、より透明で持続的な外国人雇用を実現する鍵となります。
特定技能制度の活用でクリーンな採用を実現
特定技能制度では、原則として送り出し機関を介さずに採用が可能です。
これは、技能実習のような「研修目的」ではなく、労働契約に基づく直接雇用を前提とした制度であるためです。
この仕組みにより、企業は候補者との間に余計な仲介を挟まず、採用コストを抑えつつ、透明性の高い採用を行えます。
また、登録支援機関を活用すれば、入国手続きや生活支援、日本語教育などのフォローも一括して任せられるため、送り出し機関に依存しない運用が可能です。
こうした環境整備により、外国人が安心して働ける職場をつくると同時に、企業側の信頼性や国際的評価の向上にもつながります。
直接採用・現地委託など柔軟な運用のすすめ
今後は、企業が主体的に海外人材を発掘・育成する動きが増えています。
たとえば、現地大学や専門学校と連携してインターンシップや採用説明会を行う「現地直接採用モデル」や、登録支援機関を通じて採用から定着支援までをワンストップで実施する「支援委託モデル」などがその代表例です。
こうした新しい形の採用モデルは、送り出し機関の数や質に左右されず、より自由度の高い採用戦略を取ることができます。
TSBケア・アカデミーでも、こうしたクリーンで持続的な外国人雇用の実現を目指す企業を全力でサポートしています。
🌿 まとめ
送り出し機関を理解し、必要に応じてうまく活用することは重要ですが、最終的な主導権は企業自身にあります。
特定技能制度の正しい理解と、自社に合った採用体制の構築こそが、これからの時代に求められる“信頼される外国人雇用”の形です。
外国人採用でお困りの企業担当者様へ ― クリーンで持続可能な雇用を実現しませんか?
送り出し機関の選定や特定技能の活用は、制度理解と実務対応の両面が求められる分野です。
「どの国から採用すべきか」「信頼できる機関をどう見分けるか」など、お悩みの企業様も多いのではないでしょうか。
TSBケア・アカデミー(https://tsb-care.com/)では、
特定技能・技能実習制度に精通した専門チームが、採用から定着までをトータルでサポートしています。
制度の正しい理解と企業目線の運用設計で、トラブルのない安定した外国人雇用を一緒に実現しましょう。
👉 お問い合わせはこちら