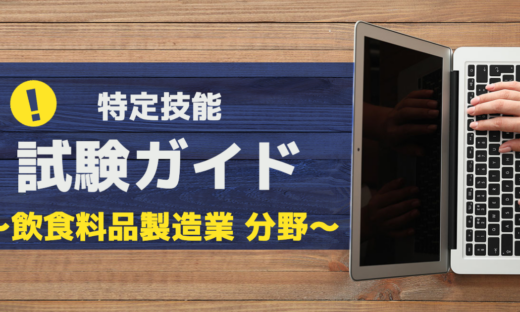特定技能から介護福祉士へ|キャリアアップの流れと資格取得のポイント

介護の現場では、外国人職員の存在が欠かせないものになりつつあります。特定技能で働く多くの人材が、日々の実務を通じて高いスキルと責任感を育てていますが、その先に見据えるべき道が「介護福祉士」へのキャリアアップです。
介護福祉士資格を取得すると、在留資格を「介護」に変更でき、在留期間の制限がなくなります。これは本人の安定した生活とキャリア形成を支えるだけでなく、受け入れ施設にとっても貴重な長期人材の確保につながります。
本記事では、特定技能から介護福祉士へステップアップするまでの流れや必要な条件、企業が行うべき支援体制、そして実際の成功事例をわかりやすく解説します。外国人介護職員の育成に取り組むすべての企業が、安心して次の一歩を踏み出せるよう、実践的な情報をお届けします。
特定技能から介護福祉士へ|キャリアアップの道筋
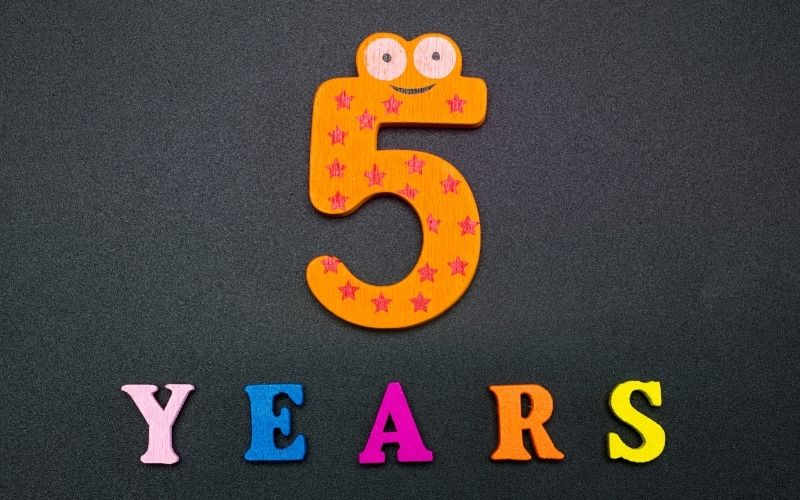
外国人が日本で介護職として長く働くための大きなステップが、「特定技能」から「介護福祉士」へのキャリアアップです。
特定技能で現場経験を積み、日本の介護文化や専門知識を身につけたのち、国家資格である介護福祉士を取得することで、在留資格「介護」へ移行でき、より安定した就労と生活が可能になります。
本章では、両者の制度的な位置づけと、キャリアアップの現実的な道筋について整理します。
特定技能と介護福祉士の位置づけ
特定技能「介護」は、2019年に創設された在留資格で、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。介護の基本的な技能と日本語力(おおむねJLPT N4レベル以上)があれば、就労が認められる点が特徴です。
雇用形態はすべて直接雇用で、派遣や請負は認められていません。
一方、「介護福祉士」は介護分野で唯一の国家資格であり、介護職としての専門性と責任を証明する資格です。介護福祉士の資格を取得した外国人は、在留資格「介護」へ変更することで、在留期間の上限がなくなり、長期的なキャリア形成が可能になります。
つまり、「特定技能」は“介護の入り口”、そして「介護福祉士」は“専門職としての定着”を意味します。企業にとっても、特定技能人材を育成して介護福祉士へ導くことは、人材の定着率や現場の安定性向上に直結する重要な取り組みです。
「5年の壁」を超えるためのキャリア設計
特定技能1号の在留期間は通算5年が上限です。5年を超えて日本で働き続けるためには、介護福祉士資格を取得し、在留資格「介護」へ移行する必要があります。
したがって、キャリア設計のカギは「5年のうちに実務経験3年以上+実務者研修修了+国家試験合格」を達成することにあります。
現実には、勤務と勉強を両立するのは簡単ではありません。しかし、勤務先の支援(学習時間の確保や教材提供、試験対策講座の利用など)が整えば、3〜4年目での合格も十分に現実的です。
試験合格後は、待遇改善や職場でのリーダー的役割も期待され、キャリアアップの実感を得やすい点も魅力です。
「5年の壁」を意識して早期に計画を立てることで、本人のモチベーション維持だけでなく、企業としても長期雇用への道筋を描くことができます。制度を正しく理解し、個々の成長計画と結びつけることが、双方にとって最良の結果を生み出します。
介護福祉士になるための条件と必要な資格
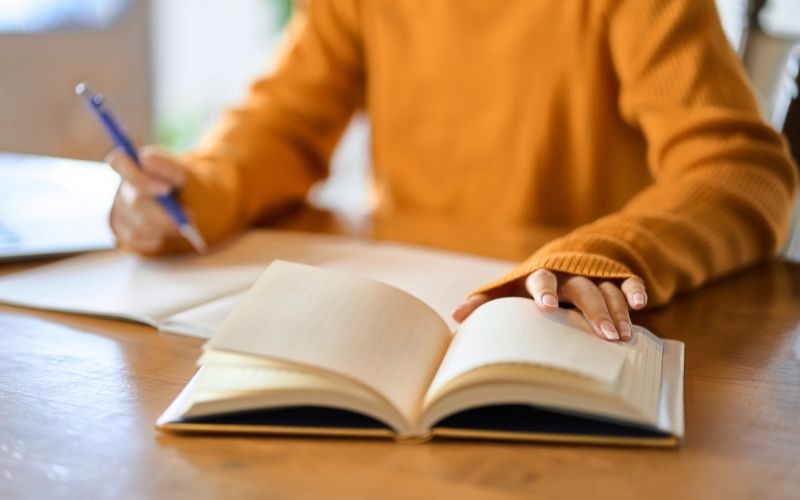
外国人が介護福祉士を目指す場合、日本人と同様に国家試験の受験資格を満たす必要があります。そのためには、一定の実務経験と研修の修了、そして日本語能力の確保が不可欠です。
この章では、介護福祉士を目指すうえで押さえておくべき基本条件と、学習支援のポイントを整理します。
実務経験と実務者研修の修了要件
介護福祉士国家試験を受験するには、介護の実務経験が3年以上あり、かつ「実務者研修」を修了していることが条件です。
実務経験は、介護職員として通算1,095日以上勤務し、540日以上の実働日数が必要とされます。特定技能で働く外国人も、この条件を満たせば受験資格を得られます。
実務者研修は、介護に関する基礎的・専門的知識を体系的に学ぶための450時間以上のカリキュラムです。通信課程を含むため、働きながら受講することも可能ですが、計画的な受講が求められます。
受験直前に修了証が発行されていない場合、試験を受けられないこともあるため注意が必要です。
企業としては、勤務シフトの調整や受講費用の一部補助など、実務者研修を受けやすい環境づくりを整えることが大切です。これにより、外国人職員の意欲を高め、結果的に定着率向上にもつながります。
日本語能力と試験対策のポイント
介護福祉士試験は、介護に関する専門的な日本語が多く登場します。
したがって、日本語能力試験(JLPT)N2レベル程度の読解力・語彙力が求められます。特定技能取得時点でN4相当の人材も多いため、受験までに段階的な日本語力向上を目指すことが現実的です。
試験では、筆記試験のみが行われ、120問中75点前後が合格ラインとされています。外国人受験者は希望すれば、試験時間の1.5倍延長やふりがな付き試験用紙を申請できるなどの配慮制度もあります。
効果的な学習には、日本語学校や介護福祉士試験対策講座を活用するのがおすすめです。最近では、オンラインでのeラーニングやライブ授業など、外国人向けに特化したプログラムも増えています。
施設側としては、教材費や講座費用の補助、勤務時間内の勉強時間確保など、**「学び続けられる仕組み」**を支援することが、試験合格の大きな後押しになります。
介護福祉士試験の概要とスケジュール管理

介護福祉士国家試験は、年に一度実施される国家資格試験で、介護の専門知識や実務理解を総合的に問う内容となっています。
外国人材が受験する場合も、日本人と同じ基準で評価されるため、早い段階からスケジュールを立て、勤務と学習を両立させることが成功の鍵となります。
試験日程・科目構成・合格基準
介護福祉士試験は例年1月下旬に筆記試験、3月に合格発表が行われます。試験はすべて筆記で、マークシート方式によって実施されます。出題科目は、介護の基本・人間と社会・コミュニケーション技術・医療的ケアなど13科目群から構成され、幅広い知識が問われます。
合格基準は総得点の約60%前後が目安とされますが、難易度や出題傾向によって毎年若干の変動があります。実技試験は不要であり、外国人受験者には希望すればふりがな付きの試験用紙や時間延長措置が認められています。
試験問題には専門用語が多く登場するため、日常会話レベルの日本語力だけでは理解が難しいこともあります。早期から模擬試験や過去問演習を取り入れ、出題形式に慣れておくことが大切です。
学習計画モデルと勤務両立の工夫
働きながら学ぶ外国人にとって、限られた時間の中で効率的に学習を進めるには計画性が欠かせません。理想的には、試験の1年前から学習を開始し、週に10〜15時間程度の勉強時間を確保するのが目安です。
初期の半年は基礎用語と介護理論の理解に重点を置き、後半は過去問演習・模擬試験・弱点補強にシフトします。仕事の疲労や夜勤の影響も考慮し、無理のないスケジュールを組むことが継続のコツです。
企業側の支援としては、勤務シフトの柔軟化や、試験直前の特別休暇制度なども有効です。また、同じ目標を持つ仲間と一緒に学ぶ「グループ学習」や、オンライン教材を活用したスキマ学習も効果的です。
学習を「個人の努力」に任せず、職場全体で応援する文化を築くことが、合格率を高める最も確実な方法と言えるでしょう。
合格後の手続き|在留資格「介護」への変更
介護福祉士試験に合格した外国人が次に行うべきステップが、在留資格を「特定技能」から「介護」へ変更する手続きです。
この資格変更を行うことで、在留期間の上限がなくなり、長期的なキャリア形成や永住申請への道が開けます。企業としても、信頼できる人材を継続的に雇用できるため、双方にとって大きなメリットがあります。
在留資格変更の流れと必要書類
在留資格変更の申請は、地方出入国在留管理局で行います。提出タイミングは、介護福祉士登録証の交付後が一般的です。主な流れは次のとおりです。
介護福祉士登録証の取得(試験合格後、登録手数料を支払い発行)
↓
在留資格変更許可申請書の作成・提出
↓
必要書類の添付(以下参照)
↓
在留カード
↓
介護福祉士登録証の写し
↓
雇用契約書または内定通知書
↓
事業所の概要資料(パンフレット等)
↓
雇用先の登記事項証明書
↓
申請理由書(企業側が作成)
↓
審査期間:約1〜2か月
↓
許可後、新しい在留カードが交付される
申請時には、勤務先の安定性や継続雇用の見込みが重視されます。受け入れ企業は、申請書類の作成サポートやスケジュール管理を行うことで、スムーズな在留資格変更を支援することが大切です。
資格変更後の待遇・キャリアの広がり
在留資格「介護」へ変更すると、在留期間の上限がなくなり、更新を続ける限り日本で働き続けることが可能になります。また、業務範囲の制限もなく、特定技能では認められなかった訪問介護や地域包括支援などの在宅系サービスにも従事できます。
さらに、介護福祉士として経験を積むことで、サービス提供責任者・リーダー職・教育担当など、より専門性の高いポジションにキャリアアップできる道も開かれます。
待遇面でも、資格手当や昇給などの優遇を設ける施設が多く、特定技能時代よりも安定した収入を得られるケースが一般的です。また、在留資格「介護」で一定期間就労すれば、永住申請の要件を満たす可能性もあり、将来的な生活基盤の安定につながります。
資格取得と在留資格変更は、本人の努力と企業の支援が結びついた「成果」です。介護福祉士としてのスタートラインに立った後も、職場全体で成長を後押しする体制を整えることが、持続的な人材育成のカギとなります。
企業が行うべき支援と成功のポイント

外国人介護職員が介護福祉士として成長するには、学習面だけでなく、生活やメンタル面のサポートも欠かせません。
企業が一体となって環境を整えることで、合格率の向上と職員の定着が同時に実現します。この章では、支援の3本柱とロールモデル育成による好循環づくりを解説します。
学習・生活・メンタル支援の3本柱
外国人職員のキャリアアップ支援は、「学習支援」「生活支援」「メンタル支援」の3つを軸に設計することが効果的です。
学習支援
国家試験対策の教材提供や日本語講師の派遣、外部スクールとの連携を通じ、継続的に学べる環境を整えることが重要です。勤務シフトを柔軟に調整し、試験前の学習時間を確保する企業も増えています。
生活支援
安定した生活があってこそ学習が続けられます。住居探し、交通手段の確保、生活相談などを受けられる窓口を設けることで、離職リスクを大幅に減らせます。地域とのつながりを支援するイベントや交流機会の提供も有効です。
メンタル支援
言語の壁や文化の違いによる孤立感を防ぐため、定期的な面談やグループミーティングを実施し、悩みを早期に共有できる環境を整えましょう。管理者や日本人職員に異文化理解の研修を行うことも、信頼関係づくりに大きく役立ちます。
この3本柱を継続的に実践することで、外国人職員が安心して働き、試験に集中できる職場づくりが可能になります。
合格者のロールモデル化で定着率を高める
介護福祉士試験に合格した外国人職員は、同僚にとって強いモチベーション源となります。合格者を「ロールモデル」として位置づけ、後輩の学習支援やOJT教育に関わってもらうことで、現場全体の士気と定着率が向上します。
具体的には、合格者インタビューを社内掲示やSNSで共有する、合格祝いの表彰を行う、指導担当者として研修に参加してもらうなどの取り組みが効果的です。こうした施策は、学習意欲を高めるだけでなく、組織への帰属意識を強める働きもあります。
また、企業側にとっても「資格取得を支援する職場」としてのブランド力が高まり、新たな外国人材の採用にも好循環を生み出します。
キャリアアップ支援の成功事例と実践ポイント
外国人介護職員のキャリアアップ支援は、単なる資格取得支援にとどまりません。本人の努力を引き出す環境づくりと、企業の伴走体制が組み合わさって初めて成果が生まれます。
ここでは、実際に「特定技能」から「介護福祉士」へステップアップした事例と、定着につながった企業側の支援方法を紹介します。
特定技能から介護福祉士へ合格した事例
ある中規模介護施設では、ベトナム出身の職員が特定技能で入職後、3年間の実務経験と実務者研修を経て介護福祉士国家試験に合格しました。
この職員は来日当初、日本語での記録業務に苦戦していましたが、施設が週1回の勉強会を設け、日本人先輩職員が付き添う形でサポートを継続。勤務時間外の勉強負担を軽減するため、シフトを調整し、夜勤前後に学習時間を確保できるよう配慮しました。
結果として本人は合格し、現在は後輩の学習サポートや新人研修にも関わる立場に。合格後は在留資格「介護」へ変更し、施設の中心的な人材として長期雇用が実現しました。この事例は、「日常的な支援」と「本人の主体性」を両立させることが成功の鍵であることを示しています。
企業の支援体制が定着率を高めたケース
別の法人では、複数の外国人職員が同時に介護福祉士を目指すチーム制を導入。月1回の模擬試験会や、グループ単位での進捗確認を行うことで、「仲間と学ぶ」モチベーションを高めました。
さらに、企業側は試験対策費用の一部を補助し、合格後には報奨金と昇給を明確に設定。こうした仕組みが学習意欲を支えました。
その結果、3年以内に5名が合格し、離職率が大幅に低下。合格者が教育係として次世代を育成する体制も定着しました。
企業担当者は「支援を投資と捉えることで、長期的な戦力化が進む」と語っています。
このように、支援の“仕組み化”と“共有文化の醸成”が、外国人介護職員のキャリアアップを持続的に支える鍵となります。
まとめ:特定技能から介護福祉士へ──5年で未来をつくる

特定技能で働く外国人が介護福祉士を目指す5年間は、本人にとっても企業にとっても成長の時間です。制度上の「5年の壁」は確かに存在しますが、計画的に学びと実務経験を積めば、資格取得と在留資格「介護」への移行は十分に可能です。
外国人職員が専門職として定着することで、現場の知識共有が進み、利用者にとってもより安心・安定した介護サービスが提供できます。これは単なる“雇用継続”ではなく、現場全体の質を高める長期的人材戦略といえるでしょう。
介護現場の安定化と人材育成の鍵に
介護福祉士へのキャリアアップは、外国人材にとって「日本で生きていく力」を得る道であり、企業にとっては「信頼できる中核人材を育てる」道です。
試験合格をゴールにするのではなく、その後のキャリア形成やチームづくりまで見据えることで、職員が誇りを持って働ける職場が生まれます。
介護の未来を支えるのは、制度ではなく「人」です。
外国人職員が安心して学び、成長できる環境を整えることこそが、これからの介護現場の安定化につながります。
TSBケア・アカデミーでは、こうしたキャリア形成を支援する研修・相談体制を整えています。
外国人材の採用や資格取得支援をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。