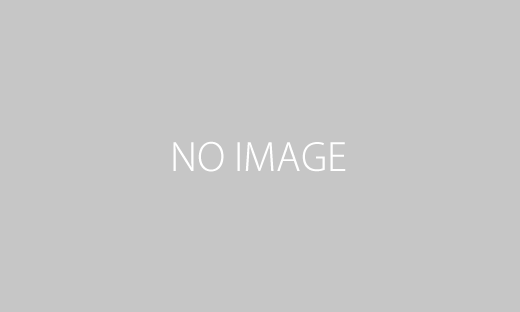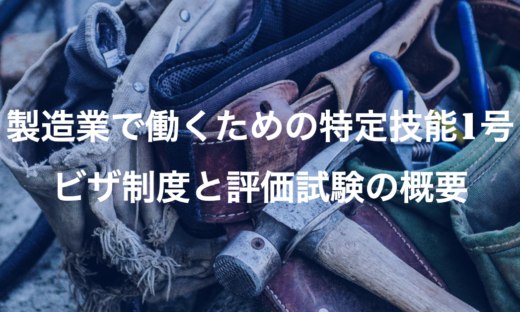外国人雇用で使える助成金まとめ|企業が押さえるべき条件と活用ポイント【2025最新版】

〜外国人雇用と助成金の基本をわかりやすく〜
外国人雇用を進める企業にとって、助成金は採用コストを抑えながら働きやすい職場づくりを促進できる重要な制度です。
しかし、助成金は種類が多く、対象者・条件・必要書類が制度ごとに大きく異なるため、「どれが使えるのか」「どの在留資格が対象なのか」が分かりづらく、チャンスを逃してしまう企業も少なくありません。
特に特定技能や留学生アルバイト、技人国など、外国人雇用では制度の理解と申請の“タイミング”が成否を分けます。制度の目的や要件を正しく押さえておけば、自社に最適な助成金を選び、申請漏れを防ぎながら、外国人材の定着・スキルアップにつなげることができます。
本記事では、外国人雇用で活用できる主要な助成金を整理しつつ、在留資格別のポイント、自治体の支援制度、申請時に失敗しやすい点などをわかりやすく解説します。
初めて外国人を採用する企業も、すでに受け入れを進めている企業も、助成金を“安全に正しく使う”ための基礎が身につく内容です。
外国人雇用と助成金制度の基本
外国人材を受け入れる企業にとって、助成金は負担を大きく軽減してくれる重要な制度です。
特に日本語教育や生活サポート、多文化コミュニケーションへの配慮など、外国人雇用には日本人と異なる準備が必要な場合があります。こうした「受け入れに伴うコスト」を国が支援することで、企業はより安心して外国人材の採用・定着に取り組むことができます。
まずは、助成金がなぜ外国人雇用と相性が良いのか、その基本的な位置づけを確認しましょう。
外国人雇用で助成金が用意されている理由
外国人材は日本の労働力不足を補う重要な存在として注目されていますが、その一方で受け入れには日本語指導、生活サポート、文化の違いを踏まえた教育など、企業側の追加負担が生じやすい側面があります。
そこで国は、外国人が働きやすい環境を企業が整備できるよう、「多言語マニュアルの作成」「安全衛生の改善」「日本語研修の導入」などを助成金で支援しています。
これにより、企業は採用コストを抑えながら定着率を高めることができ、外国人本人も安心して長く働くことができます。助成金は、外国人雇用の成功に向けて企業と行政が協力するための“共同ツール”として機能しているのです。
助成金と補助金の違い・共通ルール
助成金は、法律や制度に基づき「条件を満たせば支給される」後払い型の支援制度で、一方の補助金は採択制であり、審査を通過しなければ受給できません。
どちらにも共通するのは「事前の計画」「実施記録」「証拠書類」が必須であることです。外国人雇用では、在留カードの確認、雇用契約書、日本語研修の実施記録など、外国人特有の書類も必要になります。
また、期限遅れや不備があると支給されないことも多いため、適切な労務管理が欠かせません。補助金との併用が可能な場合もありますが、費用按分や重複計上に注意が必要です。
外国人雇用で使える国の助成金
外国人雇用で最も利用しやすいのが厚生労働省の助成金です。特に日本語教育、安全衛生対策、キャリア形成、職場環境整備など、外国人の“働きやすさ”と“定着”に直結する取り組みが幅広く対象になります。
ここでは、外国人雇用と相性が良い代表的な助成金をまとめます。
人材確保等支援助成金(就労環境整備)
外国人材を受け入れるとき、多言語化されたマニュアル、安全衛生教育、生活相談窓口など“現場が働きやすくなる仕組み”を整えると支給される助成金です。
特に特定技能の受け入れでは、企業が実施すべき支援項目が多いため、この助成金を活用することで経費を大幅に削減できます。最大72万円の支給が可能で、申請には「計画届け出 → 実施 → 実績報告」の3段階が必要です。
外国人の早期離職が多い企業にとっては、非常に効果的な支援制度といえます。
人材開発支援助成金(訓練・キャリア形成)
日本語研修、業務に必要な技能研修、資格取得支援など、“教育訓練”に幅広く使える助成金です。外国人材にとって日本語教育は定着に欠かせない要素であり、「仕事で使う日本語研修」も対象になりやすいのが特徴です。
OFF-JT、OJT、eラーニングなど実施方法も柔軟で、特定技能の実務習熟にも向いています。継続して教育環境を整えたい企業には、最も活用しやすい助成金のひとつです。
キャリアアップ助成金・業務改善助成金など
キャリアアップ助成金は、非正規雇用の外国人を正社員化した場合などに活用できます。等級制度や賃金規定の整備を伴うため、日本人社員にもプラスの影響が出やすい制度です。
また業務改善助成金は、生産性を向上させる設備導入費用の一部を支援する制度で、外国人が安全に働ける環境改善にも応用できます。外国人雇用そのものを対象としていなくても、“働きやすさ”の向上に役立つ助成金は多く存在します。
トライアル雇用助成金
外国人材を本採用する前に“試行雇用”として受け入れる企業に支給される制度です。特に、日本語力や職場との相性を確かめたい場合に活用しやすく、特定技能候補者や留学生の採用でも利用されています。
一定期間(原則3カ月)雇用した企業に月額4万円の支給が行われるため、受け入れリスクを抑えながら雇用判断ができるメリットがあります。
在留資格別に活用できる助成金
外国人材は在留資格によって働き方や支援内容が異なるため、活用しやすい助成金も変わります。ここでは特定技能・技能実習・技人国・高度専門職など、主要な在留資格別にポイントを整理します。
特定技能・技能実習からの移行で使いやすい制度
特定技能は日本語教育や生活支援が必須で、環境整備が助成金の対象になりやすい在留資格です。
多言語マニュアル、安全衛生の改善、日本語研修などが“就労環境整備”に該当しやすく、人材確保等支援助成金との相性が非常に良いのが特徴。
技能実習→特定技能へ移行する場合は、教育訓練計画を見直すタイミングでもあり、人材開発支援助成金で研修体系を整える企業も増えています。
技人国・高度専門職・留学生など一般就労で使える制度
技人国や高度専門職など「専門系の外国人材」は、キャリア形成支援や資格取得支援、OJT強化が助成金の対象となるケースが多いです。
特に日本語力を伸ばしたい留学生の採用においては、日本語研修を含む教育体系の整備が効果的で、人材開発支援助成金が活用されます。また、正社員登用を予定している場合は、キャリアアップ助成金が選択肢に入ります。
個人事業主・中小企業が申請する際のポイント
中小企業や個人事業主でも助成金は十分利用できますが、「計画書の提出期限」「労務管理」「実施記録」の3点が特に重要です。外国人の場合、在留資格・支援記録の確認も必要となるため、社労士や登録支援機関と連携しながら申請する企業が増えています。
実務負担を抑えつつ制度を活用するには、専門家のサポートが有効です。
自治体の補助金・支援制度
国の助成金だけでなく、自治体が独自に設けている外国人雇用向けの支援制度も活用することで、企業は受け入れ負担をさらに軽減できます。
自治体は地域の実情に合わせた支援を行っており、日本語教室の運営、通訳派遣、職場環境整備の補助など、現場で役立つ支援内容が多いことが特徴です。地域の制度は比較的申請しやすいものが多く、中小企業でも取り組みやすいのが魅力です。
主要自治体の代表的な補助金例
自治体が実施する外国人支援制度は多岐にわたり、特に大都市圏では企業向けの支援内容が充実しています。例えば東京都では、日本語教育の導入支援、通訳派遣、生活相談窓口の運営などが整備されています。
名古屋市では外国人雇用企業向けの研修費用を補助する制度があり、京都市では国際交流会館と連携した日本語講座や生活支援相談を実施しています。
こうした自治体の支援は、企業が単独で実施するには負担が大きい日本語教育や生活サポートを“地域全体で支える仕組み”として活用できる点が大きなメリットです。地域の制度を把握することで、外国人材の定着率向上にもつながります。
分野別の補助制度と探し方
自治体の支援制度は、介護・建設・製造など特定分野に特化したものも多く、自社の業種に合わせて活用できる補助金を探すことが可能です。例えば介護分野では、外国人介護職員の研修費用を支援する制度が設けられている自治体もあります。
これらの情報は「自治体名+外国人+補助金」「多文化共生」「日本語教育」などのキーワードで検索すると見つけやすく、国際交流協会や外国人支援センターが窓口となる場合も多くあります。
自治体の支援は、国の助成金ではカバーしづらい“地域ごとの課題”に寄り添った内容が多いため、組み合わせて活用することで受け入れ負担を大きく軽減できます。
自治体が提供する日本語教育・生活相談・通訳支援の活用ポイント
多くの自治体では、外国人住民のために日本語教室や生活相談窓口、通訳派遣などを実施しています。企業が自前で日本語教育を整えるのは大きな負担になりますが、自治体の日本語教室を活用すれば無料〜低負担で継続的な学習環境を提供できます。
また、外国人が生活面で困った際に相談できる窓口があることで、企業が生活支援をすべて抱え込む必要がなくなり、離職防止にもつながります。
さらに、行政手続きや病院受診時に無料の通訳支援を使える自治体も多く、慣れない生活の不安を軽減する効果は非常に大きいです。こうした地域資源をうまく組み合わせれば、企業は過度に負担を背負うことなく外国人材の定着を支えることができます。
助成金申請の実務ポイント
助成金を確実に受給するためには、制度の理解だけではなく、実務面での適切な準備・記録・期限管理が重要です。外国人雇用では在留資格の確認や支援記録など独自のポイントもあり、申請負担が大きくなりがちです。
ここでは、企業が押さえておきたい申請の基本フローや失敗しやすい場面、複数制度を併用する際の注意点を整理し、ムダのない手続きと不支給リスク回避につながる実務対応を解説します。
申請の基本フロー
助成金申請は「事前準備 → 計画届提出 → 取り組み実施 → 実績報告 → 支給決定」という流れが一般的です。まず、自社の取り組みが助成金の要件に合致しているかを確認し、期限内に計画書を提出する必要があります。
外国人雇用の場合、日本語研修の実施記録、生活支援記録、在留カードの写しなど、通常より記録する項目が増えるため、日常の労務管理を整えることが重要です。
実施段階では、計画書と異なる内容の実施や記録漏れがあると不支給の原因になります。実績報告では、領収書・出勤簿・研修記録など多数の証拠書類が必要となり、提出期限を過ぎると申請自体が無効になることもあります。
手続きをスムーズに進めるには、社労士や支援機関との連携が効果的です。
よくある失敗例とチェックポイント
助成金申請で多いトラブルは、提出期限の遅延、記録不足、計画書と実施内容の不一致です。特に外国人雇用では、在留資格と実際の業務内容が一致していない、支援計画と支援実績に差がある、研修内容の証拠(写真・日誌・名簿)の不足など、外国人特有の不備が生じやすい傾向があります。
また、労働条件通知書や出勤簿の記載ミスも審査に影響します。申請前には、「書類の整合性」「計画と実績の一致」「在留資格と業務内容の一致」を必ずチェックし、担当者だけで抱え込まず、社労士や登録支援機関のダブルチェックを行うと不支給のリスクを大幅に減らせます。
助成金は“細かい管理を丁寧に積み上げること”が成功の鍵です。
他制度との併用と費用按分の考え方
助成金は複数制度を併用できる場合がありますが、同じ費用を二重で計上することは禁止されています。
たとえば、日本語教育を人材開発支援助成金で支援を受けつつ、同じ研修費用を別の制度に申請することはできません。このような場合は費用按分を行い、どの制度の対象とするのかを明確に分ける必要があります。
設備投資系の助成金と教育訓練系の助成金を組み合わせるなど、目的が異なる制度との併用は認められるケースが多いですが、判断が難しい場面では専門家に確認することが不可欠です。
外国人雇用の場合は、日本語教育・支援業務・環境整備など複数の費用が発生するため、併用の管理が複雑になりやすい点に注意が必要です。併用制度を正しく理解すれば、企業は負担を抑えつつ効果的に環境整備を進めることができます。
不正受給を防ぐためのポイント
助成金は企業の負担を軽減する有効な制度ですが、要件を誤解したり手続きを怠ったりすると、不正受給と判断されるリスクがあります。
不正受給は返還だけではなく、今後の申請禁止や企業名公表など深刻な影響を及ぼすため、制度を正しく理解し、適正に運用することが重要です。
ここでは、審査に落ちやすいケースや不正受給とみなされる行為を整理し、助成金に依存しない採用の考え方をまとめます。
審査に落ちやすいケース
助成金申請で最も多い不支給理由は、“書類の不備” と “実態と記録の不一致” です。たとえば、出勤簿・賃金台帳・就業規則の記載が矛盾していたり、申請内容と実際の勤務実態が異なっていたりする場合、審査に通りません。
また、雇用契約書が曖昧なまま申請したり、必要な労働保険・社会保険に未加入だったりすると、その時点で不適格となります。さらに、外国人雇用の場合は在留資格・業務内容の整合性も重視されるため、特定技能・技人国などの在留要件を満たしていないと助成金の対象外となることがあります。
日頃から労務管理と記録整備を徹底しておくことが、助成金審査を通過するうえでの最大のポイントです。
不正受給と認定される行為
不正受給とみなされる典型例には、「架空の雇用」「実態と異なる勤務時間の申告」「書類の改ざん」があります。
また、実際には解雇同然であるにもかかわらず、継続雇用しているかのように装って助成金を受給したり、給与を支払っていないのに支給したと申請するケースも不正と判断されます。外国人雇用においては、在留資格で認められていない業務に従事させていた場合も、助成金の返還対象となる可能性があります。
不正受給が発覚すると、受給額の返還に加え、企業名の公表や行政指導、場合によっては刑事罰が科されることもあるため、「知らなかった」「ミスだった」では済まされません。
助成金ありきにしない採用の考え方
助成金はあくまで“採用や人材育成を後押しするための補助制度”であり、助成金を受給するために採用するという逆転した発想はリスクにつながります。
特に外国人雇用では、在留資格・業務内容・労働条件など守るべきルールが多く、助成金を目的に採用を進めるとミスマッチやトラブルの原因になりかねません。
企業はまず「自社がどのような外国人材を必要としているか」「どのポジションで長期活躍できるか」を明確にし、そのうえで助成金を“使えるなら活用する”程度の位置づけにしておくことが重要です。
助成金は便利な制度ですが、正しく使いながら、自社に合った外国人材の採用・育成を軸に据えることが、長期的な成功につながります。
まとめ
外国人雇用に活用できる助成金や支援制度は、国・自治体・関連団体によって多岐にわたります。
制度を上手に使うことで、日本語教育や支援体制の整備、研修費用や環境改善などのコストを抑えつつ、安心して受け入れを進めることができます。
しかし、助成金は「使えれば得をする制度」ではなく、「正しい理解と適切な管理が必要な制度」です。自社の状況に合わせて無理なく活用し、外国人材が長く働き続けられる環境づくりにつなげることが大切です。
自社に合った制度の選び方
制度選びで最も大切なのは、「目的」と「対象費用」を明確にすることです。日本語教育を強化したいのか、研修体制を整えたいのか、職場環境を改善したいのかによって選ぶべき助成金は変わります。
また、特定技能や技能実習からの移行など、在留資格ごとに使いやすい制度も異なります。まずは自社の課題を整理し、「どの費用が助成対象になり得るか」を確認してから制度を選ぶと失敗しにくくなります。
制度ごとに要件や期限が細かく定められているため、事前の情報収集が非常に重要です。複数の制度を比較したうえで「使えるものだけを選ぶ」のではなく、「無理なく続けられる制度」を選ぶことが、長期的な外国人受け入れ成功につながります。
専門家と連携して無理なく活用する
助成金申請は書類作成・記録管理・期限遵守など実務負担が大きく、担当者だけで完結させるのは難しいケースが多くあります。特に外国人雇用では支援記録や在留資格の管理など追加の手間が発生し、ミスが不支給につながるリスクも高まります。
こうした負担を軽減するためには、社労士・行政書士・登録支援機関など“外国人雇用に詳しい専門家”と連携することが効果的です。専門家と協力することで、制度選定から申請準備、計画書の作成、実績報告までスムーズに進めることができ、不支給のリスクを大幅に減らせます。
自社で抱え込みすぎず、外部の力を上手に活用することが、助成金を継続的に利用するための最短ルートです。
〜外国人雇用のことなら、まずはTSBケアアカデミーへご相談ください〜
助成金の活用や特定技能の受け入れは、制度が複雑で一人で抱え込むと負担になりがちです。TSBケアアカデミーでは、外国人雇用に精通したスタッフが、制度選びから申請準備、受け入れ後の支援まで丁寧にサポートします。
「どの助成金が使えるかわからない」「申請が大変で手が回らない」と感じたら、どうぞお気軽にご相談ください。
👉 TSBケアアカデミー
👉 お問い合わせはこちら
専門家と一緒に進めることで、助成金の活用も、外国人材の定着も格段にスムーズになります。まずは一度、気軽にご相談ください。